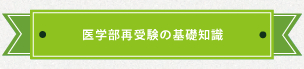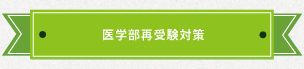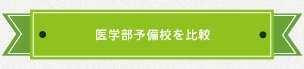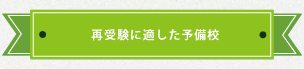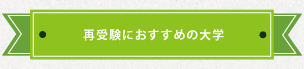医学部再受験の勉強法・勉強時間を紹介

近年、不景気の中で医師という職業が高収入であり、安定した資格職であることから、医者を目指して医学部受験にブームがきており、現役生、浪人生だけではなく社会人経験を経て医学部に志望する医学部再受験生も増えてきています。
しかしながら医学部受験は非常に合格難易度が高く、狭き門をくぐり抜ける必要があることから、社会人として受験勉強から離れていた医学部再受験生たちにとっては、よりいっそうハードルが高くなっているのも事実です。
では医学部再受験を成功に収めるには、どういった対策をとる必要があるのか見ていきましょう。
医学部再受験のポイント、まず何から始める?

医学部受験では他学部の入試と比べて科目数が多く、面接や小論文も課せられる場合が多いです。
そして問題の難易度も医学部だけは別問題であることもあり、非常に難易度の高い構成になっていることがほとんどです。
受験勉強の時間をとりやすい現役生や浪人生であっても簡単には合格できず、毎年多くの学生があと一歩及ばず涙をのんでいます。
ましてや受験勉強から離れていた医学部再受験生にとって、医学部合格というのは「いばらの道」であり、合格率もかなり低いと言われています。
また、再受験生は現役生や浪人生に比べて記憶力が低下していたり、理解の定着に時間がかかることがほとんどであり、年齢的に不利になることが多く、並大抵の努力では思うように成績が上がりません。
したがって医学部再受験を成功させるには、綿密な勉強計画を立てたうえで適切な志望校選択と効率のいい勉強法の確立から始めることが重要となってきます。
国公立大学の勉強法・勉強時間
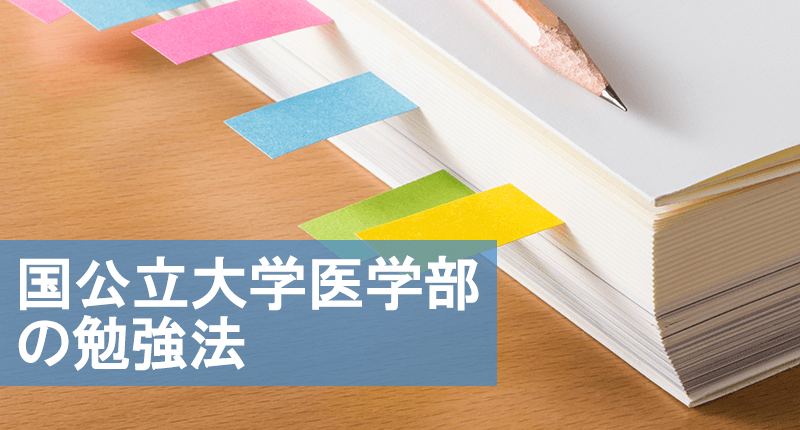
国公立大学医学部の合格には私立大学医学部よりも共通テスト(旧センター試験)が直接的に関係してくるため、対策も多く取る必要があります。
また、国公立医学部であれば共通テストは90%の得点率を確保したうえで二次試験で高得点をとる必要があり、私立大学医学部以上に対策を入念に取るべきです。
共通テスト(旧センター試験)の勉強法
国公立大学医学部志望であれば共通テスト対策は重点的にやるべきですが、共通テストは2021年度入試から導入されたばかりで、過去問もほとんどなく、対策問題集などもセンター試験の対策本とほとんど変わっていないのが現状です。
共通テストではより思考力を問う問題が増えていますが、本質的な部分はセンター試験と大きく変わってはいないので、センター試験の対策本は共通テスト対策として有効です。
共通テストの対策本をやり終わったら、センター試験対策の問題集を重ねてやるとよいでしょう。
夏ごろから共通テストを見据えた基礎固めをして、12月ごろからは共通テスト対策に1日の勉強量の8割ほど力を注ぐ形がベスト。
特に医学部再受験生の場合、受験勉強の内容を忘れていることが多いので、計画的な対策が高得点獲得には必須となります。
二次試験の勉強法
国公立大学医学部の数学はほとんどの場合全問記述式であり、答案作成力が必要となります。
非常に難易度の高い問題から構成されていることが多く、難問対策が必須なのは間違いないですが、それ以上に大事なのは基礎力です。
難問は基礎の積み重ねで解けるものなので、早いうちから難問に手を出すのではなく、夏までに基礎作りを徹底することが大事です。
英語はオーソドックスな問題が多く、長文の題材も自然科学系や文化系、ロボットに関するものなど読みやすいものが多いため、日頃から長文読解を欠かさずやることが何よりの対策といえます。
医学部再受験生は社会経験があり、英語を使う機会もあることが多いので、他の受験生と比べて再受験生がアドバンテージを持っている部分でもあると思います。
英語力が落ちないようにカバーしつつ、いかに他の理系科目に時間を割けるかが大事となります。
理科2科目については特に文系出身の医学部再受験生が一番苦労する科目です。
物理、化学、生物問わず高レベルな問題が出題され、物理基礎、化学基礎、生物基礎しかやっていない文系出身者だと、たった1年間で2科目を医学部合格レベルまで上げる必要があり厳しい戦いといえます。
なるべく綿密な計画を立てて演習を積むことが何よりも大事となります。
国語は東京大学、京都大学、名古屋大学、山形大学では二次試験でも出題されています。
非常に難易度の高い文章を読む必要があり、共通テストでしか国語を使わない他大学医学部と比べて科目数が増えることから、当然負担は大きくなります。
少しでも負担を軽くしたい医学部再受験生にとっては、国語を出題科目としている大学は志望校とするにはリスクが高いことが分かります。
国公立大学医学部に必要な勉強時間の目安
国公立・私立大学によらず、医学部合格には合計で5000時間は勉強に充てる必要があると言われることもあります。
国公立大学医学部の合格には私立大学医学部よりも共通テスト(旧センター試験)が直接的に関係してくるため、対策も多く取る必要があることから、当然勉強時間も私立大学医学部より多くなります。
また共通テスト(旧センター試験)でも90%程度の高得点を狙う必要があり、対策を軽くすることもできないのが特徴。
しかし実際のところ、医学部再受験生で5000時間も新しくやるには長い年月がかかってしまうので、いかに効率よく勉強を進めるかが合格のカギになってくるのは明らかです。
では国公立大学医学部志望の医学部再受験生の場合、合格に必要な勉強時間はどれくらいなのでしょうか。
1日あたりで考えると、できれば普段から1日10時間前後の勉強時間を確保はしておきたいです。
理由としては、現役生の場合はだいたい1日10時間前後の勉強を夏明けから開始してくるので、医学部再受験生の場合は少なくとも現役生より勉強時間が少ないということは避けたいです。
直前期ではもっと増やす必要があり、1日12時間近くの勉強を目指しておくといいと思います。
学業・仕事との両立をしながら合格を目指している医学部再受験生は、週で50時間などとやや大きな単位での計画をたて、通勤やお昼休憩などのスキマ時間を有効に活用すべきです。
とはいえ、学業・仕事の両立はただでさえ難しい医学部再受験をさらに難しくしてしまうので、できれば直前期だけでも医学部再受験の勉強に全力で打ち込めるような環境作りが大切です。
私立大学の勉強法・勉強時間

私立大学医学部の受験では、共通テスト利用入試以外は特に共通テストに関係がないことから、対策自体は一見減ります。
しかしその分、各大学の筆記試験の比重が大きくなるのでミスの許されない戦いになります。
入試という緊張感のある場で自分の実力を出すには、各大学に合わせた綿密な対策と十分な演習を積むことが必要になってきます。
英語
私立大学医学部の英語はクセが強いことが多く、超長文や医学系の文章が出題されることもしばしばなので、直前期には各大学の過去問をもとにした演習が一段と大事になってきます。
私立大学医学部で出題される医学系の文章では、医学英語に注釈がついておらず知っている前提でくることもあるので、最低限の医学英語は覚えておいて損はありません。
ただし、私立大学医学部の英語は大学ごとにかなり傾向があって対策がしやすいことも一つの特徴なので、過去問を参考にしてどういった問題が多いのかを把握することも重要です。
また、文章自体は決して難易度の高すぎるわけではなく、むしろ使われる文法は平易なことが多いため、医学部再受験生は日々の英語学習でも十分に対応できると思います。
数学
私立大学医学部の数学は形式が共通テストのような穴埋め形式のものや国公立大学医学部と同様の全問記述である場合が多いです。
全問記述の場合は国公立大学医学部の場合と同じような対策で大丈夫なのですが、穴埋め形式のものは慣れていないと難しいです。
穴埋めだから簡単だと思うのではなく、難易度の高い問題を決められた誘導に乗って解く問題だという認識が必要です。
センター試験や共通テストの数学の過去問を最初に練習として解き、そのあとに大学の過去問を軸に演習を行うと効果的な過去問演習を行えるでしょう。
理科二科目
国公立大学医学部の欄でも言及しましたが、文系出身者の医学部再受験生にとっては一番の難関ポイントです。
特に私立大学医学部の理科は全体的に変わった題材を扱うことが多く、時には医学的な内容と物理と化学が絡んだ問題や、生物でもやや医学的な内容を含んだ内容であることもあります。
ただし、いくら変わった題材が出たとしても本質的には標準的な問題であり、落ち着いて解けばいつも問題集で解いている問題と同じように解けるはず。
また、そういった問題の場合は完答を目指す必要はなく、あくまでも他の受験生が解いた問題を自分も落とさなければいいので、焦りは禁物です。
まずは4月からの勉強計画を練り、どの時期までに基礎を固めておくか、どの時期から二次試験対策を行うのかを計画通りに実行することは、再受験生が最短距離で合格するのに必須です。
面接・小論文
私立大学医学部では一般的に国公立大学医学部よりも面接・小論文を重視している大学が多いと言われています。
たかが面接、たかが小論文だと思っていると、インフォームドコンセントやヒトゲノム計画といった医療の背景知識がないと答えられない質問や、専門性の高い題材が来ることもあるので全く太刀打ちできないでしょう。
そうならないために、日頃から新聞記事やニュースを参考にして背景知識を蓄えておくことをおすすめします。
また医学部再受験生の場合は社会人経験があることから、所作などはやや厳しめにみられる印象なので、注意してください。
直前期になると各医学部予備校が大学別の面接・小論文講座を開講しており、無料の体験講座や外部生も受講できる講座もあるので受けてみるのも1つの方法です。
私立大学医学部に必要な勉強時間の目安
私立大学医学部では共通テスト(旧センター試験)対策が必要となる国公立大学医学部よりも、対策自体は軽くなることは事実です。
しかし、国公立・私立大学によらず、医学部合格には合計で5000時間は勉強に充てる必要があると言われることもあることから、やはり相当の勉強量は要求されます。
私立大学医学部の場合は各大学の出題傾向・クセなどに影響されることが多く、対策が一筋縄ではいかないことが特徴です。
また、国公立大学医学部の方が問題は難しいと思うかもしれませんが、意外と難易度的には私立大学医学部の方が難問・奇問を解かなくてはならないことが多いです。
これらのことを踏まえると、私立大学医学部志望の場合は普段の勉強に関しては国公立大学医学部志望の学生と同じくらいの、1日10時間程度の勉強をするといいでしょう。
医学部再受験生は年齢的に記憶力・理解力がやや現役生・浪人生と比べて劣ってしまうので、できるだけ早くから対策をしておきたいです。
夏までに基礎的な内容を終わらせ、各志望校に向けた対策を練りたいところです。
そして直前期なのですが、私立大学医学部の場合スケジュール的に密な場合が多く1日13時間近くは勉強時間を確保したいです。
1日に各大学の過去問を複数個やる必要があり、丁寧にやろうと思うとこれくらいの時間は確保しておくべきだと思います。
私立大学医学部志望の医学部再受験生も、もし学業・仕事との両立を目指しているのであれば週で50時間などとやや大きな単位での計画をたて、通勤やお昼休憩などのスキマ時間を有効に活用すべきです。
医学部再受験生の理科科目の選び方

医学部再受験生にとって理科は特に苦労する科目だということを、ここまでに説明してきましたが、では物理、化学、生物のどれを選択するのが医学部再受験生にとってやりやすいのでしょうか。
まずそれぞれの科目についてみていくと、物理は圧倒的に数学的思考が多く、数式計算も多いです。
それに対して生物は暗記要素が多く、論述問題が多いことが特徴として挙げられます。
化学は計算問題と知識問題がおおよそ半々の割合であり、計算問題も比較的パターン化されていると思います。
したがって理系的思考が必要とされるのが物理、文系的思考が必要とされるのが生物、その中間が化学といった立ち位置だと考えられます。
このことから考えると、理系出身の再受験生は物理・化学選択がやりやすく、文系出身の再受験生は化学・生物選択だと比較的負担が小さいと思われます。
特に文系出身であると数3も未履修であり、数学にも負担があるのでできるだけ理科では負担が軽い科目選択をすべきです。
独学での合格は厳しい
医学部再受験がいかに難易度が高いものなのかについて、ここまで解説してきました。
まず医学部再受験生は、医学部合格に必要な学力を身に着ける必要がありますが、前述の通り判断力や記憶力が現役生・浪人生と比べるとブランクがあるために落ちており、市販の参考書を用いて独学で合格を勝ち取るのは至難の業といえます。
独学でやれば金銭面での負担が小さく、気楽に始めやすいですが、それで合格できなければ元も子もありません。
医学部再受験で無事合格を収めている人の多くが医学部予備校に通って、医学部に特化した対策を受けています。
医学部予備校では大手予備校と比べて講師と生徒間の距離が近く、自分の苦手な分野を効率よくつぶせるのがポイントで、基礎学力の向上にはもってこいの環境であると言えます。
医学部予備校の費用は決して安くはないですが、来春の医学部合格のための先行投資だと思えば安いです。
また、医学部予備校は数多くの再受験生を合格まで導いてきた実績があるため、どの大学が再受験生に寛容なのかの情報や、合格までの最短距離を知っているので、少しでも合格可能性を上げたい再受験生にとっては良い環境であると言えます。
これから医学部再受験を考えている社会人の方は、医学部予備校で入念な対策をとってもらうとよいでしょう。
社会人の医学部再受験生で勉強時間の確保が難しい場合

医学部再受験生の中には、現在の職業を継続して勤務しながら医学部合格に挑むという人も多いです。
やはり医学部再受験での合格は至難の業であり、現在のステータスを完全に捨てるのが不安であったり、学費を払うために稼ぐ必要があるなどの理由で仕事を続けている人が多い印象です。
しかし、仕事を続けるとなると必然的に勉強時間は減ってしまいます。
仕事を続けていきたい場合は、どのようにして勉強すればいいのでしょうか?
平日はスキマ時間を有効活用する
仕事を続けるとなるとたいていの平日は勤務で忙しく、医学部予備校にも行けず、勉強に割く時間はあまりないでしょう。
しかし、ご飯を食べるタイミングや通勤時間にはわずかながらスキマ時間が生まれることがほとんど。
この時間をただスマホを眺めて終えてしまってはもったいないので、こうしたちょっとのスキマ時間を有効活用していきましょう。
とはいえ数学の問題などを解くのは厳しいので、こうしたスキマ時間では暗記系を中心にやるといいでしょう。
特に単語帳などは電車の中で、少しの時間でやるにはもってこいです。
土日・祝日は演習に費やす
土日や祝日は仕事を続ける医学部再受験生にとって時間がたっぷりあるため、ここでいかに演習を行うかが大事です。
時間があるときは数学、理科や英語の長文問題など、できる限り演習を積みましょう。
数学や理科は時間が少なく演習量がどうしても少なくなってしまいがちですが、焦らずに一回一回の演習を丁寧に行うことを心掛けましょう。
医学部再受験で一番やってはいけないのが、時間がないからといきなり難問に挑むことです。
難問はあくまで基礎の複合であるので、基礎がぐらついている状態ではとても理解できないです。
焦る気持ちはわかりますが、医学部再受験生はとにかく基礎の演習を丁寧に行いましょう。
医学部予備校に通っている場合は、ここでできる限り弱点を洗い出し、自分の苦手に特化した授業を受けるとよいでしょう。
まとめ
ただでさえ医学部受験で合格をつかみ取ることは難関であるのに、社会人経験のある医学部再受験生の場合は大学受験の勉強のブランクがあるため、さらに志望大学合格へのハードルは高くなります。
そのため合格するには合格するまでの計画をいかに綿密に立て、実践できるかが重要となってきます。
ここで述べた各科目の勉強法についてみてもらえれば分かりますが、あくまでも合格するのに重要なのはみんなが取れる問題を落とさないことです。
医学部受験では難問が確かに出ますが、結局差がつくのは基本・標準問題の出来であるため、普段の演習からその点を踏まえて学習するとよいでしょう。
そして医学部再受験生の場合、過去問からの傾向把握は必須です。
医学部再受験生はできるだけ早く合格したいので、各大学の入試傾向に合わせた対策が一番効果的なのは明らかですよね。
しかし、自分で合格までの勉強計画を練って過去問から傾向を把握するのは、はっきり言って時間の無駄です。
医学部再受験生は持ち得る時間をできるだけ勉強に使った方がいいので、やはり医学部予備校を利用することが合格への最短距離となるのは当然です。
医学部予備校では無料体験授業や無料相談も行っているため、それだけでもまずは気になった医学部予備校に連絡してみることをおすすめします。