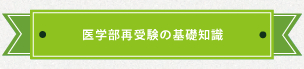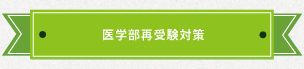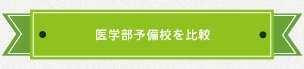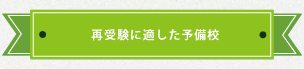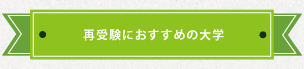医学部再受験の難易度について

医学部再受験の難易度はどれくらい高いのか。
ここでは、直近の医学部入試の傾向や偏差値ランキングから難易度を考察しています。
医学部再受験を検討している人はぜひ前もって確認し、自分も挑戦できるか判断してみましょう。
医学部の偏差値・難易度はまだまだ高い

国公立大学および私立大学の医学部医学科入試は、2022年度も前年と変わらず高い人気を誇っています。
特に新型コロナによる影響で社会情勢の先行き不透明感が増す中、安定した職業である医師を希望する受験生は一層増加している状況です。
共通テスト2年目の2022年度入試は、平均点が下がったにもかかわらず、医学部志願者は微増。
現役生や浪人生で医学部医学科を目指す受験生は強気の出願がみられるため、医学部再受験生もまずは合格に必要な学力を習得することが最優先事項となります。
特に医学部再受験生が気になる点が、後期日程の廃止および一般選抜の募集定員が減少する代わりに、総合選抜などの定員が増加していることです。
一般選抜しか出願資格がない医学部再受験生も多いので、募集定員が減少することは難易度上昇が避けられません。
医学部再受験の難易度は以前にも増して厳しいといわざるを得ないでしょう。
国公立は後期日程廃止が相次ぐ
近年の医学部受験では、後期試験の廃止が、特に国公立大学の医学部で顕著にみられます。
2020年には福島県立医科大学、広島大学、鳥取大学の医学部がそれぞれ後期試験を廃止しました。
2021年では香川大学と愛媛大学の医学部で後期試験の廃止され、前期日程や総合型選抜の定員が増加しました。
このように、医学部医学科の入試において、後期試験というのがどんどん廃止されている傾向が明確にあります。
2022年度の入試から、岐阜大学医学部も後期試験の実施を行わないことが決定し、実に国公立医学部50校のうちの17校しか後期試験を実施しないことになります。
国公立医学部の場合、一般で受験するとなると前期試験と後期試験しか選択肢がないため、ただでさえ合格難易度は高いです。
後期試験がこのまま減少していくことで、よりいっそう医学部合格へのチャンスが減っていくことにつながり、医学部再受験生は注意する必要があります。
一般の代わりに推薦の定員が増加
国公立および私立ふくめ全国の医学部全体で言えることは、一般入試の定員が減少し、その分の定員を推薦入試の定員に振り分けている大学が増加傾向でることです。
推薦入試は、専願制が基本であり、合格者=入学者となるため、大学側も学生を確保しやすいメリットがあります。
また、地方では医師不足が深刻な地域も多く、卒業後に地元に残ってもらうためにも地域枠の推薦入試枠で将来の医師を確保するという動きが広がっていること一因。
さらには、推薦入試は現役生および浪人生なら1年目までしか出願できないため、若い人材を確保したいという医学部側の意志も動いているのではないかと思われます。
一般入試の志願者が減ることは医学部再受験生にとっては不利でしかないので、今後の推移を注視する必要があります。
国公立医学部の偏差値一覧と難易度を解説

国公立大学医学部医学科の偏差値ランキング【2022年】
| 順位 | 大学名 | 大手平均 |
|---|---|---|
| 1 | 東京大学 | 75.8 |
| 2 | 京都大学 | 74 |
| 3 | 大阪大学 | 72 |
| 4 | 東京医科歯科大学 | 71 |
| 5 | 九州大学 | 68.8 |
| 6 | 千葉大学 | 68.3 |
| 6 | 名古屋大学 | 68.3 |
| 8 | 東北大学 | 67.8 |
| 8 | 神戸大学 | 67.8 |
| 10 | 北海道大学 | 67.3 |
| 10 | 横浜市立大学 | 67.3 |
| 10 | 奈良県立医科大学 | 67.3 |
| 13 | 京都府立医科大学 | 66.5 |
| 13 | 大阪市立大学 | 66.5 |
| 13 | 広島大学 | 66.5 |
| 16 | 岐阜大学 | 66.3 |
| 17 | 金沢大学 | 66 |
| 17 | 岡山大学 | 66 |
| 19 | 筑波大学 | 65.5 |
| 19 | 名古屋市立大学 | 65.5 |
| 21 | 新潟大学 | 65 |
| 21 | 和歌山県立医科大学 | 65 |
| 21 | 長崎大学 | 65 |
| 21 | 熊本大学 | 65 |
| 25 | 宮崎大学 | 64.8 |
| 26 | 群馬大学 | 64.5 |
| 26 | 信州大学 | 64.5 |
| 26 | 滋賀医科大学 | 64.5 |
| 26 | 浜松医科大学 | 64.5 |
| 26 | 山口大学 | 64.5 |
| 31 | 福井大学 | 64 |
| 31 | 大分大学 | 64 |
| 31 | 鹿児島大学 | 64 |
| 34 | 三重大学 | 63.8 |
| 35 | 愛媛大学 | 63.5 |
| 36 | 富山大学 | 63.3 |
| 37 | 旭川医科大学 | 63 |
| 37 | 弘前大学 | 63 |
| 37 | 秋田大学 | 63 |
| 37 | 島根大学 | 63 |
| 37 | 佐賀大学 | 63 |
| 37 | 琉球大学 | 63 |
| 43 | 札幌医科大学 | 62.8 |
| 43 | 香川大学 | 62.8 |
| 43 | 高知大学 | 62.8 |
| 46 | 鳥取大学 | 62.3 |
| 47 | 山形大学 | 61.8 |
| 47 | 福島県立医科大学 | 61.8 |
| 49 | 徳島大学 | 61 |
国公立大学医学部の難易度解説
国公立医学部偏差値ランキング上位には東京大学や京都大学、大阪大学といった旧帝大医学部が入っているのが分かります。
旧帝医学部は医学部受験の中でも最難関なのは有名で、その地域での学閥が強いことや研究が盛んに行われていること、またどの旧帝医学部も大都市に所在していることから人気が高くなっているようです。
ここで注目したいのが、格の高い「旧六医科大」と大都市に近い「非旧六医科大」とでは難易度がどちらが高くなるかです。
旧六医科大というのは、千葉大学、新潟大学、金沢大学、岡山大学、熊本大学、長崎大学の各医学部をまとめた総称で、歴史が古く、格が高いと言われています。
ランキングの上位を見てみると、大都市に近い東京医科歯科大学や神戸大学、横浜市立大学、大阪市立大学などの方が、千葉大学を除く旧六医科大学よりも上に来ているように見えます。
すなわち近年の医学部受験では、「大学の格」よりも「大学の立地」が重視されている傾向を読み取れます。
実際、偏差値ランキングの下位には東北地方や中国・四国地方の大学が並んでいます。
これらの大学の多くは東京や大阪、名古屋といった大都市からのアクセスが悪く、また県の中でも立地があまりよくないことが多いために敬遠されているようです。
試験・面接によるマッチング制度によって医学生自身が研修先を選ぶようになった現在では、昔ほど大学医局の力が強くなく、「大学の格」というのを重視して選ぶ学生は減ってきているように思います。
私立大学医学部医学科の偏差値ランキング

| 順位 | 大学名 | 平均 |
|---|---|---|
| 1 | 慶應義塾大学 | 73.3 |
| 2 | 東京慈恵会医科大学 | 68.5 |
| 3 | 順天堂大学 | 68 |
| 4 | 日本医科大学 | 67.5 |
| 5 | 防衛医科大学校 | 66.8 |
| 6 | 大阪医科薬科大学 | 65.8 |
| 7 | 自治医科大学 | 65.3 |
| 7 | 昭和大学 | 65.3 |
| 9 | 産業医科大学 | 65 |
| 10 | 関西医科大学 | 64.8 |
| 11 | 東邦大学 | 63.8 |
| 12 | 国際医療福祉大学 | 63.5 |
| 13 | 日本大学 | 63.3 |
| 14 | 東京医科大学 | 62.8 |
| 15 | 近畿大学 | 62.5 |
| 16 | 愛知医科大学 | 62 |
| 17 | 東北医科薬科大学 | 61.5 |
| 17 | 杏林大学 | 61.5 |
| 17 | 東京女子医科大学 | 61.5 |
| 17 | 藤田医科大学 | 61.5 |
| 17 | 久留米大学 | 61.5 |
| 22 | 北里大学 | 61 |
| 22 | 帝京大学 | 61 |
| 22 | 東海大学 | 61 |
| 22 | 聖マリアンナ医科大学 | 61 |
| 26 | 兵庫医科大学 | 60.8 |
| 27 | 福岡大学 | 60.5 |
| 28 | 岩手医科大学 | 60 |
| 28 | 金沢医科大学 | 60 |
| 30 | 獨協医科大学 | 58.8 |
| 30 | 埼玉医科大学 | 58.8 |
| 32 | 川崎医科大学 | 56 |
私立大学医学部の難易度解説
国公立の旧帝大医学部と同様に、上位には私立御三家が並んでいます。
私立御三家は、場合によって変わりますが、旧御三家が慶應義塾大学、東京慈恵会医科大学、日本医科大学のことをまとめた総称で、新御三家では慶應義塾大学、東京慈恵会医科大学、順天堂大学のことをまとめた総称です。
これら四校の中でも、慶応義塾大学はその学閥の強さやネームバリューなどから二位の東京慈恵会医科大学と大きく離してトップにいます。
また、私立医学部の偏差値ランキングは、国公立と違って立地や格だけで決まるわけではありません。
国公立は6年間の学費がほぼ全校で同じですが、私立医学部の場合は学費が偏差値を左右する重要なファクターになるように思います。
基本的には、学費が安くなればなるほど偏差値は上がると言われていて、ランキング上位にある順天堂大学や昭和大学は学費を大幅に下げたために、一気に偏差値が上がった過去があります。
また、5位の防衛医科大学校は卒業後の勤務条件を満たせば学費が無料になるため、偏差値がかなり上がっています。
これは7位の自治医科大学、9位の産業医科大学でも同じことが言えて、どちらも卒業後9年~12年程度の勤務条件を満たすのであれば、学費が無料、もしくは大幅に削減されるので、偏差値が上位に来ているように思います。
逆に言えば私立医学部の偏差値ランキングで下位に来るということは、それだけ学費が高額だと考えていいように思います。
医学部再受験生へ。2023年度入試はどうなる?

国公立の後期試験は狭き道
先ほども述べた通り、国公立大学医学部の後期試験は廃止される傾向にあります。
既に多くの国公立医学部が後期試験を廃止していて、大学の選択肢が減り、かつ国公立医学部の後期試験全体の定員が減少することで、よりいっそう国公立医学部の後期試験の難易度上昇は必至。
医学部再受験生はこの実情を踏まえたうえで、できる限り前期試験で合格できるような実力を身に着けておきたいです。
前期試験で軽々と合格できるような実力を手に入れてれば、仮に前期試験で残念だった場合でも後期試験のわずかなチャンスをものにすることができるでしょう。
また、後期試験は前期試験よりも定員が少ない分、面接試験の重要度が高まりますので、医学部再受験生は注意しておきましょう。
私立医学部も視野に入れる
国公立医学部では後期試験を廃止する流れがかなり強いですが、私立医学部では国公立医学部と比べるとやや緩やかです。
学費が高額であるという理由から私立医学部の受験を敬遠する医学部再受験生も多いですが、国公立医学部がよりいっそう狭き門である以上、少しでも医学部合格の可能性を上げておくべきです。
私立医学部の多くの大学では奨学金制度が充実しているため、学費が高額のように見えても実質負担は少ないなんてこともあるので、各私立医学部のホームページを確認してみてください。
難易度面で医学部再受験生におすすめの大学はどこ?

三重大学医学部
三重大学医学部は三重県津市江戸橋2-174に所在を置く、三重県唯一の国立大学です。
キャンパスが全学部で統一されていて、国公立医学部としては珍しく他学部と6年間同じキャンパスで過ごすことになることが特徴です。
2022年度における河合塾偏差値は65と国公立大学医学部では平均的な位置にいることが分かります。
一番の特徴としては、医学部再受験に対してかなり寛容であるということ。
毎年一定数の医学部再受験生が合格しており、面接でもまったく圧迫的な質問がないため、医学部再受験生にとって本当におすすめといえます。
また、問題の難易度も国公立医学部にしてはかなり易しめであり、高難易度の問題を解くよりも、いかに易しい問題を落とさずとるかが重要になります。
難問の対策をとる必要がなくなるので、時間のない医学部再受験生にはかなり狙いやすいと言えます。
福井大学医学部
福井大学医学部は福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3に所在を置く、福井県の総合大学です。
福井大学医学部は河合塾偏差値62.5と、国公立医学部の中ではやや合格しやすい位置にいます。
京都・大阪といった関西圏と名古屋・岐阜といった中京圏からの受験者が多く、地元の医学部に届かない層が共通テストの点数を踏まえて福井大学医学部を受験する流れが強いです。
福井大学医学部も毎年、一定数の医学部再受験者の合格があると報告されており、やや寛容であると考えられます。
福井大学医学部は英語がやや難、数学・理科がやや易から標準レベルの問題難易度です。
医学部再受験生にとって英語は得点源であることが多く、周囲に差をつけることが可能と考えられ、また理系科目は発展的な内容はほぼ出ないので対策がかなり取りやすいことが特徴。
医学部再受験生の強みを活かし、弱みを軽減できるのでかなり合格しやすいと言えます。
藤田医科大学医学部
愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98に所在を置く、単科医大の一つです。
2022年度の河合塾偏差値は65と私立医学部の中で平均的な位置にいます。
藤田医科大学医学部は医学部再受験生の受験が多く、またほとんど毎年医学部再受験での合格者も2桁人数出ていることが発表されていて、医学部再受験に対して寛容な態度であることがうかがえます。
藤田医科大学医学部の問題難易度ですが、福井大学医学部と似ていて英語がやや難で、他の理系科目が標準レベルです。
そのため英語を得点源とする医学部再受験生の場合、英語でかなり差をつけることが可能になり、合格に近づけるでしょう。
ただし、理系科目は標準的といいましたが、化学だけはやや難の問題で構成されることが多く、医学部再受験生は独自の対策をとった方がよさそうです。
化学は解答に手間がかかる問題や医学に関する問題も出されるので、過去問を通じて傾向を把握するとよいでしょう。
久留米大学医学部
久留米大学医学部は福岡県久留米市旭町67に所在を置く総合大学で、私立医学部の中では伝統のある大学として有名です。
2022年度の河合塾偏差値は65と、藤田医科大学医学部と同じくらいの平均的な合格難易度です。
久留米大学医学部は元来、医学部再受験生に対して寛容な態度をとっていると言われており、2018年の東京医大を皮切りとした不正入試についても、文部科学省の調査で問題なしと認定されていることがポイント。
久留米大学医学部の問題難易度ですが、英語は標準、理系科目はやや易と非常に医学部再受験生にとって合格しやすい設定になっています。
高得点争いになってしまうことさえ注意すれば、医学部再受験生に対する差別もないため、十分に合格できるのでおすすめです。
医学部再受験生が偏差値以外で注意したいポイント
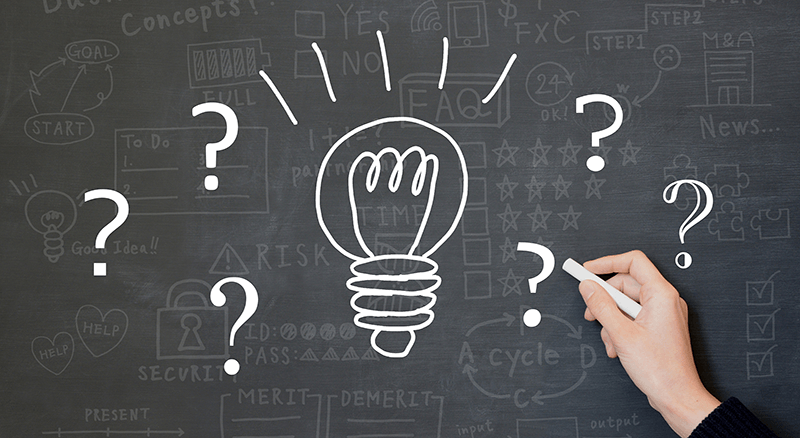
合格できる医学部を目指す
医学部によっては年齢が上がると合格者数が減少するなど、現役生や浪人生を好む大学があります。
したがって、医学部再受験生は偏差値だけでなく、年齢に関係なく合格できる大学を目指すのが最短ルートです。
地方国立大学は偏差値もそこまで高くはなく、年齢に関係なく合格者を受け入れている大学があります。
合格しないと医師へのスタートラインに立つことができないので、入りたい大学ではなく、入れる大学を目指しましょう。
入試科目と配点比率も忘れず確認
偏差値を確認することも重要ですが、医学部再受験生一人ひとり得意科目が違うように、入試制度も各大学で異なってきます。
したがって、自分の得意科目の配点比率が高く、苦手科目の配点比率が低い医学部が一番合格できるチャンスが高いと言えます。
1点でも多く点数を取ることが医学部合格では必要不可欠。
各医学部の入試科目や配点比率を確認して自分との相性を確認しましょう。
最新の合格実績を確認すること
医学部再受験生の場合、合格しやすい大学を選ぶことが重要だと紹介しましたが、参考にする情報は最新の入試結果を活用しましょう。
というのも、昔から医学部再受験生にとって寛容だった大学が、方針を変更して急に年齢に厳しくなることがあるからです。
もちろん、過去、医学部再受験に厳しい大学の22歳以上合格者が増加することもあります。
したがって、最新の偏差値情報を参考にするのと同じように、寛容度も直近の入試結果を利用して医学部再受験生の合格状況を確認するようにしましょう。
医学部予備校を活用する
ここまで記述した偏差値以外に注意したいポイントですが、確実な合格に直結するためにそれぞれを十分に行うのは独学ではかなり難しいことがあります。
例えば、再受験に寛容な大学とそうでない大学の見極め、各大学の過去問の入手と傾向の分析、模試の結果の分析と学習計画への還元、過去の倍率や問題の傾向や動向から自分に相性のいい大学選び、などが合格を大きく左右する行動になります。
これらはすべて「情報力」。実際に医学部受験を成功させた先輩が身近にいればその成功体験を伺うことができますが、それは一例に過ぎません。
これまでに多くの医学部受験生を毎年輩出し、ほぼすべての大学の過去の受験情報を抱えている医学部予備校は、その点で最強の情報力を有しているといえます。
そのため、確実に合格を決めたい医学部再受験生には医学部予備校を活用することがおすすめです。
もちろん、本科生として予備校に通うことができれば最も手厚いサポートをうけることができますが、経済的に難しい人も多いはず。
その場合は、単科受講や短期講座を受講することをおすすめします。少なくともこの期間は予備校生の一員ですので、その予備校が保有する大学情報や過去問などにアクセスすることが可能です。
分析や自分との相性を考えるのは自分自身の力になりますが、単に偏差値のみで受験校を選ぶよりも確実に合格可能性を高めることができます。
まとめ
医学部の偏差値で自分の目標とする大学をある程度絞ることは可能です。
しかし、医学部再受験という特有なバックグラウンドから年齢に寛容的な大学を選ぶことも短期合格を実現するためには重要となります。
入試不正が発覚したことにより、年齢差別もなくなったと言われていますが、22歳以上の合格者が減っている医学部があるのも事実。
やはり、年齢に寛容的で多くの医学部再受験生が合格している大学を目指すことが一番だと言えるでしょう。