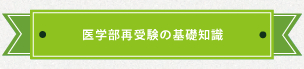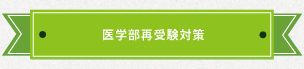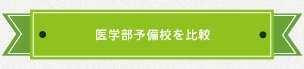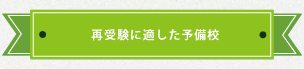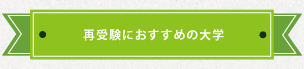医学部再受験という言葉を耳にすることが多くなってきた昨今ですが、やはり人気なのは東京大学や京都大学等の旧帝大を始めとする、国立大学医学部です。
しかし、国立大学医学部再受験を成功させることは簡単なことではありません。
本記事では、医学部再受験生が国立大学医学部を目指す理由と合格の可能性、そして選択肢となりうる私立大学医学部の医学部再受験情報について紹介していきます。
医学部再受験生が国立大学を目指す理由

医学部受験再受験生がなぜ国立大学医学部を目指すのかということについてですが、理由として以下のようなことが考えられます。
- 学費が私立大学に比して圧倒的に安い
- ステータスを求める
それぞれについて、解説していきます。
学費が私立大学に比して圧倒的に安い
この経済的問題が、医学部再受験生が国立大学を目指す圧倒的な原因であると言えるでしょう。
一般的に国立大学医学部では標準額といったものが規定されており、入学金が282,000円、授業料が1年間に535,800円ということになっています。
したがってこれらを計算すると6年間でかかる学費が約350万円と言われています。
※2020年より千葉大学医学部と東京医科歯科大学医学部では、1年間の授業料が535,800円から642,960円に変更されたためこの2校では6年間にかかる学費が約414万円となっています。注意してください。
一方で私立大学医学部にかかる学費についてですが、国立大学はほとんどすべての大学で350万円であってのに対して、私立大学で最も学費が安い国際医療福祉大学ですら6年間にかかる学費が1,850万円と、国立大学の5倍以上となっています。
私立大学で2,000万円を切っているのはこの国際医療福祉大学のみで、他の大学は2,000万円以上の学費がかかります。
いくら仕事をして自分で稼いでいるとはいえ、医師になるためにこの私立大学の高額な学費を払うことのできる経済的余裕のある再受験生はこの時代に少ないため、皆学費の安い国立大学を目指すことになるのです。
ステータスを求める場合
次に考えられる理由としては、ステータスを求める受験生が国立大学を目指すということが挙げられます。
学歴至上主義の日本では、近年学歴で個人の能力を判断するということから脱却する動きがあります。
しかしながら、頭脳が物を言う医師の世界ではまだまだ学歴至上主義が残り続けるでしょう。
そしてこの観点で考えると、国立大学に入学することは私立大学に入学することよりも圧倒的に大きなメリットとなります。
もちろん、私立大学医学部でも慶應義塾大学医学部や順天堂大学医学部を始めとする名門大学も多く存在しますが、国立大学に入ることができれば一定以上のステータスが保証されます。
こういった医師の世界独特の理由が医学部再受験生が国立大学を目指す理由としてあります。
医学部再受験生の国立大学合格は厳しいのか?
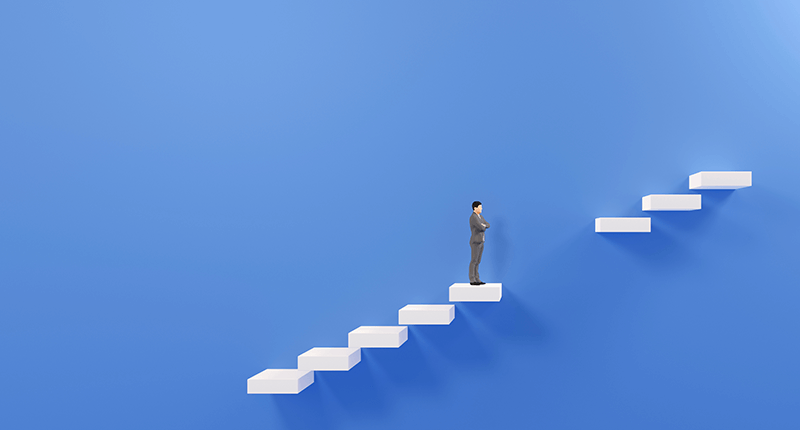
そんな医学部再受験生にとっての国立大学ですが、実際に合格することは可能なのかどうかという点についてお話していきます。
国立大学医学部の受験が一般に難しいと言われている理由としては、私立大学医学部に比べて対策するべき科目数が多いということ、二次試験だけではなく共通テスト対策をする必要があるということなどがあります。
現役の受験生ですら国立大学医学部に合格するのが難しいと言われているので、医学部再受験生にとってはなおさら難しいと言わざるを得ません。
しかし、実際に国立の医学部再受験を成功させて医師になっている再受験生もいますから、かなり難しいですが不可能というわけではありません。
年齢によるハンディキャップを乗り越える必要
医学部再受験生が最も苦労するのは、受験勉強から長期間離れていたことによって勉強の勘が鈍っているということ・加齢によって脳の能力が落ちていることだと言われています。
「昔は簡単に覚えられていたものが全然覚えられない」「こんなはずではなかった」と医学部再受験を諦めてしまう人も少なくありません。ましてや、国立大学では先程述べたように私立大学医学部受験に比べて圧倒的な勉強量を要します。
受験の世界は残酷で、どんなに努力をしたとしても国立大学医学部に合格するには、共通テストで9割、2次試験では大学によって異なってきますが、かなりの点数を確保することができなければ不合格になってしまいます。
人間の脳の能力が加齢によって落ちてしまうのは抗うことのできないものです。
国立医学部合格が可能な水準の偏差値まで持っていくことは非常に難しいです。しかし、若い頃と同じようには行かないことをしっかりと認識した上で腐らない精神を持ってして挑めば、必ず光が見えてくるはずですから、このことを頭に置いておいてください。
また医学部再受験に挑戦するにあたって、何が何でも一年で成功させてやるという気持ちではなく、2-3年くらいかけて自分のペースでやっていこうという具合に余裕を持って勉強を勧めていくことも重要です。
以上のようなことを意識できれば、医学部再受験で国公立大学に合格することも夢ではないでしょう。
再受験生に寛容な大学を選べば可能
一概に国立大学医学部と言っても、大学によって年齢に寛容かどうか、医学部再受験生に寛容かどうかということは大きく異なってきます。
毎年のように医学部再受験生が合格しているような国立大学医学部もあれば、ほとんど医学部再受験生が合格できていないと言った国立大学医学部もあります。
いくらその大学に合格できるレベルの学力が伴っているとしても、医学部再受験生に寛容でない大学では入試で現役生に勝つことは難しいでしょう。
したがって、志望大学を決定する際には偏差値と同じくらい医学部再受験生に対する寛容度を重視しておくことが重要です。
医学部再受験生に寛容である国立医学部を例としてあげておきます。
- 滋賀医科大学
- 香川大学
- 山梨大学
- 新潟大学
- 信州大学
- 岐阜大学
- 名古屋市立大学
- 三重大学
- 奈良大学
- 東京大学
- 滋賀大学
- 大阪公立大学
- 岡山大学
- 島根大学
- 香川大学
- 熊本大学
- 琉球大学
これらの大学の、過去の合格者の年齢別分布割合を見てみると、いかに医学部再受験生に寛容であるかが見て取れるかと思います。
以上をまとめると、医学部再受験生が国立大学に合格できる可能性は、年齢によるハンディキャップを乗り越える精神力を持ち、かつ医学部再受験生に寛容な大学を選ぶことができれば、かなり難しいですが不可能というわけではないことになります。
私立大学医学部の再受験情報
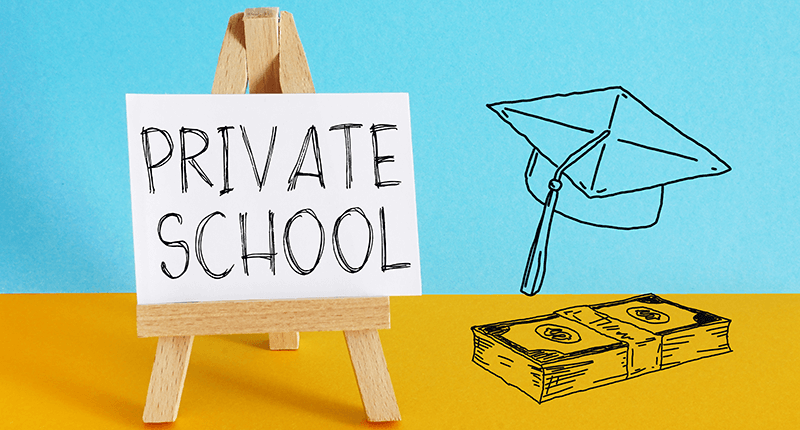
これまでは、医学部再受験生が国立大学医学部を目指す理由や国立大学医学部の合格の可能性ということについて説明してきましたが、医学部再受験生には私立大学医学部という選択肢もあります。
私立大学入試制度
私立大学の入試制度の、国立大学の入試制度との大きな違いは、やはり共通テストを受ける必要がないという点です。
共通テストでは、二次試験でほとんど必要な数学・理科・英語に加えて文系科目である国語や社会の対策をする必要があります。
したがって、私立大学医学部を目指す場合は理系科目に割くことのできる時間が増えるというメリットがあります。
また、国立大学の入試制度との違いとして国立大学は日程の関係上基本的に1校しか受験することができないのに対して、私立大学では日程さえかぶらなければ、複数の大学を受験することができます。
したがって、落ちたら終わりの国立大学と違って、複数受験可能な私立大学を志望することはリスク管理の観点からすると非常に魅力的です。
合格状況
私立大学の医学部再受験生の合格状況については、年齢別の合格者数を公表していないもあり、明らかになっているとは言い難いです。
また、近年複数の私立大学医学部で年齢差別をしていることが明らかになったということもあり、医学部再受験生としてはあまり良いイメージを持っていないというのが実情でしょう。
しかし、実際に医学部再受験生に寛容であると言われている私立大学医学部も存在します。
例としてあげると、東京都に位置する日本医科大学がその一例です。
日本医科大学のホームページに有る合格体験記を見てみると、驚くべきことに再受験生として日本医科大学に合格した方のインタビューが掲載されています。
自大学のホームページに再受験生の合格体験記を掲載するということは、自大学が年齢及び医学部再受験生に寛容であることをアピールしたいと受け取ることができますから、日本医科大学は医学部再受験生に非常に寛容であると言えるのではないでしょうか。
また、その他の医学部再受験生に寛容であると言われている私立大学医学部は以下のようになっています。
- 東北医科薬科大学
- 聖マリアンナ医科大学
- 国際医療福祉大学
- 帝京大学
- 近畿大学
- 関西医科大学
- 岩手医科大学
- 久留米大学
- 東海大学
- 愛知医科大学
- 東京女子医科大学
- 藤田医科大学
- 杏林大学
私立大学医学部の経済問題を解決する方法

この記事を最初から読んでくださっている方は、「いくら私立大学に進学したくても、学費を払うことができなければどうしようもないじゃないか」とお思いのことでしょう。
しかし、実は特定の制度を利用すれば私立大学の学費を抑えて進学することができるのです。
そんな制度について、紹介していきます。
地域枠制度を利用
医学部入試には、地域枠制度というものがあります。
デジタル大辞泉(小学館)によると、医学部地域枠とは以下のような紹介がされています。
「地域医療の担い手を確保するために、大学医学部が設ける入学者選抜枠。将来、その地域で一定期間、医療に従事することを条件に、返済不要の奨学金を支給したり、入学しやすくしたりする。」
この、返済不要の奨学金という点が肝になってきます。
地域枠は医師の偏在を解消するために、医師として一定の期間その地域で特定の診療科で医療に従事することを目的として作られた制度で、その見返りとして学費を援助してくれるといったものになります。
もちろん、医学部地域枠として入学後に他の地域で働きたくなっても、卒後数年間は実現が難しいであったり、将来の診療科が絞られてしまったりというデメリットが有ることは事実ですが、私立医学部で学ぶために必要な莫大な学費が援助されるという点は非常に魅力的でしょう。
ただし、地域枠は大学ごとに応募要件が異なっているため年齢等が制限されていることもありますから、しっかりとその大学の応募要項を熟読しておきましょう。
特待生・奨学生といった制度を利用
大学によっては、医学部入試の際の成績によって特待生・奨学生といって学費を減免したり、貸与しているところがあります。
例えば、国際医療福祉大学では医学部特待奨学生制度を用いると、1年次に250万円が給付・入学金150万円を免除、2~6年次には230万円を毎年次給付されることになります。
もちろん、特に成績が優秀な合格者(一般選抜45名、共通テスト利用選抜5名)といった条件がありますが、こういった成績を目指すことのできる医学部再受験生であれば利用しない手はありません。
以上のように、莫大な学費を必要とする私立大学医学部でも、特定の制度を利用して経済的問題を解決することができる可能性がありますから、ぜひ調べてみることをおすすめします。
まとめ
いかがだったでしょうか。
医学部再受験生が国立大学医学部を目指す理由や国立大学医学部の合格の可能性、そして医学部再受験生の国立大学以外の選択肢として考えておくべきな私立大学医学部の再受験情報についてまとめてきました。
今回の記事では紹介することができませんでしたが、医学部再受験生には編入試験という選択肢もあります。
編入試験は、2年次や3年次から医学部に入学できるため、大学在学期間が短いというメリットが有る一方で、挑戦者が少なく難易度も高いというデメリットもあります。一考の価値がありますから、ぜひ視野に入れてみてください。
医学部再受験を成功させることは並大抵のことではありませんが、せっかく挑戦してみようという気持ちになったのであれば、事前のリサーチを十分に行った上で、少しでも年齢によるハンディキャップを埋めることのできるような対策をしてください。
皆さんの医学部再受験生活がうまくいくことを心より祈っております。