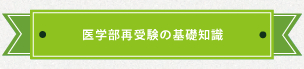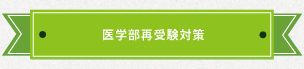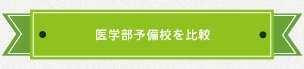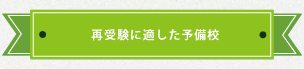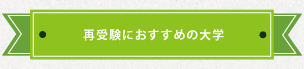医学部受験には学士編入試験というの入試制度があります。
一般入試に比べて受験科目が少なく、医学部在籍期間を短くすることができる学士編入。受験生がその社会人経験を多いにアピールすることができる場でもあります。
しかしながら、その歴史はまだまだ浅く、定員総数を少ないことからなかなか情報が出回っていないのも現状です。
今回は、医学部の学士編入試験について、その仕組みや対策方法などを、基本から裏話まで、徹底解説していきます。
学士編入試験制度とは
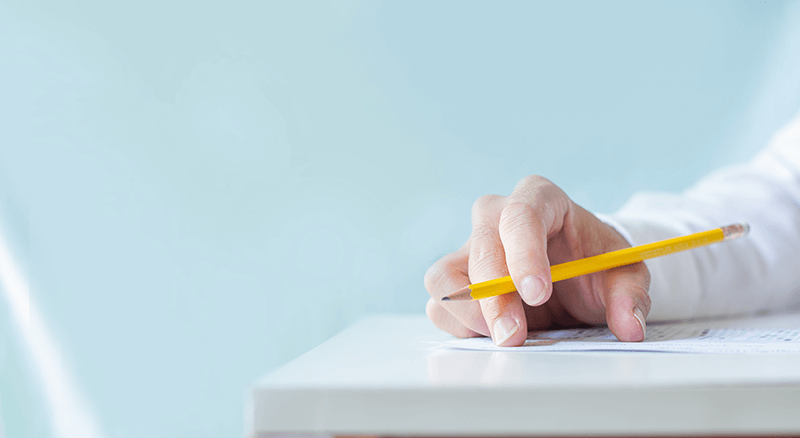
一般に、「編入」は4年生大学に途中の学年から入ることを指します。
その中でも「学士編入」とは、4年生大学の卒業者つまり学士の学位を持った者(見込み含む)を対象に行われる試験です。
したがって、3年生以下の現役大学生や大学を中退した人は受験資格がない場合がほとんどです。
その中でも、医学部の学士編入は他学部とは異なる点が多数あります。
2022年度の医学部の編入試験は、国公立大学で28校、私立大学3校で実施されます。
出願期間・試験日は大学ごと
医学部の編入試験は、一般の医学部入試のように2月に試験が行われる大学はほとんどありません。
早いところでは4月上旬に、その年度の編入試験の出願が締め切られます。
その結果、7月には合格発表があり受験終了というケースもあるほど。
一般の大学受験とは時期が大きく異なることに注意が必要です。
また、大学によって出願時期・試験日が異なるので、必ず募集要項を確認しましょう。
なお、合格後は2年次前期、3年次前期からの編入となる大学がほとんどです。
受験科目
医学部の編入試験で課される試験科目は、大学によってさまざまです。その中でも、試験科目は大きく以下の3つのパターンに分類できることがほとんどです。
- 英語+生命科学(自然科学)
- 英語+生命科学(自然科学)+物理化学
- 英語+生命科学(自然科学)+物理化学+数学
このように、英語が必須となっている大学がほとんどで、出願要件の中にTOEICやTOEFLスコアの規定があるほど、医学部の学士編入の英語は一般の医学部入試より高難易度となります。
また、生命科学や自然科学と称される科目が課されることがほとんど。
実際には各大学の募集要項の中で、具体的にどのような内容を出題するかが示されているのが多いため確認するべきですが、ざっくり「高校生物ベースの人体関連の問題」が出題されます。
その他、物理化学、数学については高校卒業レベルの内容が問われることがほとんど。中には大学教養レベルの問題が課される大学もあるため、出題科目は募集要項を確認しましょう。
なお、面接は必ず行われ、小論文が課される大学もあります。
また、大学によっては出願時点で書類選考にかけることもあるため、候補大学の募集要項は必ず確認が必要です。
推薦書
学士編入試験の出願書類の中に「推薦書」が求められる場合があります。
一般には出身大学または大学院の指導教員が対象となりますが、大学によっては配偶者や三親等以内の近親者でも可能としているところも。
また、実際には教員自ら文章を作成することはそれほど多くなく、編入受験生が自分で推薦書を書いてそこに印をいただく、というパターンがほとんど。
結局のところ、形式が整ってさえあれば内容や執筆者についてはあまり突っ込まれない印象があるため、編入出願を決意したらなるべく早くから推薦書の準備にとりかかりましょう。
どんな人が受けている?
医学部の編入は、正直かなりハイレベルな戦いとなります。
もちろん、歯学部出身者、薬学部出身者や元薬剤師、元看護師といった医療従事者が受験することも珍しくありません。
また、大学院で研究をしていた人、企業で実績をあげた人も受験します。
医学部の学士編入受験生の中には、このようなライバルのステータスを気にしてしまい自信を持てずにいる人がいます。
確かに学士編入を実施している医学部によっては、卒業学部や年齢に制限を設けている大学もわずかにありますが、合格に際して重要になるのは筆記・面接で高得点を取ることに他なりません。
ぜひ、自身の社会人経験だけでなく、医師を志したその強い意志を自信にしてください。
意外とかかる「費用」
医学部の学士編入試験、実際の受験生のほとんどが感じるのが「お金がかかる」ということ。
これは複数校の受験が可能でありながら、試験会場は当該大学のキャンパスという一般の医学部入試とは大きく異なる受験方法が原因です。
簡単に、実際の医学部学士編入試験にかかる費用を見ていきましょう。
まずは出願時にかかる費用。
入学検定料として国公立では30,000円、私立では60,000円が必要です。さらに、これらの振り込み手数料や出願書類の郵送などに¥2,000~3,000かかります。
次に、いざ受験する時にかかる費用。
受験生の自宅と受験校の位置関係にもよりますが、新幹線や飛行機を利用するとなると往復で¥20,000〜¥30,000はかかってしまいます。これに加えてバスやタクシーの交通費、さらには現地での宿泊費として5,000〜8,000円/泊。
試験当日は集合時間が早朝なので前日に現地入りすることが基本。また、地方医学部のほとんどは市街地から離れた場所にありがちなので、主要駅や空港からの移動には都合よくバスがあれば好都合ですが、タクシーを使わざるを得ないことも多いとか。
重要なことがもう一つ。それは医学部の学士編入試験のほとんどが「1次試験と2試験が別日程」ということ。
つまり、晴れ1次試験に合格した場合には、2次試験を受験するためにまたもう一度大学に向かうのです。ここにまた往復の交通費や宿泊費が。
結果、受験にはどれほどの金額がかかるのか。
医学部の学士編入試験受験生は平均5校ほど受験します。全て国公立で、そのうち3校が面接試験まで進めたと仮定すると、ざっと約500,000円ほどの総額に。
また、受験校の組み合わせによっては、合格をもらった大学を”キープ”するために入学金282,000円を払うことも。
医学部の編入試験では、受験校を戦略的に選択することがいかに大切か、このことからも分かりますね。
医学部の学士受験対策
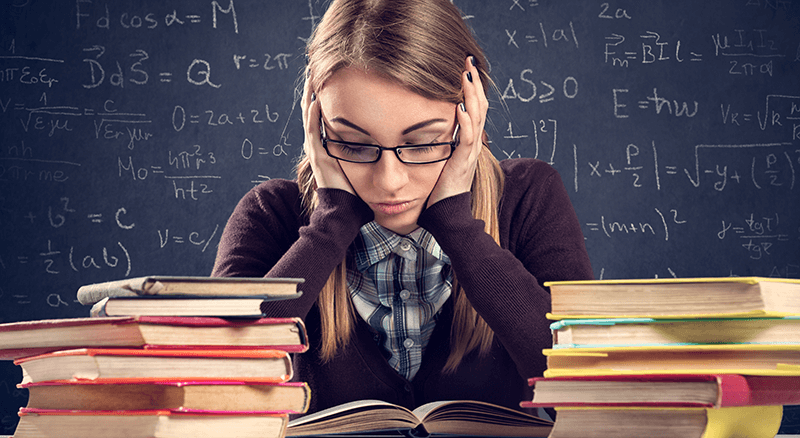
基本的な勉強方法
一般の医学部受験では、どの試験科目でも「基礎知識のinput→演習問題→過去問で傾向と対策」という流れが基本となります。
医学部の学士編入試験でもこの流れは変わりませんが、過去問について難が。
大学によっては過去問をホームページなどで公表しているところもありますが、試験問題の持ち帰りが禁止されている大学もあるため、公式には出回ってない大学も。
GHS会という学士編入を支援するサイトなども活用してみましょう。
また、河合塾の学士編入専門コースKALSでは短期講座など受講するだけで、ほぼ全大学の過去問を閲覧できるようになります。
直近1〜3年分はどうにか確保して演習することが目標です。
実際、市販の参考書では医学部学士編入試験に特化したものはほとんどありません。
そんな数少ない医学部編入試験のための参考書の中でもおすすめのものがこちら。
- 『医学部編入への生命科学演習』(KS生命科学専門書)
これに合わせて、以下の参考書を購入する医学部編入試験受験生が多いです。
- 『医学部編入への英語演習』(KS生命科学専門書)
- 『Essential細胞生物学』(南江堂)
なお、2021年6月に発売されたこの本も好評です。
- 『医学部学士編入試験の教科書 合格者10名による完全解説』(エール出版社)
英語
医学部の学士編入試験では、その特性上、英語が課される大学では相当レベルの難易度であることが多いです。
中には、出願要件としてTOEFLやTOEICで一定以上のスコアを有していることが挙げられている医学部も。目安として、TOEICでは850点以上なければ厳しいでしょう。
受験校の候補も広がるので、医学部学士編入試験を検討している人はまずはTOEICやTOEFLでの高得点獲得を目標にするといいでしょう。
また、科学雑誌の論文を試験に引用している医学部も珍しくないため、受験校によっては生物系・医療系の英語論文には慣れる必要があります。
したがって、①受験英単語に合わせて簡単な科学系英単語の暗記、出題頻度の高い②下線部和訳の訓練、医療科学系の論文をスムーズに読めるために③背景知識の学習を行いましょう。
生命科学・自然科学
実際には、高校生物の内容に加えて、分子生物学・生化学・免疫学・遺伝学といった科目に加え、物理や化学の知識が問われる試験科目。
各大学の出題傾向を確認して、高校生物の参考書をやってみたり、統計学の入門書をやってみたりと自分に合った参考書を選びながら学習を進めましょう。
なお、上で紹介した参考書の中に『Esssential細胞生物学』がありますが、これはあくまで資料集のような存在。読破しようとするのではなく、別の参考書や過去問をやっているときの一助として使用します。
逆に言えば、この本に記載されている内容の大まかを理解できれば医学部の学士編入試験は難がないとも言えます。
面接・小論文
面接や小論文では、当然、志望動機が聞かれます。
医学部の学士編入試験では、志望動機で何を言ってもほぼ必ず突っ込まれます。
どの大学も、「本当に医師になりたいのか」「なぜ、医師を選ぶのか」といった部分を、一般の医学部入試とは比にならないほど突っ込んで聞いてきます。
自身のこれまでの経歴や経験などに繋げる形で医師という職業への「動機付け」をできなければ、面接点で高得点はまず無理。
おすすめは、これまでの自分を整理し(過去)、長所短所など自分を冷静に分析し(現在)、医学部進学後や医師としての将来のプランを具体的に考える(未来)ことです。
将来については、どういう診療科に進みたいか、どこで働きたいかなど、とにかく具体的に検討することが大事。
面接で突っ込まれた時に、いかに上手に返事できるかどうかは、「どれだけ準備したか」ではなく、「どれだけ考えてきたか」なのです。
ある編入試験受験生は、「動機が弱いですね…。この辺にしましょうか。」と言われて面接が終了したという話まであるほどです。徹底的に対策しておいてください。
文系出身者はココに注意!
医学部の学士編入試験には文系受験生も珍しくありません。
英語が得意な場合は、TOEICなどの点数を英語の点数として採用する大学を受験校として、英語対策に時間を割かれないようにするのも手のひとつ。
大きなネックとなるのは生命科学です。
まずは大学受験レベルの生物、高校生物の参考書から学習を開始しましょう。
その際に重要なのは特に動物・人体に関する点に集中することです。
高校生物の中には、植物の生態系や生殖なども取り上げられます。これらが全く試験で問われないわけではありませんが非常に珍しいケース。
多くは動物・人体への関連知識が問われるので、特に基礎となる細胞・分子生物学などは重点的に基礎を徹底しましょう。
受験校は自ずと、英語+自然科学の二科目となる大学を選択することになります。
その中でも記述試験となる大学にすると、部分点などがもらえる店で有利に働くかも知れません。
まずは高校生物の基礎知識の獲得を重要視することに気をつけましょう。
医学部予備校という選択も
学士編入試験に限らず、医学部受験は情報戦です。その中でも、学士編入試験は定員数・受験者ともに一般の医学部入試に比べて少ないため、情報自体なかなか得られません。
ツイッターやブログなどネットの情報には限界があり、最新情報がなかなか手に入らないもの。
そこでぜひ検討するべきなのが、予備校という選択肢。
河合塾では医学部学士編入試験に特化したコースが設けられているなど、大手予備校での対策も可能です。
また、「医学部専門予備校」という選択肢もあります。費用は大きく異なりますが、専門ということもあり情報や試験勉強のノウハウなどはかなり特化したものがあります。
いずれにしても、医学部の学士編入試験は試験日が大学によって異なっており、過去問が出回っていないなど、独学での受験には困難が多くあります。
実際に予備校に通わずして編入合格している受験生も少なくはありませんが、チャンスを棒に振らないためにも、ぜひ一度検討してみましょう。
学士編入試験を実施している大学一覧【2022年度入試】

2022年度の医学部編入試験を実施している大学は、国公立大学28校、私立大学3校です。
なお、2021年9月時点ですでに出願期間が終了している大学がほとんどです。
国公立
- 北海道大学
- 旭川医科大学
- 弘前大学
- 秋田大学
- 群馬大学
- 筑波大学
- 東京医科歯科大学
- 新潟大学
- 金沢大学
- 富山大学
- 福井大学
- 浜松医科大学
- 名古屋大学
- 滋賀医科大学
- 大阪大学
- 神戸大学
- 岡山大学
- 鳥取大学
- 島根大学
- 岡山大学
- 山口大学
- 香川大学
- 愛媛大学
- 高知大学
- 長崎大学
- 大分大学
- 鹿児島大学
- 琉球大学
私立
- 岩手医科大学
- 東海大学
- 北里大学
【医学部学士受験】おすすめの大学

惜しみなく地方医学部を選ぶべし
医学部の編入試験では倍率が20倍を超えることも珍しくありません。
したがって、関東や関西など都市の大学は人気となりかなりの難易度となります。
そこでおすすめなのが地方大学。
都市のブランド大学を卒業した方が医師としても羽振りがいいのでは…と思われがちですか、現在では出身大学はほとんどキャリアに影響しません。(※大きなポストを狙う場合は例外)
医学部教育に力を入れている大学はむしろ地方大学の方が多いこともおすすめの理由。
以下に、例年の医学部編入試験の倍率が比較的低いおすすめの大学を紹介します。
| 大学名 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 弘前大学 | 5.25 | 7.3 | 8.0 |
| 東京医科歯科大学 | 7.8 | 11.8 | 7.2 |
| 岡山大学 | 11.4 | 8.0 | 8.0 |
| 鳥取大学 | 30.4 | 3.8 | 7.8 |
| 島根大学 | 16.0 | 12.2 | 4.2 |
| 愛媛大学 | 18.8 | 15.2 | 11.6 |
これは各年度の倍率の表です。
20倍前後となる医学部編入試験の世界でこの数字はかなり珍しいです。
中には、そもそもの受験資格が狭いという場合もありまずが、一様に地方大学であることが分かります。
最短で確実に合格を勝ち取りたい編入試験受験生は、ぜひこの中から検討してみてください。
編入試験受験生の中には、各大学の進級・卒業率すなわち単位の取りやすさを検討する人もいます。実際のところ、大学によっては進級がかなり厳しいところやほぼ9割がストレート卒業できるところと様々です。医師となるまでの期間を最短にするためにも気にかけてみても良いかもしれません。
準備は早めに!そして戦略的に!
医学部の学士編入試験では、早い大学では年度末から次期年度の入学選抜の出願が始まります。
いざ編入試験に挑戦しようと思うと、情報の収集や各試験科目の対策勉強に加えて、推薦書の準備やTOEIC/TOEFLの受験などタスクは山積みとなります。
合格可能性を高めるためにも、決断は早く、準備期間を十分に設けましょう。