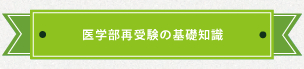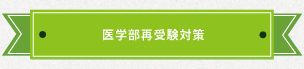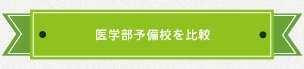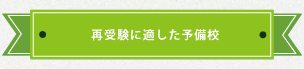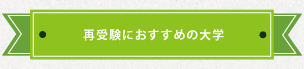日本の最高学府である東京大学。
その東大の中でも最難関とされるのが東京大学理科三類です。
大学受験の最難関と言われる医学部受験の中でも、さらにその最難関である東大理三。
医学部再受験生が検討する大学として真っ先に名前の挙がる大学ではありませんが、実は受験生の年齢や経歴については全く偏見を持たない大学の一つ。
すなわち、医学部再受験生にとって「かなり寛容」な大学の一つです。
この記事では、そんな東京大学理科三類について、概要から勉強法、過去の入試結果まで、医学部再受験で必要な情報をお届けいたします。
東京大学理科三類(医学部)の概要

日本の最高学府
東京大学理科三類は言わずと知れた、国公立・私立全医学部の中でも最高峰の学力を誇る大学です。
東大、京大、医科歯科、阪大、慶應。この5大学は長年医学部受験最難関ですが、東京大学はその中でも群を抜いてトップレベル。
最新の2021年度入試では共通テストのボーダー得点率は92%、二次偏差値は72.5と圧倒的な難易度です。この年、共通テスト初年度だったことも踏まえると、ボーダー得点率92パーが驚異的な数字であることがお分かりいただけると思います。
日本最古の学府ということもあり、東京都内でのキャンパスの立地やアクセスも十分なもので、医学部再受験生にとって学生生活を送る面での不満はほとんど生じない大学でもあります。
特徴的な入試制度・カリキュラム「進振り」
東京大学の入試では、文科一類・二類・三類、理科一類・二類・三類の6類で募集が行われます。
医学部を志望する学生のほとんどは理科三類を選択し受験します。
入学後は前期課程として2年間、教養学部に所属し始めの1年半は理科二類と合同のクラスとなり、一般教養を学びます。
現在、多くの医学部医学科ではこの教養課程が平均1年間、短い医大では半年となっているため、この点でも東京大学は特徴的なカリキュラムと言えます。
2年次に行われる「進学選択」において、全東京大学生は進学する学部の希望を提出し、最大3段階の経過を経て進学内定を獲得し、前期課程の残り半年間をその学部の専門基礎科目を学びます。
東京大学医学部=東京大学理科三類
このように、東京大学の入試制度では入学時点でどの学部に進学できるかは確定しておらず、教養課程での成績と希望調査とで進学する学部が決定します。
ただし、医学部は特殊で、理三で合格した人がほぼそのまま医学部生となるのが現状。
医学部再受験生の中には、「理科二類で合格したあとに教養課程で好成績を残し、医学部に進学する」という計画を立てる人がたまにいますが、これはかなりのレアケース。
東京大学医学部に行きたいのであれば、理三を選択するのがベターです。
なお、理科二類からは10人、理一・文科からは合計3名が医学部に進学可能となっています。
逆に、制度上は理三で合格しても成績不良者は医学部に進学できないケースもあり得ますが、東京大学ではこれまでのところそのような事例はないようです。
臨床・研究・海外、さまざまな進路
東京大学医学部では、卒業後進路の選択肢が豊富にあります。
もちろん東京大学附属病院での研修も可能で、この東大病院は大学病院としては珍しく人気な病院。症例数も指導医の教育力も十分で非常に評判です。
また、当然ながら大学に残って日本最高峰の研究に携わることも可能。
さらには、日本の名前を背負ったグローバルな大学なだけに、卒業後すぐに海外で活躍する選択肢もあります。
医学部再受験生の多くは医学部受験の段階で強い思いや野心を抱えていることも多く、東京大学はその点で医学部再受験にとって最高の環境を提供してくれる大学です。
東京大学医学部のデータ
| キャンパス | ■駒場地区キャンパス(1,2年次)■本郷地区キャンパス(3,6年次) |
|---|---|
| 住所 | 〒113-0033 東京都文京区本郷7丁目3番1号 |
| 医学科公式HP | http://www.m.u-tokyo.ac.jp/ |
東大合格を目指す医学部再受験生の入試対策
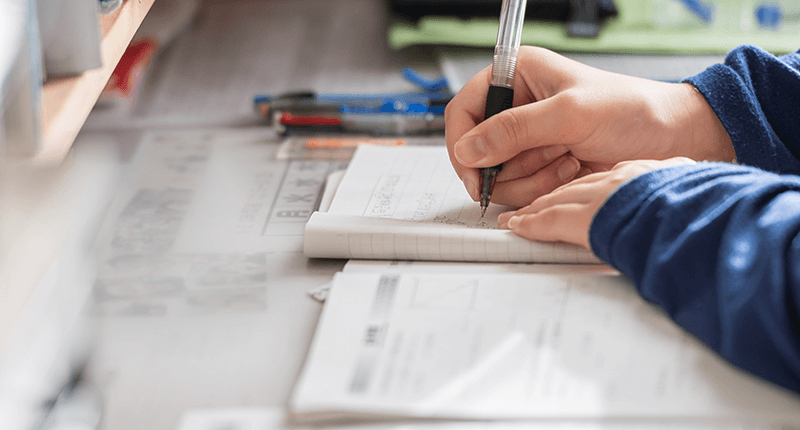
医学部再受験への寛容度
医学部再受験においては、そもそもその大学が医学部再受験に寛容かどうかが重要です。
東京大学の場合、ズバリ医学部再受験には「かなり寛容」な大学と評価されています。
つまり、医学部再受験生の年齢に関しては、東大受験ではほぼ全く逆風がありません。
ただし、東京大学は「医学部再受験に寛容である=入りやすい」が通用しない大学でもあります。
まずは毎年の東京大学の理科一類〜三類全体の年齢別合格者の内訳をご覧ください。
| 年度 | 性別 | 18歳 | 19歳 | 20〜22歳 | 23〜29歳 | 30〜39歳 | 40歳以上 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 男 | 1012 | 464 | 67 | 8 | 3 | 0 | 1554 |
| 女 | 198 | 68 | 10 | 0 | 0 | 0 | 276 | |
| 2020 | 男 | 973 | 511 | 77 | 10 | 3 | 1 | 1575 |
| 女 | 161 | 79 | 7 | 2 | 0 | 0 | 249 | |
| 2019 | 男 | 963 | 534 | 80 | 10 | 4 | 0 | 1591 |
| 女 | 151 | 86 | 10 | 0 | 0 | 0 | 247 | |
| 2018 | 男 | 933 | 537 | 94 | 3 | 2 | 2 | 1571 |
| 女 | 184 | 74 | 7 | 1 | 0 | 0 | 266 | |
| 2017 | 男 | 951 | 540 | 87 | 6 | 2 | 1 | 1587 |
| 女 | 156 | 72 | 11 | 0 | 0 | 0 | 239 |
医学部再受験生といえば25〜30歳が平均的な年齢ですが、このように、理科類全体をみても、医学部再受験生の層である20代後半や30代の合格者は決して多くありません。
また、女子に至っては23歳以上では過去5年間でもたったの3人というデータ。女子の医学部再受験生にとっては、現実としてかなり合格可能性は低いと言わざるを得ません。
東大が医学部再受験生にとって入りやすい大学ではないという、極め付けのデータがこちら。
東京大学理科三類の、志願者・合格者における現役生の占有率です。
| 年度 | 志願者数 | 合格者数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 現役 | 占有率 | 全体 | 現役 | 占有率 | |
| 2021 | 385 | 169 | 43.9% | 98 | 82 | 83.7% |
| 2020 | 413 | 164 | 39.7% | 97 | 67 | 69.1% |
| 2019 | 405 | 180 | 44.4% | 97 | 75 | 77.3% |
| 2018 | 450 | 187 | 41.6% | 98 | 73 | 74.5% |
| 2017 | 527 | 186 | 35.3% | 98 | 76 | 77.6% |
このように、東大理三では、医学部再受験生も含めて受験生の半分以上が1浪以上であるにもかかわらず、実際の合格者の約8割が現役生という現実が。
これは、東大合格という難関は、中学高校からの長期的な準備に賜物であると言われる所以でもあります。
「無理ではない」と思える人だけが受験しよう
上述のデータが示すとおり、東大理三の合格は「1浪以上」という枠の時点で狭き門であり、医学部再受験においても同様に厳しいものと言えます。
ただし、もしも学力さえ合格基準に達していれば、他大学で見られるような医学部再受験の年齢差別などはほとんどない大学であるため、「純粋に学力さえ満たせば入れる大学」と言えます。
しかし、東京大学理科三類は日本最難関。
正直なところ、医学部再受験生の東大理三受験はかなりおすすめできないのが筆者の本音です。
ましてや文系出身の医学部再受験や自身の大学受験から5年以上ブランクのある医学部再受験生については、東大受験は再検討することを強くすすめます。
その上で、「東京大学理科三類なら目指せそうだ」ともしも医学部再受験のあなたが今この段階で思えているのであれば。そう思えていることこそが、東大合格可能性を秘めている証とも言えるのかもしれません。
まとめると、東京大学理科三類は医学部再受験生には「かなり寛容」ですが、当然のことながら、合格のためには日本最高峰レベルの学力が要求されます。
【医学部再受験】東京大学のおすすめの勉強法

ここでは、東京大学理科三類を目指す医学部再受験生に向けて、おすすめの勉強法を簡単に解説していきます。
国語
東京大学の入試国語は、点数の差がつきにくい科目です。
よく言えば「それほど時間をかけなくても致命的にならない」、悪く言えば「時間をかけて努力しても他の受験生との差をつけるのが難しい」。
なかなか珍しい科目ではないでしょうか。
従って、東京大学の国語対策として意識すべきなのは「効率よく、かつみんなができるところを絶対に落とさないように王道の勉強をしていく」ということになります。
みんなができるところとはなんぞやと思うかもしれませんが、具体的には例えば、現代文なら漢字の問題、古文漢文なら単語の意味や文法事項といった基礎的な知識でしょうか。
基礎を固め終えたら、もうするべきことは過去問演習しかありません。
「東大の現代文27ヶ年」や「東大の古典27ヶ年」等を用いて"慣れ"ていきましょう。
また、題材となる話のレベルが似ている共通テストや過去のセンター試験の過去問を解くことも東大国語の点数を安定させるには効果的です。
共通テストの対策をすることがそのまま東大二次試験の国語の対策をすることにも繋がりますから、共通テスト対策をする際は、ぜひその点を頭の片隅に置きながら行ってみてください。
国語には時間を割き過ぎず、80点中40点を狙うくらいの心づもりで挑むと良いでしょう。
英語
東京大学の英語では、リーディング・ライティング・リスニングのすべての能力がハイレベルにかつまんべんなく要求されます。
そのため、基礎をしっかりと固めた上で応用問題に取り組んでいくことが重要となります。
基礎となる単語・熟語についてですが、単語帳・熟語帳は「これ」というものを一冊決めてとにかく漏れのないように徹底的に暗記しましょう。
他の受験生がやっている他の単語帳などを見ると不安になってくるかもしれませんが、一冊やり込んでおけば単語力や熟語力に大きな差がつくことはありません。
東京大学の英語はどの問題も非常に特徴的であるので、市販の演習書をやりこんでもなかなか点数が伸び悩むかと思います。
そこで、勉強を始める前に東大英語の過去問を見てしっかりと問題形式を頭に入れておきましょう。
特に注意が必要な問題として要約問題、自由英作文が挙げられます。
①要約問題
この問題では、「英語の文章を読む読解力」「そこから重要な文章を抜き出す能力」「それらを簡潔にまとめる要約力」が求められます。
さらに、東京大学の英語は時間制限も厳しいため以上のことを10分程度で行う必要があります。
演習量が物を言う問題なので、東大の要約に特化した問題集を解いて重点的に対策することをおすすめします。
②自由英作文
英作文は、多くの大学で出題されると思います。
ではなぜわざわざ取り上げたのかというと、東京大学の自由英作文では書くべき内容を考えるのが非常に難しいということがあるからです。
例えば2022年の問題は、「芸術は社会の役に立つべきだという主張について。あなたはどう考えるか」というものでした。
どうでしょうか。ぱっと解答が思いつくでしょうか。
そもそも日本語ですら解答が難しい問題に、英語で答えなければいけない。ここに東大自由英作文の難しさがあります。
対策としてはとにかく単語力を増やして書きたいことが英語で書けるようにすること、普段から勉強以外にもアンテナを様々なものに伸ばして色々な考え方を吸収しておくこと等が考えられることでしょう。
何度も言いますが、東大英語では問題形式に慣れておくことが最も重要です。このことを忘れないでおいてください。
数学
東京大学の数学は、難易度の高い問題のセットとなっています。
配点も、二次試験440点満点中120点と非常に大きな割合を占めていますので、英語とともに最も重点的に対策して勉強するべき科目の一つとなっています。
東大数学に限らず、数学一般で重要となってくる考え方は、「すべての問題は人間が作ったものである」ということです。
一見どのように解けばよいかわからない問題でも、基本的な知識や考え方に立ち返ることで絶対に解放の手がかりが見つかるはずです。
そのために演習をこなす中で意識するべきことは、解けない問題に出会ったときに、「どのような思考プロセスを経ればこの開放にたどり着くことができるのか」ということです。
ただ解答を読んで満足するのではなく、疑問→理解という過程を何度もこなすことで自然と力がついてきます。
演習量ももちろん重要ですが、質の高い演習をこなしていきましょう。
また、東京大学の数学は完全記述式となっていますから、独りよがりにならず採点者に自分の思考過程を伝えるという気持ちで答案を書いていく練習もしておくとなお良いです。
理科二科目
東京大学の理科は、化学・物理・生物・地学の4科目の中から2科目選んで解く形式となっています。
もちろん得意な2科目を選ぶことが良いですが、特に選びたい科目がないという場合には物理・化学の組み合わせがおすすめです。
理由として、この2科目を選ぶ東大受験生が最も多く、それだけ入試対策としての道筋も確立されているからということが挙げられます。
ここでは、簡単に物理・化学の勉強法の方針について触れておきます。
物理
この科目では、物理現象を根本から理解することが最も重要となってきます。
あやふやな理解では全く点数が取れないですが、逆にしっかりと理解することで8割9割程度の点数が安定するでしょう。
そのためにすべきことは、演習の中で出てくる1問1問にしっかりと向き合うことです。
がむしゃらに演習量を増やすのではなく、自分が本当にその現象を理解できているのかを考え、理解できていないなら徹底的に怪しい点を潰していきましょう。
化学
化学は物理とは異なり、演習量をこなすことで知識を増やしていくことが重要です。
教科書に乗っている知識には限界がありますから、問題集や過去問を解いていると初見の問題に出会うことも多々あるでしょう。
その初見の問題を、いかに自分のものにしていくかが本番で高得点をもぎ取る鍵となります。
おすすめの勉強法としては、初見の知識や忘れやすい知識をまとめたオリジナルノートを作成して、試験前に見返すことができるようにすることです。
時間は2科目合わせて150分となっており、1科目に割くことのできる時間が75分とかなりタイトなタイムスケジュールです。
迷いなく解答を導くことのできる知識と、精密な計算力が要されますから、十分な対策を行いましょう。
面接
東京大学では、理科3類のみ二次試験に面接が課されています。
面接試験は2007年度入試から一度廃止されたのですが、2018年度入試から面接試験が再び復活したのです。
ただし、面接試験については現状そんなに恐れる必要はありません。
学力試験でついた順位が面接で覆ることは非常に稀なケースだからです。
ただし、医師になる人間として不適格な発言をしてしまうと一発アウトになる可能性はあります。
真偽は定かではないですが、実際にそのような例があったという話も聞きます。
勢いで発言するのではなく、しっかりと言葉を選びながら回答をしていきましょう。
理科3類の面接で聞かれる内容としては、医学部を選んだ理由だったり、理想の医師像であったりとシンプルかつ医学部面接ではメジャーなものが多い傾向にあるので、あらかじめ無難な回答を準備しておくと本番で詰まったりパニックになったりせずにスムーズに試験を進めることができるでしょう。
また、服装ももちろん採点対象となるので、面接対策本に則って悪目立ちしない格好を意識してください。
一般入試の入試結果【最新2022年度分掲載】

では最後に、東京大学医学部の過去の入試結果を最新情報で確認してみましょう。
東京大学理科三類では前期日程と学校推薦型がありますが、後者は3名程度と狭き門であり医学部再受験生には無関係なため、ここでは前期日程のみをご紹介します。
東京大学前期入試【過去の志願者倍率】
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 志願者数 | 421 | 385 | 413 | 405 | 450 | 527 |
| 第1段階選抜合格者数 | 340 | 342 | 340 | 340 | 389 | 388 |
| 二次試験受験者数 | - | 335 | 330 | 331 | 378 | 377 |
| 最終合格者数 | 97 | 98 | 97 | 97 | 98 | 98 |
| 倍率 | - | 3.42 | 3.40 | 3.41 | 3.86 | 3.85 |
なお、倍率は二次試験受験者数/最終合格者数で算出した実質合格倍率としています。
東京大学では毎年二段階選抜が行われており、2019年までは4.0倍、それ以降は3.5倍となっています。
ここ数年の実質合格倍率は3.4前後で、二段階選抜の基準が下げられたことも加味すると、医学部入試全体の不人気傾向を反映した数字とも読み取れます。
東京大学前期入試【2022年度の試験科目と配点】
| 試験 | 数学 | 理科 | 英語 | 国語 | 地歴 公民 |
合計 | 換算得点 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通テスト | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 900 | 110 | 20.0% |
| 2次試験 | 120 | 120 | 120 | 80 | - | 440 | 440 | 80.0% |
| 合計 | 550 | 100.0% |
東京大学理科三類では、面接が課せられますが、これについての点数化は明記されていません。
あくまで在校生からの情報ですが、教授陣が「明らかな不審者を落とすためだけの面接」と謳っていることからも不正入試を疑う余地はない印象です。
全体としては二次試験に大きく配点が偏っており、過去問研究が命と言われる根拠でもあります。ただし、これを理由に共通テスト対策を怠るようでは学習として本末転倒。
東大で要求される考察力は全て基礎力・理解力によるため、医学部再受験生も基礎の徹底は十分に図りましょう。
過去の合格最低点・合格平均点
続いて、東京大学理科三類の過去の合格最低点・合格平均点のデータを確認しましょう。こちらは、理科三類のみの集計データです。
| 理三のみのデータ | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通テスト | 第1段階選抜合格者 の合格最低点(得点率) |
58.7% | 59.3% | 67.9% | 70.0% | 70.0% | 77.2% |
| 110点満点 | 第1段階選抜合格者 の合格平均点(得点率) |
73.2% | 84.2% | 86.7% | 89.1% | 88.1% | 88.6% |
| 総合点 | 合格最低点(得点率) | 63.2% | 68.4% | 70.2% | 70.0% | 71.3% | 74.2% |
| 550点満点 | 合格平均点(得点率) | 68.6% | 73.8% | 75.3% | 74.7% | 76.0% | 78.7% |
旧センター試験では平均88%の得点率であり、共通テスト移行後も初年度でありながら平均84.2%という点が、さすが東大理三というデータです。
なお、2021年度のデータからは、二次試験については合格者平均71.2%であったと推定されます。
東大を目指す医学部再受験生は、共通テストでは約85%、過去は約73%程度を安定して取れることが目標となっていきます。