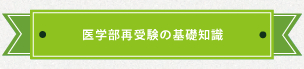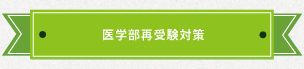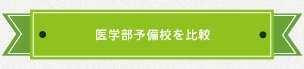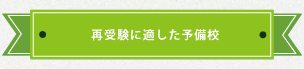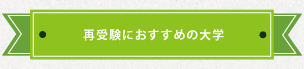医学部再受験のお金事情について知りたい!

医学部再受験にあたって、まず問題となってくるのが金銭的な問題です。
他の学部以上にハイレベルな勉強をしなければいけない分、それにかかる費用も膨らんでしまい、途中で諦めてしまった……という人も。
この記事では、勉強費用から生活費、学費に至るまで、医学部受験、特に医学部再受験を検討する場合の金銭・費用事情について紹介します。
問題や解決策についても記してありますので、是非最後までご覧ください。
【準備編】独学の場合にかかる主な対策費用

まずは、予備校等に通わず自宅等で勉強する場合の費用について考えていきます。
勉強に必須!参考書・教材代
合格を目指す勉強をするうえで避けて通れないのが、参考書や教科書などの教材費です。
著名な参考書・問題集の価格は、次の通りです。
| 大学入試過去問題集(赤本) | 東京大学 理科 | 2530円(Amazon) |
|---|---|---|
| 共通テスト実践問題集(駿台) | 各教科(計9教科必要) | 1375円(Amazon) |
| 標準問題精講(問題集) | 数学(数ⅠA~数Ⅲまで必要) | 1320~1600円(Amazon) |
※なお、私立医大を受ける場合は、大学の入試形式によっては共通テストの実践問題集が必要なくなることもあります。
これを見ると分かるように、一つ一つの問題集・参考書の価格は手ごろなものの、それを何冊も買う必要があることで費用が高くなってしまいます。
さらに、医学部再受験では高校時代に使った問題集・参考書では戦えないことも多いため、現役生と異なり新たに揃えるべき教材が多くなります。
そのため、「自分に合ったいい教材を見つけ、それを何度も勉強する」ということが必要になってきます。
勉強場所はどこを使うべき?カフェ?図書館?自習室?
医学部再受験で独学を選択する場合、勉強場所も大きな問題になってきます。
現役生であれば高校の自習室や図書室を利用することができますが、医学部再受験ではそうはいきません。
選択肢としては、
- 図書館
- 有料自習室
- カフェ
- 自宅
が挙げられます。
勿論、自宅で受験勉強を行うのが費用・時間的には最適ですが、自宅で勉強に集中できない人は他の選択肢を考慮しましょう。
図書館は、ほぼすべての場合無料で使用できます。
その費用がかからないということが最大のメリットです。大学に通う医学部再受験生の場合は、その大学の図書館を使うのも良いでしょう。
ただし、図書館は高校生などの学生もよく利用し、自習スペースが混雑することもあります。
有料自習室は、1時間500円程度、月単位で使用する場合は月1万円程度で利用することのできるスペースです。
図書館と違い有料で費用はかさみますが、周りの人も同様にお金を払って勉強しているということから、図書館ほど混雑せず、静かな空間が保証されています。
条件面では、図書館以上といえるでしょう。
カフェは、王道の勉強場所ではありますが、周りのお客さんは必ずしも勉強しに来ている訳ではなく、使うにもお店の商品を注文する必要があるため、気分転換程度に考えるのがよいでしょう。
他にも、会社に勤めている医学部再受験生は、会社のフリースペースを使うということもできます。
費用や混雑度を考慮しながら、有効活用しましょう。
【準備編】大手・医学部予備校に通う場合は?
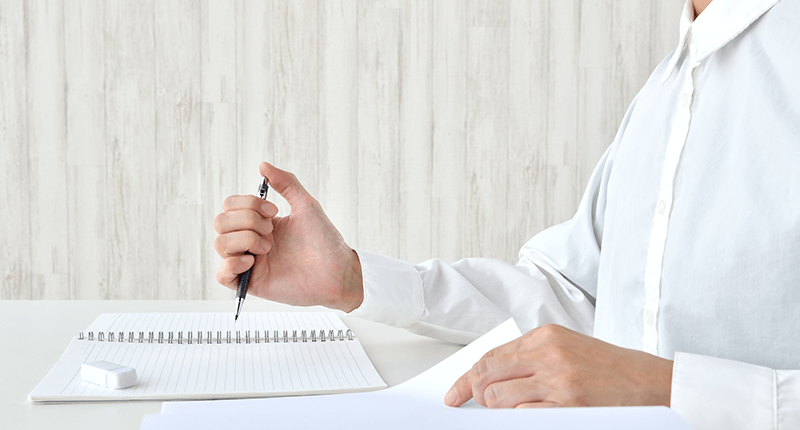
次に、大手予備校・医学部予備校に通った場合の医学部再受験にかかる費用について考えていきます。
独学との最大の違い:授業料
まず考えなければならないのは、予備校への学費・入学金についてです。
以下に、主な選択肢となる予備校の学費を示します。
| 予備校名 | 年間授業料 |
|---|---|
| 河合塾 トップレベル国立大医進コース | 790,000円 |
| 駿台予備校 スーパー国公立大医系 | 860,000円 |
| 代々木ゼミナール 国公立医系 | 795,000円 |
| メディカルラボ | 4,422,000円 |
| 東京メディカル学院 | 1,650,000円 |
※入学金・施設維持費等は含みません。
これらの通り、大手予備校の河合塾・駿台予備校は比較的安い学費で授業を受けることができます。
ただし、医学部予備校はその学費の分だけ密着型の授業を行っていることが多く、費用こそかかるものの医学部再受験において一つの選択肢となっています。
無選抜で医学部受験に特化した指導・対策が受けられるのも医学部予備校の強みの1つで、大手では選抜コースに在籍できない限り医学部に的を絞った勉強が出来ない点は注意しておきましょう。
寮費がかかるケースも!
医学部専門予備校では、全寮制の場合が多くあります。
それに加えて、大手予備校に通う場合でも、県外の予備校に通う場合は、その予備校の寮に寄宿して1年間生活することが多くあります。
その場合は、生活費を含めた寮費を払う必要があります。
例えば、河合塾の「東京飛躍寮」で生活する場合、約100万円の費用がかかるほか、それに昼食費を含めた生活費が必要となってきます。
【入試本番編】受験にかかる費用は?

さて、ここからは医学部再受験の入試本番にかかる費用についてみていきます。
国公立大学の推薦・AO入試が現役生を中心とした入試システムであるということもあり、国公立大学の入試は前期入試・後期入試の2回のチャンスしかないと考えていいでしょう。
一方、私立大学は大学ごとに入試日程が異なるため、日程が許す限り多くの大学を受験することができます。
ここでは、東京に住む医学部再受験生のパターンを例にとり、以下の大学を受験する想定で、費用のシミュレーションをしてみましょう。
- 大学入学共通テスト受験
- 国公立大学入試/前期:千葉大学 後期:秋田大学
- 私立大学入試/国際医療福祉大学、順天堂大学、北里大学
出願料は国公立大学と私立大学で大きく異なる!
国公立大学と私立大学の入試の最大の違いは、出願料です。
まず、上記の大学の受験費用を示します。
| 大学入学共通テスト | 18,000円 |
|---|---|
| 国公立大学受験料(前期・後期共通) | 各17,000円 |
| 国際医療福祉大学 | 60,000円 |
| 順天堂大学 | 60,000円 |
| 北里大学 | 60,000円 |
見て分かるように、国公立大学にくらべて私立大学の受験費用が非常に高いことが分かります。
多くの大学を受けられるのはメリットですが、費用が掛かる点に留意しながら、受験する数を検討するとよいでしょう。
移動費・宿泊費がかさむケースも
医学部再受験で遠方の地域にある大学を受験する場合、移動や宿泊に係る費用も必要になってきます。
また、受験当日はホテルが非常に混雑し、特に地方では受験間際では予約が取れなくなってしまう事もあります。
そのような場合に備えて、キャンセル費用がかからないホテルを、出願を検討している段階で押さえておくのがよいでしょう。
移動費に関しては、割引制度を使うのがおすすめです。
大学に通う医学部再受験生の場合は学割(15%引き)を、そうでない医学部再受験生は各会社の割引制度を活用しましょう(たとえば、JR東日本では「えきねっとトクだ値」を実施しており、新幹線が最大30%引きになります)。
【進学以降】馬鹿にならない!入学後の金銭事情
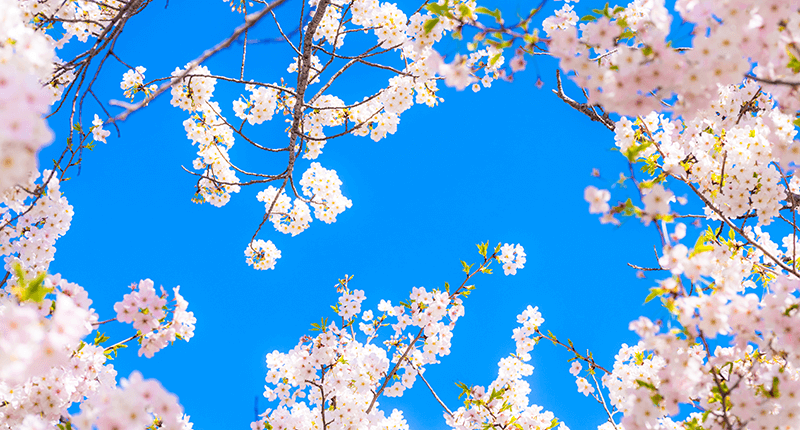
ここからは、医学部再受験後、つまり大学入学後にかかる費用についてみていきます。
学費は固定?試験で落ちると……?
まずは、学費です。
シミュレーションにて挙げた各大学の学費についてみていきましょう。
| 国公立大学(千葉大学・秋田大学) | 535,800円/年、入学金282,000円 |
|---|---|
| 国際医療福祉大学医学部 | 1,900,000円/年、入学金1,500,000円 |
| 順天堂大学医学部 | 2,000,000円/年(1年次のみ700,000円)、入学金2,000,000円 |
| 北里大学医学部 | 6年合計38,900,000円(入学金、他諸費用含む) |
これを見て分かるように、国公立大学にくらべて私立大学の学費は非常に高くなっています。
これに加えて、施設維持費などの諸費用がかかる場合もあり、さらに膨れ上がる可能性もあります。
一方で、国公立大学にくらべて私立大学は学費免除・支援制度等も充実しています。
なお、一部の私立大学の場合、試験に落ちると「再受験料」として、試験を受けるためにお金が必要になってくる場合もあります(例:獨協医科大学/5,000円、日本医科大学/1教科10,000円)。
生活費は他の学部よりかさみがち
医学部生の生活は、大学によって大きく左右されます。
国公立の総合大学(例:東京大学、東北大学など)は入学後しばらくは基本的に他の大学生と変わらない授業を取ることが多いです。
しかし、国公立大学でも医学部独自のカリキュラムが1年次から始まる場合、もしくは私立大学の場合、1年次から医学専門教育が始まり、難しい勉強や試験が始まります(前述の総合大学でも、2年次以降は専門教育一色になります)。
そのため、生活は授業や試験の為、自炊する余裕がない人が多く、どうしても生活費がかさみがちになります。
なお、全寮制の医学部(例:岩手医科大学や自治医科大学)の場合は、生活費の代わりに寮費が必要となるので、注意が必要です(岩手医科大学の場合は、費用は836,000円になります)。
また、医学部部活に入る人が多いため、その費用、例えば遠征費や飲み代をやりくりしなければなりません。
他にも、医学部のキャンパスは他の学部に比べて僻地に存在することが多く、その場合の交通費や車にかかる費用についても考慮する必要があります。
専門的な教材は意外と高め
最後に、教材にかかる費用についてのお話です。
医学の勉強では、さまざまな専門書や動画教材が必要となります(「病気がみえる」シリーズ、「イヤーノート」他)。
それらの教材は高額なことが多く、「いかに必要な教材を選択するか」が費用を抑えるポイントとなってきます。
以下に、著名な医学専門教材の費用を示しますので、参考にしてください。
| 病気がみえる 電子版 | 44,550円(全巻セット) |
|---|---|
| Q-assist(動画教材) | 39,600円 |
| イヤーノート | 23,100円 |
| プロメテウス解剖学アトラス | 13,200円 |
| Ross組織学 | 10,120円 |
| クエスチョン・バンク(国試対策) | 12,100円(1巻あたり、全7巻) |
現役医学部生が教える!医学部再受験生におすすめ費用節約術

ここからは、現役医学生の筆者がおすすめする費用節約術について解説します。
①再受験生は図書館と有料自習室を交互に活用せよ!
まず、勉強場所についてです。
前述の通り、図書館は費用的に利点があるものの、混雑することが多くあります。
特に、高校生の試験期間である6月・9月・11月・2月は混雑が予想されます。
私のおすすめは、通常は図書館を、混雑期間に有料自習室を使うということです。
基本的に費用がかかる有料自習室は学生の利用が少なく、その時期も快適に利用できます。その時期以外は図書館を利用して、費用を抑えましょう。
②国公立大学を狙え!
次に、大学選びについてです。
紹介した通り、私立大学は入学金・学費が高額です。
そのため、できるならば第一志望は国公立大学にするのがよいでしょう。
医学部再受験生に対しても私立大学に比べて寛容なことが多く(ある私立大学では医学部再受験生への差別が問題になったことは記憶に新しいと思います)、しっかり勉強すれば合格の可能性が高まります。
また、国公立大学はオーソドックスな問題が出題されており、その対策は仮に他の国公立大学や私立大学に志望校を変えたとしても応用できます。
「費用の面」「勉強の面」の2つにおいて、医学部再受験生が志望校を国公立大学に定めることは効率的といえるでしょう。
そのうえで、サブプランとして、私立大学を1~2大学受験するのがおすすめです。
③学費は学費免除制度と奨学金を使いこなせ!
最後に、大学入学後の費用についてのお話です。
先に述べたように、大学入学後も費用はかさんでしまいます。そこで、学費免除制度や奨学金を活用しましょう。
たとえば、私立大学では、入学時の成績によって特待生制度が定められていることが多く、例えば順天堂大学では計1,380万円の減免制度があったり、国際医療福祉大学では奨学金として6年間で最大1,400万円を給付する制度があります。
これらによって、私立大学の費用を国公立大学並みに抑えることもできます。
国公立大学に入学した場合でも、奨学金制度は充実しています。
たとえば、日本学生支援機構の奨学金は、採用基準こそありますが、給付型で月額7万円ほど、貸与型では月額6万円ほどの奨学金が得られます。
また、自治体や民間病院グループによる奨学金がある場合もあり、卒業後医師として指定病院への勤務が求められますが、償還免除型の給付金を得られることもあります。
それら、奨学金の制度をうまく活用し、生活や勉強にかかる費用を賄っていきましょう。
医学部再受験でかかる主な費用まとめ
いかがでしたでしょうか?
この記事では、医学部再受験にかかる費用について紹介しました。
医学部再受験は他の場合に比べて費用がかさみがちですが、うまく制度や環境を活用すれば費用を抑えることが可能です。
この記事をご覧になった皆さんが、医学部に無事合格し、充実した生活を送ることをお祈り申し上げます。