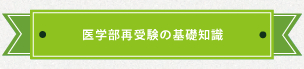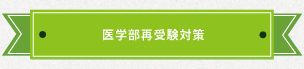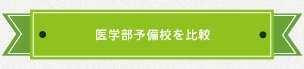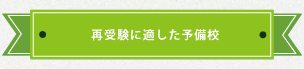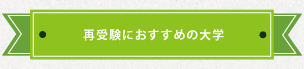医学部再受験生にとって学費や生活費を工面することが非常に重要な問題になりがち。
そこで大きな支えになってくるのが奨学金制度です。
今回は、医学部再受験生にとって役立つ奨学金制度について制度の仕組みや注意点をも踏まえながら詳しく紹介していきます。
奨学金制度は医学部再受験でも利用可能
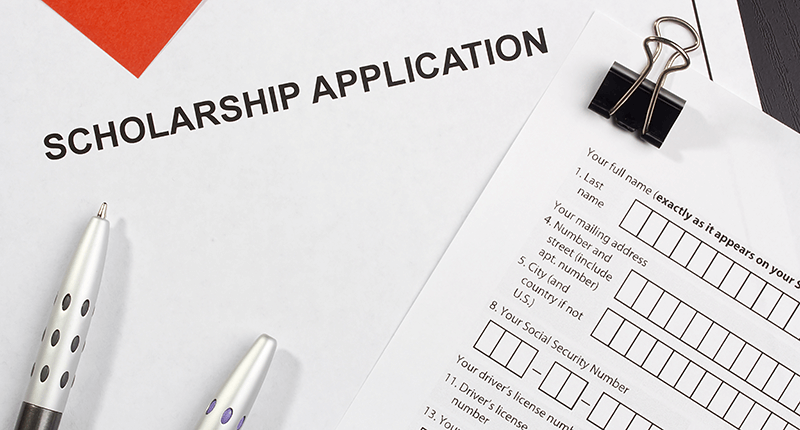
奨学金制度は、年齢制限は基本的にありません。
したがって、医学部再受験生でも利用することが可能です。
奨学金には「給付型」と「貸与型」の2種類の制度があります。
給付型の場合、もらった奨学金は返済免除となり、卒業後の負担がありません。
ただし、給付型の奨学金は数が少なく、もらえる人がほんの一握りです。
いっぽう、貸与型の奨学金は、医学部再受験生を含めより多くの学生が利用できますが、返済義務が生じてしまいます。
また、返済の場合は金利が上乗せされることも多く、卒業後は経済的負担が生じてしまいます。
多くの学生が利用する日本学生支援機構とは
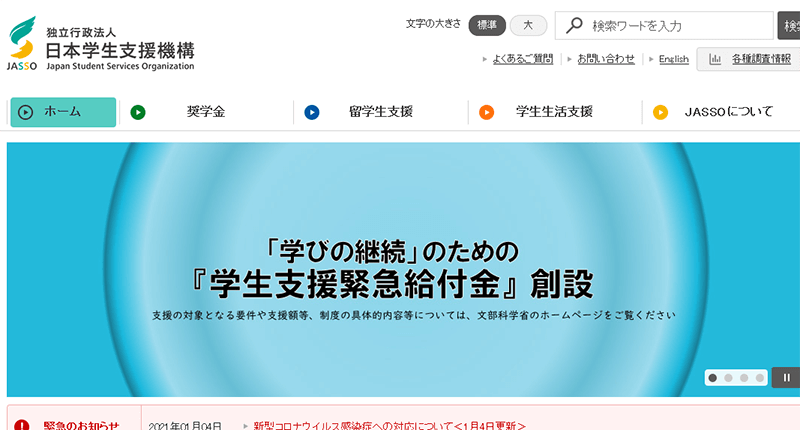
多くの医学部再受験生が利用している奨学金が日本学生支援機構です。
日本学生支援機構には第一種と第二種の奨学金が用意されていますが、種類によって高校の成績や所得の審査基準が異なります。
第一種は、無利子の奨学金ですが、借りられる金額は最大64,000円となり、私立の医学部だとそこまで補填になりません。
そこで、医学部再受験生におすすめなのは第二種の奨学金です。
第二種なら第一種よりも審査の基準も緩く借りられる奨学金の額も大きいので、学費が高くなりがちな医学部生には最適な奨学金制度であると言えるでしょう。
それでは、第二種の特徴について詳しく確認していきます。
医学部医学科なら月額最大16万円を6年間貸与
第二種奨学金は、大学の場合、月額2万円から12万円の1万円ずつ刻みで申請可能。
しかも、私立大学医学部の場合は12万円に4万円の増額が可能で最大16万円まで借りることができます。
つまり、6年間総額で1,152万円となり、2000万円前後の私立大学医学部なら学費の半分程度をカバーすることができます。
このように第二種奨学金を利用すれば、国公立大学だけでなく、私立大学の医学部再受験も目指すことができるかもしれません。
教育ローンと違い低金利で借りられる
日本学生支援機構の第二種奨学金は有利子です。
しかし、営利目的ではないため、利子率は最大3%で、在学期間中は無利子と良心的。
しかも、利子率は最大3%で実際は、高くても1%台であるため、金利負担額はそこまで重くはありません。
銀行などで教育ローンを組むよりも、返済負担は軽いと言えるでしょう。
医学部再受験生向け日本学生支援機構の注意点

医学部再受験の場合は在学採用型のみ
日本学生支援機構の奨学金は、「予約採用型」「在学採用型」の2種類の応募方法から選ぶことが可能です。
ただし、予約採用型の場合、高校卒業2年以内で過去に別の大学や専門学校へ入学したことがない人を対象にしているため、医学部再受験生は基本対象外となります。
つまり、高校卒業後3年が経過、または過去に大学等に入学したことがある医学部再受験生は在学採用型しか選択肢がありません。
在学型だと奨学金の申請が受理されても初回の振込は夏ごろになることが多く、その間の経済期負担を自分で補填しておく必要があります。
しかも、予約型の場合は医学部入学前に奨学金がもらえるか分かりますが、在学型だと入学後に奨学金の有無が分かるため、仮に奨学金がもらえない場合は学費負担が大きく増えることになります。
過去に奨学金を借りていた場合はハードルが高い
医学部再受験生の場合、過去に別の大学や専門学校に通っていた人が多いと思います。
この場合に注意すべきは、過去に日本学生支援機構の奨学金を利用したことがある人は、利用できない、あるいは利用できても貸与期間に制限がある場合が出てきてしまいます。
ただし、絶対に無理ではないですが、日本学生支援機構の公式サイトにも大学の奨学金担当者に問い合わせる旨の文言が記載されているので、医学部再受験生で既に奨学金を借りたことがある人は、一度問い合わせることをおすすめします。
貸与型であるため、返済の義務が生じる
日本学生支援機構は貸与型の奨学金制度です。
つまり、借りた奨学金は必ず返済する必要があり、第二種の場合は利子を上乗せして返す必要があります。
医師になることができれば、安定した報酬も支給されるのでそこまで心配する必要ありませんが、近年は奨学金が返させない人が増加していて社会問題にまで発展。
貸与型の奨学金はあくまで教育ローンなどと同じく借金であることは変わりないため、計画的な返済計画を立てる必要があります。
日本学生支援機構の奨学金も返済を滞納してしまうと、延滞金や督促が生じ、財産差し押さえや、信用情報への金融事故扱いなど、他の債務と同じ流れとなってしまうので注意が必要です。
留年した年度は奨学金が止まる
日本学生支援機構に特化した制度ではないですが、留年した場合はその年の奨学金はストップしてしまいます。
もし、次年度に無事に進級できた場合は奨学金の支給が再開される仕組みです。
他学部であればさほど問題ありませんが、医学部医学科の場合は進級率が低い大学も少なくありません。
しかも、私立の場合は学費も高額なので、1年留年するだけでも多額の授業料が発生してしまいます。
医学部再受験でせっかく大学に合格しても留年で学費が払えず退学していく学生もいるのは事実。
したがって、奨学金を借りることを想定している場合、医学部再受験を目指している段階では進級率の高い大学を選んだり、また、大学入学後も留年リスクがあることを見据えて勉強に励む必要があります。
大学独自の奨学金制度
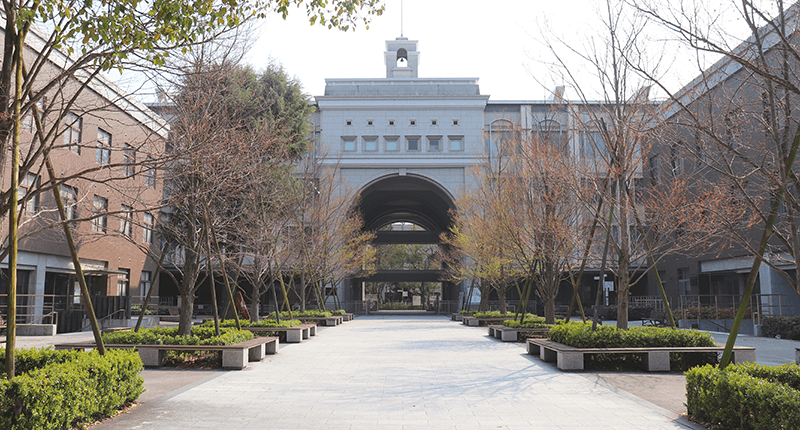
返済免除になる特待制度がある
大学に設置されている奨学金制度の中で、特待生の場合は給付型の奨学金であることがほとんど。
つまり、支給された奨学金は返済免除となります。
その代わり、特待生制度の場合は成績優秀者に限られるため、基準をクリアするには高度な学力が必要です。
医学部再受験生でお金に余裕が無い場合は、ワンランク医学部のレベルを下げて特待生を狙ることも1つの方法でしょう。
ただし、入学後もずっと6年間給付型の奨学金がもらえる保証はありません。
もし、大学入学後に成績が下がれば、特待生から外れることもあります。
地域枠は学費相当額の奨学金が借りられる
学費相当額の奨学金が返済免除になることで注目されているのが地域枠制度です。
地域枠とは、自治体が医師を確保するために、学費相当額の奨学金を貸与し、卒業後に一定期間その土地で医師として働くことで返済が免除となる制度です。
これを利用すれば私立大学医学部でも実質学費負担がゼロで学ぶことができます。
ただし、地域枠の場合は推薦入試で設けているところも多く、年齢条件は現役生または1浪人生が多いことです。
医学部再受験生の場合は30代や40代も多いですが、この場合は受験資格がありません。
したがって、医学部再受験の場合は、日本学生支援機構や大学独自の奨学金制度を利用することになります。
まとめ
以上、ここでは日本学生支援機構の奨学金制度を中心に医学部再受験生が学費を工面する方法を解説してきました。
医学部再受験生は社会人を経験し、経済的に親から独立していて貯金を崩して医学部を目指す人も多いと思います。
この場合、日本学生支援機構の奨学金制度を利用することが一番現実的ですが、応募には注意点もあるので、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。
奨学金を利用して受験体だくの選択肢を1つでも増やすことが、医学部再受験を成功させるためには非常に重要となってきます。