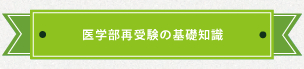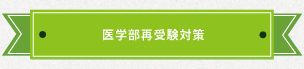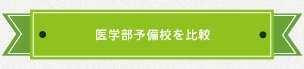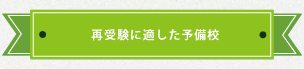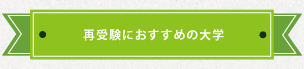医学部再受験の掲示板について解説
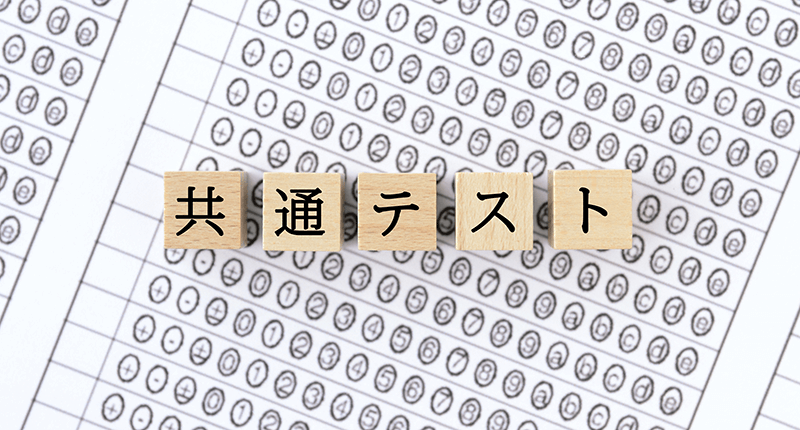
国公立の医学部を受験する上で欠かすことができないのが共通テスト対策です。
大学によっては共通テストでほとんど勝負が決まってしまうようなところもあるほか、二段階選抜を実施しているような大学では共通テストの点数が低すぎるとそこで入試は終了となってしまい、面接や二次試験を受けることすらできなくなってしまいます。
医学部再受験生にとっても同様で、共通テスト対策を十分に行うことで志望校の選択肢が大幅に増やすことができます。
特に再受験生の場合は医学部再受験生に対して寛容な大学、不寛容な大学があることから、なるべく受験校の選択しは多くしたいですね。
そこで今回は医学部再受験生の共通テスト対策、勉強方法について紹介していきたいと思います。
医学部再受験と共通テスト
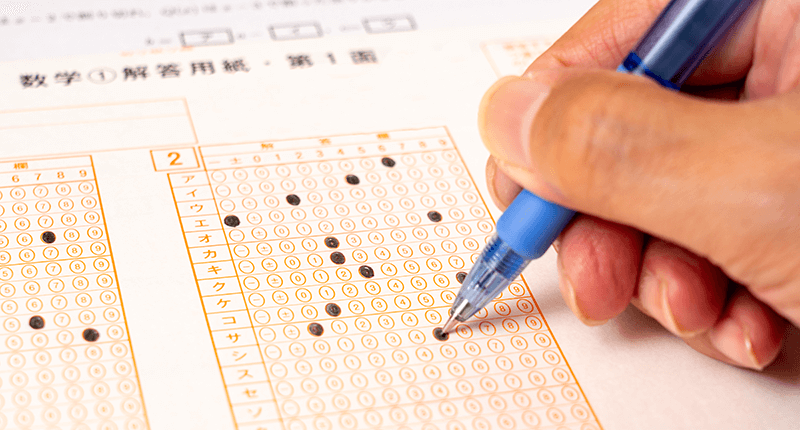
まず、共通テストについて簡単に解説していきたいと思います。
共通テストはセンター試験の後継にあたるもので、毎年1月に実施されています。
出題形式はセンター試験と同じく全教科マーク式となっており、センターよりも思考力、判断力が重要視されています。
具体的には英語の試験において発音、アクセントが出題されず、代わりに読解問題の出題が増えたり、数学の試験では日常生活を題材としたような会話形式での出題が行われたりと知識、解法の丸暗記だけでの対策が通用しづらくなっています。
医学部再受験生では年齢の面において現役生よりも不利になりがちですが、思考力や読解力でカバーすることで十分太刀打ちできると思います。
医学部入試の場合の受験科目とボーダー
国公立の医学部を受験する場合、共通テストでは国語、数学(ⅠA,ⅡB)、英語、理科2科目(物理、化学、生物)、地歴公民を受験することになると思います。
医学部再受験生の場合、共通テストで70%後半~80%中盤を目標としておくといいでしょう。
80%中盤を超えるようになると私立医学部の共通テスト利用選抜での合格も視野に入るため、私立狙いの人も共通テストで高得点を取ることに越したことはありません。
ただし、共通テストは実施されるようになってから年が浅く、年度ごとによって難易度、傾向の変動が大きいです。
模試や本番で得点率をあまり意識しすぎすると時間が足りなくなってしまったり、メンタルが崩れてしまうのであくまでも参考程度にとどめておきましょう。
医学部再受験生の場合、ほとんどの科目をゼロからスタートすることになるかと思います。
特に文系出身の方などは理系科目を基礎からのスタートとなるかと思います。
そういった場合、必要によっては中学範囲の参考書も用意しておくといいでしょう。
各科目の概要と対策・勉強法

それではここから、共通テストの各科目の概要と医学部再受験生の対策するポイントについて紹介していきたいと思います。
英語
概要
まずは共通テストの英語についてです。英語はリーディング100点、リスニング100点の計200点構成となっています。
センター試験を経験された医学部再受験生にとってはリーディング200点、リスニング50点というのが馴染み深いかと思いますので、勉強方法には注意するようにしましょう。
リーディングの設問内容は以下の表のようになっています。
| 大問 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 書籍、web情報の読み取り |
| 2 | 記事、施設案内文の読み取り |
| 3 | ブログ、雑誌記事の読み取り |
| 4 | 複数のブログ記事の読み取り |
| 5 | 伝記文の読み取り |
| 6 | 論理的な文章の読解 |
このような構成になっています。
センター試験の時に比べ、共通テストでは文法やアクセントといったように知識そのものを問う問題よりも知識を使って実際の文章を読み取る問題が多く出題されています。
文量も多く、かなり時間がかかると予想されます。
読み取り問題が中心なので、二次試験の勉強を行うことも共通テスト対策につながるかと思います。
医学部再受験生の中には英語を普段から使っているような方もいるかと思いますが、そういった方は共通テストにおいてかなり有利なのではないでしょうか。
次にリスニングです。
| 大問 | 設問内容 |
|---|---|
| 1 | 短い発話の内容に合う英文、絵を選ぶ |
| 2 | 短い対話の内容に合う絵を選ぶ |
| 3 | 短い対話の内容について質問に合う答えを選ぶ |
| 4 | 情報の整理、複数の対話を比較してふさわしい発話を選ぶ |
| 5 | 社会的話題に関する講義を聞き、質問に合う答えを選ぶ |
| 6 | 会話、議論を聞いて質問に合う答えを選ぶ |
こちらがリスニングの内容です。
前半は平易な語句が多く使われる設問で難易度は低いのですが、後半になるにつれて内容をまとめる力や意見を整理して判断する力といったようにスムーズに解くことが難しいような設問もあります。
リスニングは読み上げ回数が決まっているため、焦ると普段通りの力を出せないということが起こりえます。
医学部再受験生は普段から日常的に英語のニュースなどを聞いておくのがよいかと思います。
英語の対策ポイント・勉強法
医学部再受験生の共通テスト英語の勉強法についてです。
リーディングでは共通テストになって文法の設問がなくなったものの、解答する上で不要になったというわけではないため、文法、語句は参考書を用いて学習するようにしましょう。
また、必要な情報を読み取って正しい選択肢を選ぶという能力が求められているため、医学部再受験生はセンター試験のイメージで本番に臨むと危険です。
まずは共通テストの過去問に目を通し、時間配分をイメージしてみるのがおすすめです。
リスニングも同様で、音源が公式サイトで配布されているので読み上げスピードなどを確認しておくといいでしょう。
普段英語をあまり使わない医学部再受験生の場合、まずは単語や文法といったようにインプットから始めましょう。
基礎レベルの単語帳、文法問題集をスキマ時間で行いつつ、ある程度実力がついたら共通テストの長文の演習をするかといいと思います。
普段から英語を使う医学部再受験生の場合にはそこまで重点的に学習する必要はないかと思います。
ただし、日常的に使わないような文法、表現でも共通テストでは出題される場合があるので、念のため共通テストの過去問を数年分解いておくといいかもしれません。
国語
概要
次に共通テストの国語について、概要を解説していきたいと思います。
まずは大問ごとの設問内容について紹介していきたいと思います。
| 大問 | 設問内容 |
|---|---|
| 1 | 論理的文章 |
| 2 | 文学的文章 |
| 3 | 古文 |
| 4 | 漢文 |
共通テストになっても基本的にはセンター試験と変わらないですね。医学部再受験生の中にはかなり馴染み深く感じる方もいるのではないでしょうか。
ですが、出題形式は変更点がいくつかあるようです。
具体的に言うと論理的文章の問題で、出題文を読んだ生徒が作成したまとめノートの空欄に当てはまるものを解答するという問題がありました。
センター試験では見ない出題形式でしたので、医学部再受験生は注意が必要です。
そのほかにも古文では文章について教師と生徒が議論している会話の中で空欄に当てはまるものを選択するなどセンター試験の対策だけでは医学部再受験生は戸惑ってしまうような出題もみられました。
対策のポイント
医学部再受験生向けの共通テストの国語の対策方法についてです。
もともと国語はセンター試験から最も点数が安定しない科目と知られています。
模試では8割以上取れていても本番では5割を切ってしまうということは多々あり、とても怖い科目です。共通テストでもそれは同じかと思います。
安定して点数を取るために、医学部再受験生は普段の勉強からスピードを意識して解くようにするとよいと思います。
そのほかに高得点を狙うコツとして、古文、漢文を完璧にするという方法があります。
古文、漢文は知識や勉強量を積むことで比較的安定して高得点を狙うことができます。
この2つで9割を安定してとれるようになると評論、小説の調子が良くなくてもそこまで致命的な点数になることは避けられると思います。
国語の勉強法
医学部再受験生の具体的な勉強法として、評論、小説はまず過去問演習を重点的に行いましょう。
センター試験の過去問も参考になるかと思います。その際、時間も測ることで本番での時間配分もイメージがつくかと思います。
自分がどういった問題で点数を落としているかを確認し、同じタイプの問題にはなるべく時間を割くようにすると比較的点数が安定しやすくなると思います。
医学部再受験生は古文、漢文を勉強するときはまずインプットを行うようにしましょう。
古文の場合は基本単語、漢文の場合は句形ですね。
これらの勉強を進めつつ、こちらの場合も問題集、過去問で勉強することで読解力も鍛えられるようになると思います。
繰り返しになってしまいますが、古文漢文は点数が安定しやすいので高得点を安定してとれるようになることが医学部再受験生の合格への近道になると思います。
数学
概要
次は共通テストの数学についてです。
数学はⅠAとⅡBがあり、国公立医学部を志望の医学部再受験生ならば基本的にどちらも受験するかと思います。
まずは数学ⅠAの設問内容について紹介していきたいと思います。
| 大問 | 設問内容 |
|---|---|
| 1 | 数と式、図形と計量 |
| 2 | 2次関数、データの分析 |
| 3 | 場合の数と確率、整数、図形から選択 |
次はⅡBの設問内容について紹介していきたいと思います。
| 大問 | 設問内容 |
|---|---|
| 1 | 図形と方程式、指数関数、対数関数 |
| 2 | 微分、積分 |
| 3 | 確率分布、統計的推測、数列、ベクトル |
このようになっています。
こちらも国語と同じくセンター試験と出題されている内容はあまり変わっていないですね。
ただし、共通テストでは問題文の導入が会話形式であったり、日常生活の中にあるようなことが題材となっていたりとセンターからは変更点も数多くみられています。
対策のポイント
医学部再受験生の対策のポイントとして、基本的にはセンター試験と同じような対策方法でよいと思います。
二次試験よりも難易度は劣るため、マーク形式に慣れることと、スピーディに問題を処理する能力さえ身に着ければ高得点は安定して獲れるかと思います。
ゼロから医学部再受験をする場合、まずは教科書などで公式、基本定理の理解から始めるようにしましょう。
公式が理解できたら次は青チャートで公式の使い方、基本問題の解法を身に着けるようにしましょう。
普段働いていて時間がない医学部再受験生もいるかとは思いますが、数学の場合演習量がかなり大事となっています。
解くにスピードが求められる共通テストでは勉強した量が成績に直結してくるので、量にはこだわるようにしましょう。
数学の勉強法
なお、医学部再受験生の数学ⅠAのデータの分析という問題に注意しましょう。
データの分析は二次試験で出題している大学がほとんどないため、医学部再受験生は勉強力が少なくなりがちです。
教科書レベルを完璧に理解し、過去問演習をすればいいかと思います。
医学部再受験生の場合、共通テスト数学は得点源としたいですね。
ここで点数を稼いでおくと国語や地歴公民で多少失敗してもカバーすることができます。
理科(物理、化学、生物)
化学の設問内容
| 大問 | 設問内容 |
|---|---|
| 1 | 物質の構造、状態 |
| 2 | 物質の変化と平衡 |
| 3 | 無機物質 |
| 4 | 有機化合物、高分子化合物 |
| 5 | 熱化学、反応速度、有機化合物 |
物理の設問内容
| 大問 | 設問内容 |
|---|---|
| 1 | 小問集合 |
| 2 | 力学 |
| 3 | 電磁気 |
| 4 | 原子物理 |
生物の設問内容
| 大問 | 設問内容 |
|---|---|
| 1 | 霊長類の系統、ヒトの進化 |
| 2 | 植物と病原菌の相互作用、遺伝子導入 |
| 3 | 脊椎動物の肢芽の分化 |
| 4 | アリの道標フェロモン |
| 5 | 植物と動物の環境応答植物の生殖、ショウジョウバエの視覚と行動 |
共通テストの理科には物理、化学、生物の3種類があり、多くの医学部再受験生はこの中から2つを選択することが多いと思います。
現役の高校生では物理+化学を選択している人が例年多いと思いますが、物理は独学ではかなり難しいので予備校に通っていない医学部再受験生には少し厳しいかもしれません。
かといって生物選択が無条件でベストかと言われるとそうでもないのが現状です。
大学によっては二次試験の科目で物理が必須になっているところもあり、生物選択では志望校選択の幅が狭くなってしまうのです。
医学部再受験生にとっては志望校選択の幅が狭まってしまうのはかなりネックですね。
対策のポイント
共通テストの理科の対策のポイントです。
二次試験で理科が課される医学部再受験生は基本的に二次試験の勉強を優先していいかと思います。
二次で理科が課されない人は教科書~基礎レベルをしっかりと抑え、演習量を積むことで高得点を安定して狙うことができるかと思います。
理科は他の科目と違い、年によって出題内容や出題形式が変わっています。
なるべく多くのパターンに慣れるためにも、共通テストの過去問だけでなくセンター試験の過去問まで演習しておくと万全の体制で試験に臨むことができると思います。
理科科目の勉強法
ゼロから学習を開始した医学部再受験生は、他の科目と同じようにまずは教科書の理解から始めましょう。
理科に関しては教科書を理解しただけでは高得点を取ることはかなり難しく、問題集での演習が必須です。
基礎レベル~標準レベルまでの問題集を完璧にしておけば共通テストでも高得点が取れるかと思います。
ゼロからスタートした医学部再受験生には共通テストの理科が一番時間がかかると思います。
二次試験でも理科が出題される大学は多いので、よく勉強しておくようにしましょう。
理科も数学と同じく、医学部再受験生にとっては得点源にしたい科目です。
社会
概要
共通テストの社会では地理、日本史、世界史、倫政経などの科目から1つを選ぶことがほとんどではないかと思います。
今回は最も選択する学生が多いと思われる地理について紹介していきたいと思います。
まずは設問ごとの内容について紹介していきたいと思います。
| 大問 | 設問内容 |
|---|---|
| 1 | 世界の自然環境や自然災害 |
| 2 | 資源と産業 |
| 3 | 村落・都市と人口 |
| 4 | ラテンアメリカ |
| 5 | 地域調査(北海道苫小牧市とその周辺地域) |
こちらが共通テストの地理の概要になります。
センター試験の時と構成自体は変わってはいないのですが、共通テストになって図や表の出題が増えました。
ですが地理はもともと図の出題が多かったため、センター試験の地理を経験している医学部再受験生は共通テストでもほとんど同じ感覚で解くことができると思います。
対策のポイント
共通テストの地理の対策方法です。
大まかな出題形式は変わっていないので、現役時代に地理を選択していた医学部再受験生は現役の時と同じように勉強するといいと思います。
ただし、地理ではデータが年々変わるためなるべく最新の教科書、資料集を使うのがおすすめです。
社会の勉強法
ゼロからスタートした医学部再受験生もまずは教科書、資料集で学習しましょう。
地理は暗記科目というイメージを持たれがちですが、実際はそうではなく知識を身に着けた上での思考力が求められる科目です。
勉強する際は出来事やデータをただ暗記するだけでなく、その背景や理由についても着目するといいでしょう。
ちなみにですが、医学部受験生によって共通テストの社会の選択科目は割とばらつきがあります。
地理がいまいち合わないと感じた医学部再受験生は試験まで時間がある場合には他の科目に変更するのも手だと思います。
学士編入について

ここまで医学部再受験における共通テストの概要とその対策方法について紹介していきました。
ですが、特定の条件を満たした医学部再受験生には共通テストを受けなくても国公立大学の医学部を受験することができる方法があるのです。
その方法というのが学士編入です。
学士編入とは大学をすでに卒業した医学部再受験生を対象としたもので、合格すれば医学部の2年生や3年制に編入することができるというものになります。
毎年9月~11月ころに多くの国公立大学で実施されているため、共通テストの対策をしなくてもよくなります。
また、通常の入試では現役の高校生とも一緒に受験をすることになりますが、学士編入ではライバルは同じ医学部再受験生なので年齢という面でもハンデになりにくいです。
とはいえ、デメリットもあります。
学士編入試験では生命科学という高校の範囲を超えたレベルの科目が出題されます。かなり負担が大きくなるため、学士編入試験を受けて、共通テストを受けるとなるとかなりの勉強量が要求されます。
普段働いている医学部再受験生にとってはなおさらです。
【まとめ】医学部再受験と共通テスト
今回は医学部再受験生向けに共通テストの概要と対策方法について紹介しました。
共通テストはセンター試験と形式が一部似ているものの、思考力を問うような問題が増えたなど、医学部再受験生が対策なしで受験するとかなり危険です。まずは一度共通テストの過去問を確認するとイメージがつかみやすいでしょう。
ゼロからスタートする医学部再受験生はまず教科書と基礎レベルの参考書を用意しましょう。
まずは教科書を読み、問題集を解くことで理解が深まります。
また、ゼロからスタートする医学部再受験生は独学ですとどうしてもつまづいてしまいがちです。
共通テストだけでなく、二次試験のことも考えると予備校に通うのもとてもおすすめです。
医学部再受験ではとにかく年数をかけずに合格したいので、なるべく効率よく勉強するようにしましょう。