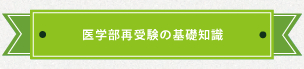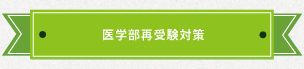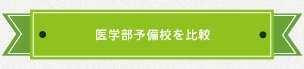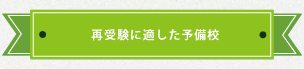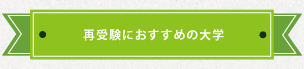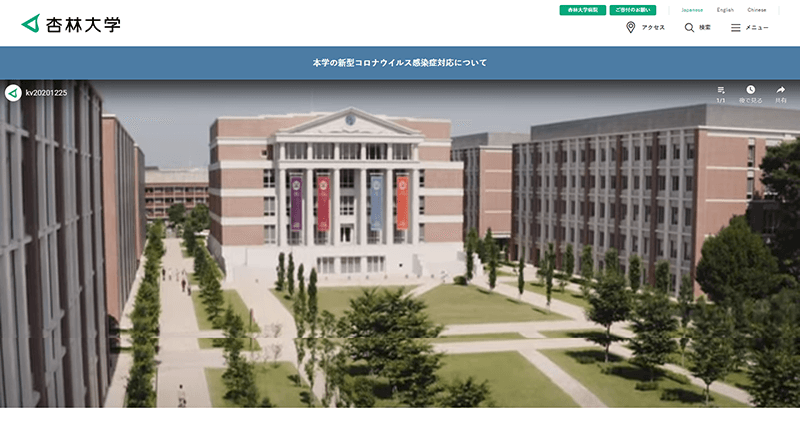
ここ数年で医学部の人気は高まりつつあります。
特に都内の医学部は顕著で私立医学部の偏差値ランキングでは上位がほとんど東京の医学部となっています。
その中でも比較的入りやすく、かつ国家試験合格率が高いのが杏林大学です。
国際交流の制度も充実しており、カリキュラムも非常に良いと評判です。
今回はこの杏林大学医学部の特徴、カリキュラムについて紹介したのち、医学部再受験生への寛容度や必要な勉強法について紹介していきたいと思います。
杏林大学医学部医学科の特徴・カリキュラム

医学部医学科の特徴
杏林大学は三鷹にキャンパスを構え、6年間一貫して三鷹キャンパスで授業が行われます。
三鷹駅からはバスで通う必要があるのですが、在学生の口コミ情報によるとアクセス的にはそこまで不便ではないそうです。
入学してから6年間同じキャンパスなのも便利ですね。
杏林大学のカリキュラムの特徴としてはただ知識のみを習得するだけでなく、医師として必要な倫理観、人間性の育成を目標とした指導を行っていることです。
具体的には低学年から医療、福祉の現場で実習を行うほか、少人数でのグループワークを行うなど教室以外での授業が多く設置されています。
医療の現場では知識はもちろんのこと、患者さんや医療スタッフとの適切なコミュニケーションをとることが欠かせません。
特に病気の患者さんやそのご家族とうまく接し、信頼関係を築くのは一朝一夕にできることではありません。
低学年のうちから医療の現場に参加できるのは勉強のモチベーションが高まるだけでなく、医師としての素養を高めることにもつながるのでとてもよい実習になるといえるでしょう。
奨学金などのサポート体制も充実
私立の医学部というと学費の面で心配という方もいるかもしれません。
特に、仕事を辞めて医学部再受験に挑戦しているような方であればなおさらかと思います。
杏林大学では経済的に困窮している方向けに独自の奨学金制度が存在しているほか、海外研修をする方向けの奨学金もあります。
国際色豊かな学風を売りにしている杏林大学らしい奨学金だと思います。
海外での実習視野に入れている医学部再受験生におすすめです。
6年間カリキュラム
1年次
杏林大学の1年次ではまず高校範囲の復習を行いつつ、医学に関する科学の学習を行います。
発生学や代謝学、生化学などですね。
病態の理解、薬の作用機序を理解するためにはこういった基礎医学を理解することがとても大事であるので、低学年のうちから学習できるのはとても効率的ですね。
こういった座学のほかにも、杏林大学では病院体験学習という授業も1年次で行います。
杏林大学附属病院や地域の病院に赴き、医師が現場でどのように働いているか、患者さんとの接し方を見学することにより、医学への学習のモチベーション促進、医師としての人間性向上ができるでしょう。
こういった実習では他の班員と話す機会が多いため、医学部再受験生も馴染みやすいのではないかと思います。
2年次
2年次でも1年次に引き続き基礎医学の勉強を行います。
解剖学、感染症など、医学にも直接関連するような内容もあります。
杏林大学では基礎医学研究棟というものがあることから基礎研究にも力を入れていることがわかります。
杏林大学では2年次でも実習を行います。
行動科学という授業では人間の行動を理解し、望ましい行動変容を行わせるための方法を学ぶほか、患者さん視点に立つ授業などを行います。
医学部再受験生はこういったグループワークでリーダーシップをとれるといいですね。
実際の医療現場でも医師は看護師さんや理学療法士さんなど、多職種の方との鍵でリーダーシップをとる場面が出てきます。
働いていたような経歴を持つ医学部再受験生は入試の際に伝えておくと有利になるかもしれません。
3年次
3年次ではいよいよ臨床医学が始まります。
また、4年次からは臨床実習が始まるため、身体診察の授業も行います。
実習で患者さんと接するときに必須の技術です。
医学に関する授業だけでなく、英語で少人数の議論を行うような授業もあります。
医学部再受験生の中には文系出身で英語が得意な方もいるかと思います。
国際色の豊かな杏林大学ですので、そういった方は面接でアピールするといいでしょう。
4年次
4年次では前半に臨床医学の授業を行ったあと、CBTとOSCEという試験を受けます。
どちらも全国の医大が臨床実習前に必ず行っており、今までの集大成ともいえるでしょう。
CBTでは医学に関する知識をコンピューターによる択一式の試験でチェックし、OSCEでは診察や医療面接の技術について、模擬患者さんを相手にして行います。
CBTとOSCEに合格すればいよいよ臨床実習が始まります。
医療スタッフの一員として、実際の患者さんと接したり治療の現場に立ち会ったりします。
5年次
5年生でも4年生に引き続き臨床実習を行います。
患者さんの担当医になったつもりで病歴を聴取したり、課題を解決するための検討を行ったりと実践的なトレーニングを積むことができます。
6年次
6年次では国家試験、そして実際に医師として働くため今までに学習した知識の総まとめを行います。
杏林大学は高い国家試験合格率を誇っており、質の高い授業を提供しています。
医学部再受験生は集大成となる学年です。
医学部再受験生への寛容度

杏林大学の基本データ
それではここから、医学部再受験生に対する杏林大学の寛容度について紹介していきたいと思います。
まずは、厚生労働省が公表している資料から引用した杏林大学の平成30年度における年齢別受験者の分布を紹介したいと思います。
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 18歳 | 475 | 456 |
| 19歳 | 722 | 485 |
| 20歳 | 471 | 301 |
| 21歳 | 284 | 148 |
| 22歳以上 | 530 | 235 |
| 合計 | 2482 | 1685 |
次に、杏林大学の合格者における再受験生の割合について紹介していきたいと思います。
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 18歳 | 39 | 20 |
| 19歳 | 95 | 67 |
| 20歳 | 49 | 34 |
| 21歳 | 26 | 11 |
| 22歳以上 | 13 | 2 |
| 合計 | 222 | 134 |
こちらが杏林大学の合格者の年齢別分布です。
ここでは便宜的に22歳以上の受験者を全員医学部再受験生とします。
表から、医学部再受験生の受験者数が男性530人、女性235人であるのに対し、合格者は男性13人、女性2人とかなりの少数でありました。
ですが、私立医学部の中で医学部再受験生に厳しい大学では再受験生の合格が0のこともあるため、杏林大学は医学部再受験生に普通~やや寛容といえるでしょう。
また、杏林大学の公式HPでは浪人による合否への影響はないと明言されていました。
医学部再受験生にとって杏林大学は比較的狙いやすいといえるのではないでしょうか。
再受験生に対する面接内容
医学部再受験生にとって面接でどのようなことを聞かれるのか?というのは気になりますよね。
インターネット上に杏林大学医学部合格者の方のインタビュー記事がいくつかあったのですが、どの記事でもそこまで厳しい面接が行われたという情報はありませんでした。
基本的には緩い雰囲気で面接が進むようですね。
医学部再受験生はやはり面接で現役生に差をつけたいので、予備校などで面接対策はしっかりやるようにしましょう。
特に医学部再受験生はなぜ再受験という手段を選んでまで医学部に入ったのか?という質問についてはしっかりと対策しておきましょう。
個性ある解答で自分をPRすることができれば面接官の記憶にも残りやすいですね。
医学部再受験合格に必要な勉強・対策方法
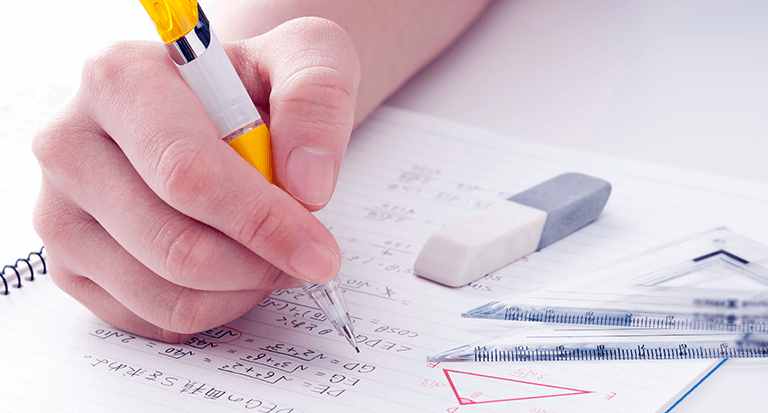
それではここから、医学部再受験生向けに杏林大学の入試で必要な勉強、対策方法について紹介していきたいと思います。
英語
杏林大学の英語の入試では文法読解、並び替え問題、会話の空欄補充、長文読解の4つの大問から構成されています。
全体的に難易度はそこまで高くはなく、解きやすい問題が多いです。
しかし、一部解くのに時間がかかるような問題もあるため、場合によっては問題を飛ばすという選択も必要になってきます。
医学部再受験生は焦りから全問解いておきたくなってしまいがちですが、合格のためには解くべき問題と後回しでいい問題を見極めるのも重要です。
初学者の医学部再受験生はまずは文法、単語から勉強しましょう。
近年共通テストで文法の出題がなくなってしまったので、国立志望の医学部再受験生はそれらをおろそかにしないようにしましょう。
数学
続いて数学です。杏林大学の入試は大問2つの構成となっており、全問穴埋め方式となっています。
分野ごとの垣根を超えたような融合問題が出題されているため、数学ⅠAからⅢまですべての分野をまんべんなく勉強することが合格への近道です。
初学者の医学部再受験生は教科書から勉強するようにしましょう。
標準レベルの入試問題ですが、いきなり過去問を解くのは難しいです。
まずは公式の理解から始め、ちょっとでもつまづいたらその分野は重点的に勉強するといいですね。
杏林大学の融合問題では苦手な分野を作ってしまうとかなり苦しくなってしまいます。
また、穴埋め方式なのでうまく誘導に乗ることが重要です。
国公立志望の医学部再受験生は記述式の対策がメインになってしまいがちなので、注意ですね。
うまく誘導に乗ることができないと模試で数学の成績が良い医学部受験生でも時間を浪費してしまいがちです。
理科科目
最後に理科です。
杏林大学の入試では物理、化学、生物から2科目を選択して受験することとなっています。
化学
化学の入試問題では理論化学、無機化学、有機化学からまんべんなく出題がされています。
問題レベル的にはそこまで高くはないので、基礎的な事項をしっかりと学習しておくようにしましょう。
医学部再受験生はまずは教科書レベルの事項をしっかりと理解し、標準レベルの問題集を完璧にしておくといいでしょう。
苦手な分野を作ってしまうと大問まるまる一つ落としかねないので注意です。
物理
物理の入試も全問マーク式となっており、大問4つの構成です。
力学、電磁気学、熱力学、波動といった分野がメインで出題されているようです。
全体的にレベルは医学部再受験生にとって標準レベルですが、一部見慣れないような問題設定をされていたりと解くのに時間がかかってしまうような出題もいくつか見られました。
医学部再受験生は標準レベルの問題集をまず完璧にしたら、杏林大学の過去問やほかの大学の過去問を演習するといいと思います。
マーク式なので、そちらにも慣れるいい練習になりますね。
生物
生物の入試もマーク式となっています。小問集合、遺伝、発生、感覚器といったように医学に関連する分野が頻出となっています。
他大を志望している医学部再受験生ですと生物の入試対策はどうしても広く浅くになってしまいがちです。
この分野には特に集中的に勉強しましょう。
グラフを読み取るような問題や与えられた条件から考察するような問題が多く見受けられ、かなり時間がかかると予想されます。
特に、杏林大学では理科が2科目合わせて100分とかなり短くなっており、医学部再受験生はスピーディーに問題を解くことができるようになるのが合格への近道です。
杏林大学の入試情報・選抜概要(2023)

続いて杏林大学の入試情報を紹介したいと思います。
一般選抜の募集人数は89名で、入試科目は杏林大学の公式情報で以下の表のようになっています。
なお、総合選抜は2023年から廃止されているので、注意して下さい。
| 科目 | 英語 | 数学 | 理科(2科目) |
|---|---|---|---|
| 一次試験 | 100 | 100 | 150 |
杏林大学の入試は一次試験と二次試験に分けて行われます。
一次試験では英語、数学、理科の3科目で学力試験が実施され、二次試験は小論文、面接が実施されます。
杏林大学は入試の面接では点数化はありません。
杏林大学では面接をどのように合否判定に利用しているかの情報はなかったのですが、対策はしっかりとしておきましょう。
小論文では自分の意見について論じる問題が出るようです。
医学部再受験生は現役生よりも人生経験が豊富な分よい文章を求められると思ってよいでしょう。
不安な医学部再受験生は日頃から新聞やニュースのトピックについて自分の意見を持つ習慣をつけるといいでしょう。
医学部再受験生は年齢という面で現役生に後れを取っています。
面接でどうして自分が医学部再受験をすることになったか、年下の同級生をうまくやっていけるかという質問はよく聞かれるので練習しておきましょう。
また、杏林大学では共通テスト利用での入試をすることも可能となっています。
そちらの配点は以下のようになっています。
| 科目 | 英語 | 数学 | 理科 |
|---|---|---|---|
| 共通テスト利用 | 200 | 200 | 200 |
こちらに加えて、二次試験では小論文と面接があるようです。
医学部再受験生にとって入試のチャンスが増えるというのはとても大事なことなので共通テストの点数が良ければ出願してみるのもいいかもしれません。
杏林大学の入試結果(2022年度)

次に杏林大学の2022年度の入試結果を紹介したいと思います。
先ほどは平成30年度の医学部再受験生に関するデータでしたが、こちらは医学部再受験生に限定したデータはありませんでした。
| 志願者 | 2649 |
|---|---|
| 1次受験者 | 2559 |
| 2次正規合格者 | 194 |
このようになっています。
最低点などは公開されていませんでした。
杏林大学の入試問題は全体的に標準的なものが多いため、比較的高いのではないかと予想されます。
医学部再受験生はスピーディーに問題を処理することを日頃から意識するといいでしょう。
まとめ
今回は杏林大学について、基礎的な情報に加えて医学部再受験生向けのおすすめ勉強法などについて紹介していきました。
杏林大学は医学部再受験生に対してもそこまで厳しい差別を行っておらず、問題も癖がないので比較的合格しやすい大学なのではないかと考えられます。
今回の情報を参考に、医学部再受験生はぜひ自身に合った受験校を選んでみてください。