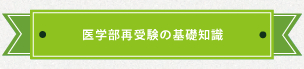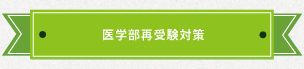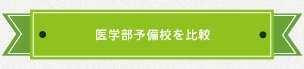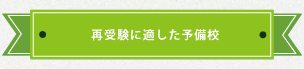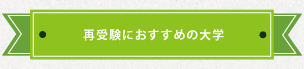医学部再受験で偏差値以外にも注意したいポイントを解説

大学受験の中でも最難関として知られる医学部受験。
そんな医学部医学科を日本全国82大学一覧にしても受験層が異なるのが事実で、それを表す指標の一つが偏差値です。
河合塾や駿台など大手予備校を含め、ネットでも医学部医学科の偏差値ランキングはよく目にするもの。
しかし、医学部受験において「偏差値」のみで受験校を選んではいけません。
この記事では、医学部受験における偏差値について、偏差値の基本から受験大学の選び方まで徹底解説していきます。
偏差値とは
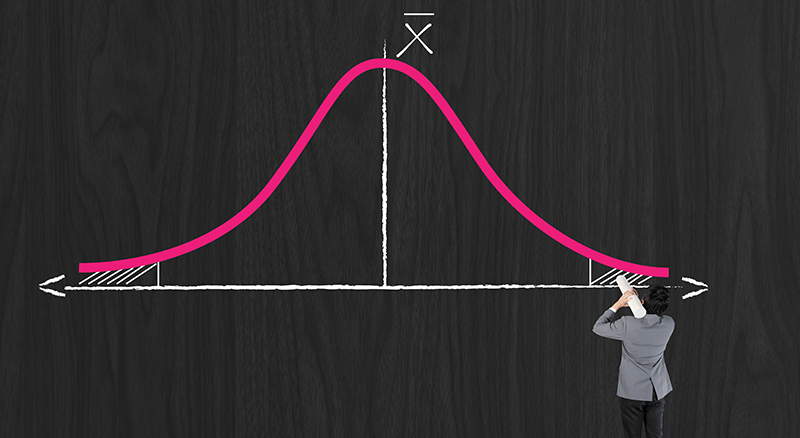
まずは偏差値について、簡単に解説します。
偏差値とは、模試などの試験を受けた集団の中で自分がどれくらいの位置にいるかを表す数値です。
平均点が偏差値50となるように計算し、そこを基準にどれくらい高い点数だったかを表したもので、平均点や順位と違って相対的に学力を測ることができます。
このように数値の算出に模試などの成績が使われているため、簡単に自分の偏差値とネットの偏差値を比較することは厳密には誤りともいえます。
自分が受けたこのある模試の中での比較、自分が所属している(成績データを提供している)予備校の偏差値との比較をすることで初めて、正しく偏差値の評価が可能になるのです。
駿台と河合塾で数値が違う問題
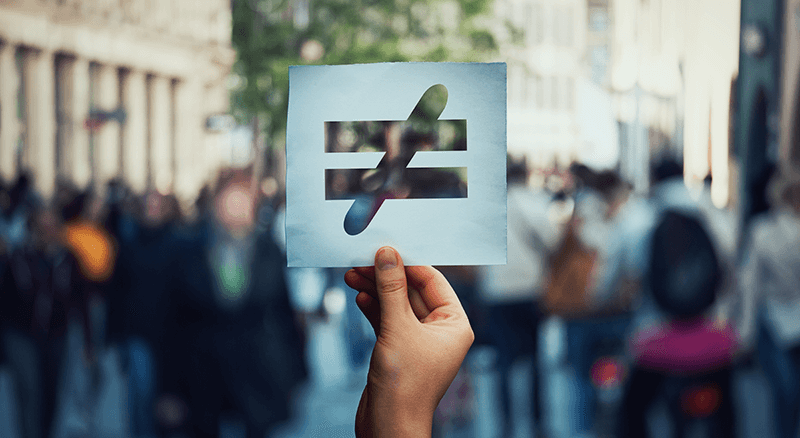
では実際に医学部医学科の偏差値を調べてみると、サイトや記事によって同じ大学でも数値が異なることが多々あります。
大手予備校である駿や河合塾、東進やベネッセなど一覧を見ても大きく差が見られます。(なお駿台はここ数年、偏差値データを一般公開していません)
もちろん、2020・2021・2022と見比べても年によって数値は異なります。
この違いは、「データソースの違い」と「表記する偏差値の定義の違い」によるものです。
データソースの違い
データソースとは、簡単には模試のこと。
偏差値を発表しているそれぞれの予備校は、いずれも独自の模試を定期的に行なっており、その成績と実際の合格者のデータを元に偏差値を算出しています。
全ての医学部受験生が同じ模試を受けるわけでもなく、中には医学部受験生の層が少ない模試もあり、そもそも模試自体の難易度も違います。
このようにデータの元が違うので、医学部医学科の偏差値は同じ大学でも違う数値になるのです。
表記の定義の違い
実は同じ「偏差値」と言っても、その定義は予備校などによって様々です。
| 河合塾 | 合格可能性50% |
|---|---|
| ベネッセ | 合格可能性60% |
| 駿台 (模試受験者に配布される資料) |
合格可能性80% |
| 東進 | 合格可能性80% |
このように、主要な予備校を比較しても、それぞれで表記の定義が異なることがわかります。
駿台や東進の医学部医学科の偏差値が高く、河合塾の医学部医学科の偏差値が低く出るのも納得です。
あくまで「ボーダー」の偏差値
いずれにしても、医学部受験に限らず「偏差値」と呼ばれているものは全て、あくまでボーダーの偏差値です。
仮に同じ模試をあなたが受けていて、その偏差値を超えていても、その大学の医学部医学科に落ちる可能性は20〜50%あるとも言えるし、超えていなくても医学部医学科に受かる可能性が無いと断定できるわけでは無いのです。
そもそもボーダーの話をしているだけなので、ある程度割り切って評価するべきです。
偏差値ランキングの確認方法

偏差値ランキングはあくまでボーダーであり、自分の模試などの偏差値とネット上の偏差値を比較してはいけないということを言いましたね。
しかし、ネット上で調べると出てくる偏差値ランキングはやはり気になりますし、参考にしたくなります。
偏差値ランキングを真に受けず、しかし、受験校を選ぶ際には絶対に指標の一つとしなくてはなりません。
これらを有効に活用するには、どのように見ると良いのでしょうか。
色んなサイトを見比べよう
まずは、河合塾や駿台の大手をはじめ、いくつかの偏差値ランキングを見比べましょう。
偏差値がサイトによって全然一致していなかったり、固定で上位にあったりと大学によって様々なことが分かるかと思います。
偏差値ランキングを見比べて様々な評価がされている大学は、例えばまだ新しく、入試の難易度が一定していなかったり、受験層が毎年変化していたりなどが考えられますよね。
逆に言うと、固定で偏差値が表されている大学は、その入試難易度が上下・さらに受験層が急激に変わる可能性は低いと考えられます。
繰り返しますが、偏差値というのは、必ずしも難易度とではありません。
立地がよいことで受験生があつまり、入試倍率が上がるから偏差値が高い、などということも十分に考えられるのです。
その大学の偏差値との数年の変化を見よう
注目するのは、数年間のその大学の偏差値の変化です。
偏差値が右肩下がりの大学は、単純に難易度が低くなったほかに、定員数が増えた等の何かしら合格しやすくなったポイントがあるはずです。
狙い目だと感じますが、それは医学部受験生全員も感じていること。
慎重に、過去問を見て自分との相性が良いか確認をしながら受験校を選びましょう。
他にも、去年の倍率が異常に低かった等も考えられます。
国公立大学では、共通テストを受験後に志望校を変える受験生がたくさんいるため、倍率が極端に高い・低いということがあり得ます。
歴史の深い旧帝大などでも、一時的に偏差値が下がる現象があります。
次の年に、狙い目だと受験生上位層が攻めてくる可能性があるため、注意しましょう。
真に受けないこと
そしてやはり、何度も言いますが、その数値をそのまま真に受けないことです。
自分の得意不得意との相性であったり、また、その年の様々な状況・変化によって偏差値は変わるものです。
あくまで指標として見て、上に書いたように、個々の大学の数年間の偏差値の変化に注目したり、様々なサイトを見比べたりしながら慎重に志望校を選ぶ際の指標の一つとしましょう。
参考:河合塾の国公立大学医学部偏差値ランキング【2022年度】
| 偏差値 | 大学名 |
|---|---|
| 72.5 | 東京大 |
| 京都大 | |
| 70.0 | 千葉大(後期) |
| 東京医科歯科大 | |
| 山梨大 | |
| 岐阜大(後期) | |
| 大阪大 | |
| 奈良県立医大(後期) | |
| 67.5 | 千葉大(前期) |
| 横浜市立大 | |
| 岡山大 | |
| 九州大 | |
| 宮崎大(後期) | |
| 65.0 | 旭川医科大(後期) |
| 北海道大 | |
| 東北大 | |
| 筑波大 | |
| 群馬大 | |
| 新潟大 | |
| 信州大 | |
| 金沢大 | |
| 福井大 | |
| 名古屋大 | |
| 名古屋市立大 | |
| 三重大(一般枠) | |
| 滋賀医科大 | |
| 京都府立医科大 | |
| 大阪公立大 | |
| 神戸大 | |
| 奈良県立医大(前期) | |
| 島根大 | |
| 広島大 | |
| 山口大 | |
| 愛媛大 | |
| 長崎大 | |
| 62.5 | 旭川医科大(前期) |
| 福島県立医大(一般枠) | |
| 富山大 | |
| 岐阜大(前期) | |
| 浜松医科大 | |
| 三重大(地域枠) | |
| 和歌山県立医科大 | |
| 鳥取大 | |
| 高知大 | |
| 佐賀大 | |
| 熊本大 | |
| 大分大(一般枠) | |
| 宮崎大(前期) | |
| 鹿児島大 | |
| 琉球大 | |
| 60.0 | 札幌医科大 |
| 秋田大 | |
| 福島県立医大(地域枠) | |
| 徳島大 | |
| 香川大 | |
| 大分大(地元枠) |
参考:河合塾の私立大学医学部偏差値ランキング【2022年度】
| 偏差値 | 大学名 |
|---|---|
| 72.5 | 慶應義塾大 |
| 順天堂大(B方式) | |
| 順天堂大(B方式以外) | |
| 東京慈恵会医科大 | |
| 日本医科大 | |
| 67.5 | 東北医科薬科大(地域枠) |
| 自治医科大 | |
| 昭和大 | |
| 東海大 | |
| 東京医科大 | |
| 東邦大 | |
| 日本大 | |
| 金沢医科大 | |
| 大阪医科薬科大 | |
| 関西医科大 | |
| 産業医科大 | |
| 防衛医科大学校 | |
| 65 | 東北医科薬科大(一般枠) |
| 国際医療福祉大 | |
| 杏林大 | |
| 帝京大 | |
| 愛知医科大 | |
| 藤田医科大 | |
| 近畿大 | |
| 久留米大 | |
| 福岡大 | |
| 62.5 | 岩手医科大(一般枠) |
| 獨協医科大 | |
| 埼玉医科大 | |
| 北里大 | |
| 東京女子医科大 | |
| 聖マリアンナ医科大 | |
| 兵庫医科大 | |
| 60 | 岩手医科大(地域枠C) |
| 川崎医科大 |
医学部入試では偏差値と難易度は違う
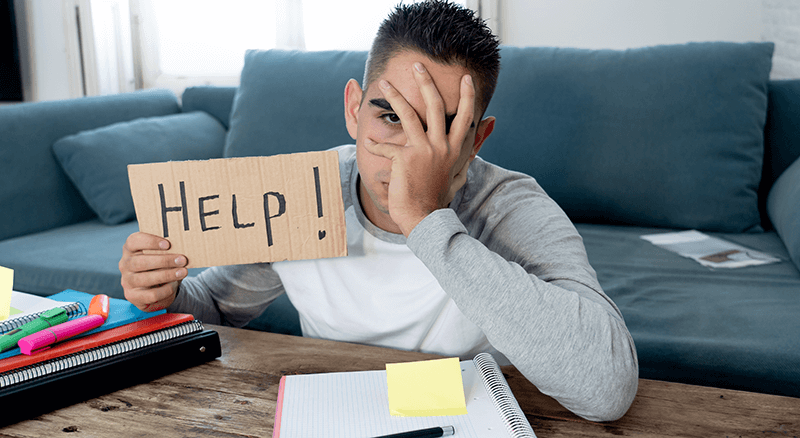
実際に、医学部入試では偏差値を使った評価をよく行いますが、最終的な受験校の決定など厳密に評価する場合には簡単には決められないものです。
例えば、同じ偏差値の医学部受験生であっても、現役か浪人か、出身高校や得意分野など多くの要因を加味するため、ここを受験するべき!とおすすめする最終判断は人によって結果が変わってくるのです。
相関はあるが「ムリ」という断定はできない
偏差値を使った評価には、一定の信頼性があるのは確か。
特に、「合格可能性80%」としている駿台や東進の偏差値を安定して超えられている場合には、その医学部医学科にはかなりの確率で合格できるでしょう。
しかし、逆の場合、すなわち駿台や東進の偏差値を一度も超えたことがない受験生であっても、「ムリ」とは決していえないのです。
仮に河合塾の模試を受験していて、そこで偏差値をクリアしているとしたら、合格可能性は50〜80%にあるとも言えてしまいます。
この可能性は医学部受験では十分すぎるほど。
では合格可能性50%を切っていたら無理?かというと無理ではありません。
理由は単純。その模試やその偏差値が、本番の試験ではないから。
結局のところ、最後の最後まで努力し、試験当日に十分な結果を出すことができれば、合格できるのです。
過去問対策がとても重要
偏差値はあくまで、参考。
自分の立ち位置の指標として利用し、あまり惑わされることなく、自身の勉強計画に沿って試験勉強を続けていけば大丈夫です。
特に医学部受験では、各大学の過去問の傾向と対策が命。特に私立では顕著です。また、国公立大学志望の場合は共通テストの得点率も必要に。
いずれにしても、過去問対策が重要になるため、多くの時間を割けるように計画を立てましょう。
難易度以外で重視したいポイント

医師国家試験の合格率
大学受験ではよくよく偏差値を第一に考えてしまいがちですが、特に医学部の場合、受験で合格することがゴールではありません。
あくまでも、医学部合格は医師になるためのスタート地点なのです。
仮に高い競争率をくぐり抜けて、高偏差値の医学部に入学できたとしても、医師国家試験に合格できずに医師になることができない可能性もあります。
そうした可能性を減らすためには、医師国家試験の合格率を見てみるとよいでしょう。
毎年、各大学は医師国家試験の合格率を発表しており、一覧化されていることがほとんど。
基本的には多くの大学で90%近くの合格率であることがほとんどですが、国公立・私立によらず85%を切る大学もあります。
合格率の低い大学ではカリキュラム的に国試対策を行っていない可能性もあるので要注意です。
進級の厳しさ
上の医師国家試験の合格率に近いですが、在学中の進級の厳しさも重視したいです。
もともと医学部は進級が厳しいとは言われていますが、その中でも特段厳しいところであれば何度も留年した結果、放校になってしまう学生もいます。
せっかくあこがれの医学部に合格したのに放校になってしまうのは嫌ですよね。
また私立医学部では多大な学費が余分にかかってしまいます。
こうした進級の厳しさなどは医学部予備校などでも共有されているので、必ずチェックしておきましょう。
卒後の進路
特に国公立大学において、昔は卒業大学の医局に入り、大学周辺の関連病院で勤務することが当たり前でした。
2022年現在はマッチング制度により自由に勤務地を選択することは可能ですが、結局のところ一種の就活のようなものであり、大学周辺の病院はかなりその大学出身者が多いという状況になっています。
もちろん外部地域からの学生も採用しますが、いわばコネがない学生扱いなので、どうしても働きたい地域がある場合はその周辺の大学を狙うといいでしょう。
立地・アクセス
普段の大学生活を送るうえで、なんだかんだ立地やアクセスは重要です。
学生の本文は学業であることは確実ですが、ただでさえ膨大な勉強を行う医学生にとって息抜きができる場所は必要です。
都会が好きな学生であればなるべく関東・関西の大学、もしくは電車ですぐに都会に出れる大学、田舎が好きな学生は地方の大学を視野に入れてみるといいでしょう。
また、あまりにも立地が悪いとバイトなどがしにくいというデメリットもあるので、それについても念頭に入れておきましょう。
おすすめの医学部を紹介

ここでは、偏差値が高すぎて到底入ることができないということはないにも関わらず、医学部としての実績が豊富な大学を紹介していきます。
筑波大学医学部
まず紹介するのは、茨城県に位置する国立大学の筑波大学です。
筑波大学は、文部科学省発表のデータによると、2022年医師国家試験合格率が99.3%で全医学部の中で2位となっており、医師国家試験合格率に置いて非常に優秀な成績を修めています。
医師国家試験の合格率は、全体を平均して90%程度となっていますから、この合格率99.3%がいかに驚異的な数字かわかるかと思います。
偏差値も河合塾のデータ上では65となっておりそこまで高いわけではありませんので、非常におすすめの大学です。
名古屋市立大学医学部
次に紹介するのは、愛知県に位置する公立大学の名古屋市立大学です。
医学部では、他学部に比べて大学で受ける必要のある試験の数が圧倒的に多く、その上試験の難易度も非常に高いということも相まって、6年間の医学部生活の中のどこかで留年してしまうという学生も多くいます。
せっかく苦労して医学部に入っても、留年して姉妹自分の経歴に傷がついたり、医師になるのが遅れてしまうことはなんとしても避けたいです。
そんな方におすすめなのは、名古屋市立大学です。
名古屋市立大学では、平成27年度入学生の医学部6年間ストレート進級率が99.0%となっています。
これは、学年が100人いるとすると99人が“一度も”留年を経験せずに六年間進級したとういことになりますから、非常に留年しにくい大学であると言えるでしょう。
東京女子医科大学医学部
最後に紹介するのは、東京女子医科大学です。
東京女子医科大学は、日本の中心である東京都新宿区に位置しており、医学部の中では随一の立地を誇ります。
新宿区に位置しているということから想像がつくと思いますが、非常に交通の便がよく、電車で通うにしても大学記載の最寄り駅が3つもあります。
また、路線バスで通うこともできるので、柔軟な通学方法が可能という点がメリットですね。
池袋や新宿といった大型の駅にもアクセスが良いため、学校終わり等に寄ってカフェで勉強したり、ショッピングやディナーを楽しむことで過酷な医学部生活の気分転換もできてしまいます。
これだけ好立地な医学部は早々ありません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
偏差値の考え方や、偏差値の味方、そして偏差値以外にも大学選びに置いて重要視するべきことについて見てきました。
この記事を読んできたみなさんならもうおわかりかもしれませんが、偏差値というのは一つの視点から見た尺度に過ぎません。
偏差値にこだわりすぎて自分の実力に見合っていない大学や、興味もない大学に挑戦するのはあまりおすすめできません。
また、今回示した偏差値以外にも重要視するべきことというのはあくまでも例に過ぎませんから、自分が何をしたくてどんな事ができる大学に行くのかということを受験前に一度じっくりと考えて、後悔のないような志望校選択をしてください。
そうすれば、自ずと受験に対するモチベーションも湧いてくるはずです。