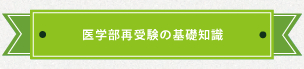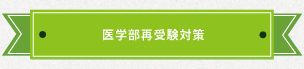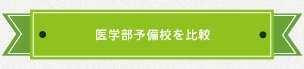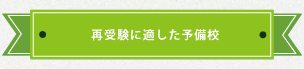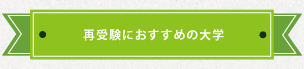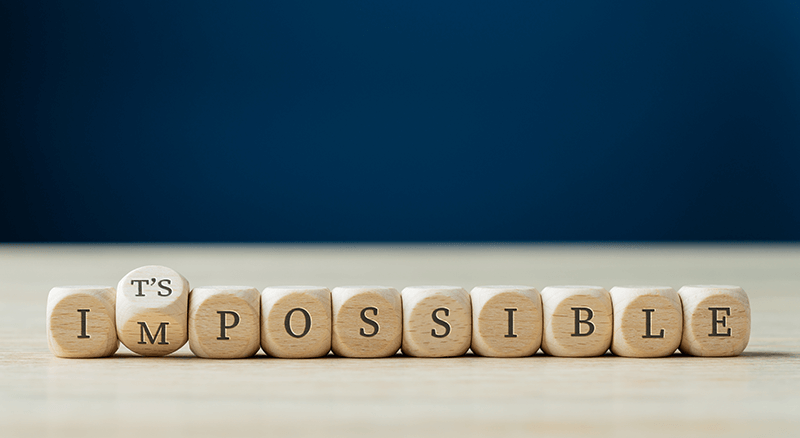
こんにちは、現役国立大学医学部生のむぎなべと言います。
大学受験の中でも最難関の難易度とされる医学部受験。
現役合格率は3割と謳われるほど多浪生が珍しい医学部では、一度他大学を卒業したり社会人経験を積んだ後で受験に挑む「医学部再受験」も全く珍しくありません。
しかしながら高校生同様、医学部再受験もその難易度は同じ、もしくはそれ以上の難易度とまで言われます。
この記事では、医学部再受験の実態に触れながら合格難易度やその可能性について解説していきます。
合格難易度は高いのか低いのか
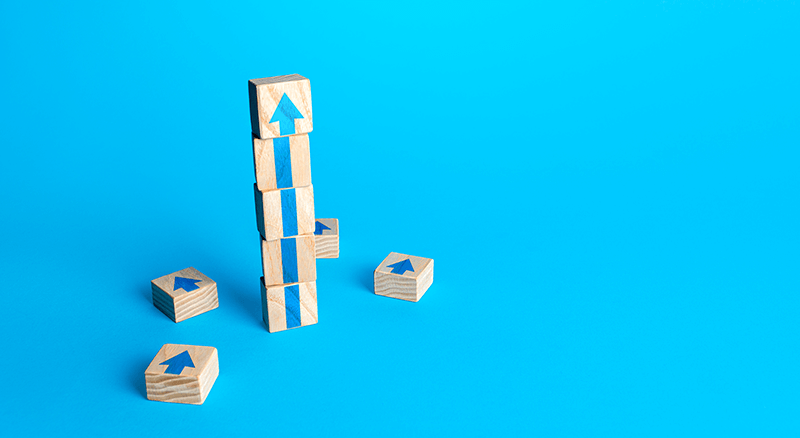
医学部再受験に限らず、ズバリ医学部受験自体、合格難易度は「高い」の一言。
では具体的に、どうして難易度が高いのかについて、医学部再受験の実態も踏まえながら解説していきます。
医学部全体の偏差値の高さ
そもそも医学部受験自体、かなりの難易度。
医学部受験でもよく利用される偏差値を使って例にあげると、医学部の偏差値は65〜75がほとんど。
試験によっては80を超える大学もあるほどです。
この偏差値の数字から、その集団の上位何%を指しているのかがわかるのですが、それが以下の表の通り。
| 偏差値 | その集団での最上位からの割合 |
|---|---|
| 80 | 0.13% |
| 75 | 0.62% |
| 70 | 2.28% |
| 65 | 6.68% |
つまり、偏差値70の医学部というと、端的に言えば、全大学受験生の上位2%に入らないと合格できないというほどの難易度。
そうでなくても平均的な医学部の偏差値65であっても、全大学受験生の上位6%に入る学力を身に付けなければ合格できない難易度なのです。
このように、医学部再受験は「再受験」ということを度外視しても、そもそもの「医学部受験」というだけでかなりトップレベルの難易度であることを押さえる必要があります。
その上で、医学部再受験の場合は後述する年齢などそのほかの条件のために、医学部再受験という枠だけで捉えれば、一般の医受験生よりも倍率が高い可能性が十分に有りえ、合格難易度は一層高いと言わざるを得ません。
年齢に「寛容」な大学、「厳しい」大学
これだけ難易度の高い医学部入試ですが、昔からその不透明さには疑問の声が上がっていた事実があり、2018年にはついに事件発覚、医学部入試差別問題としてニュースでも大々的に報じられました。
この一連の騒動では、某大学を発端として文科省が調査に乗り出したところ、複数の大学で性別や年齢が不利になるような得点操作などが行われ、合格できた受験生が不合格にさせられていたなどショッキングな事実が明るみになりました。
この医学部入試差別問題については未だに多くの議論が残っていますがここでは割愛し、学ぶべきポイントをお伝えします。
それは、実際のところ、年齢に対して寛容な大学と厳しい大学が事実分かれているということ。
しかもこれは、何年も昔からわかっている既知の事実。
例えば島根大学は毎年25歳以上の合格者が15〜20名以上いてかなり寛容な大学であるのに対し、ある大学では多い年で1人、そもそも3浪以上の合格者が皆無という大学も。
医学部再受験においては、偏差値などの学力も難易度に関わってきますが、受験校選びの段階で、どの大学を選択するかだけで合格難易度に大きく違いが生まれるのが事実なのです。
そのため、医学部再受験を考えるのであれば、年齢に厳しい大学を避け、なるべく寛容な大学を受験するのが肝心です。
ライバルは同志ではない
ここまでのお話で、医学部受験自体の合難易度が高い上に、医学部再受験の場合は年齢でフィルターをかけられてしまうために難易度がより高くなっていることをお伝えしました。
これはつまり、ライバルは同志である医学部再受験だということに。
ですが、医学部再受験の仲間は早々出会えるものではありません。それぞれが強い意志を持って挑んでいるだけに、ライバルとして敵対視するのは野暮。
むしろ、仮に同じ大学を志望しているとしても、お互いに励まし合い、双方の合格を祈るぐらいの二人三脚で挑戦するべきです。
後述しますが、医学部再受験で最大のライバルは自分自身です。さまざまな思い・プレッシャー、慣れないスケジュールの中で、いかにパフォーマンスを維持しながら試験勉強を乗り切れるか。それこそが合格難易度に最も関わっている要素なのかもしれません。
医学部再受験の実態に触れる
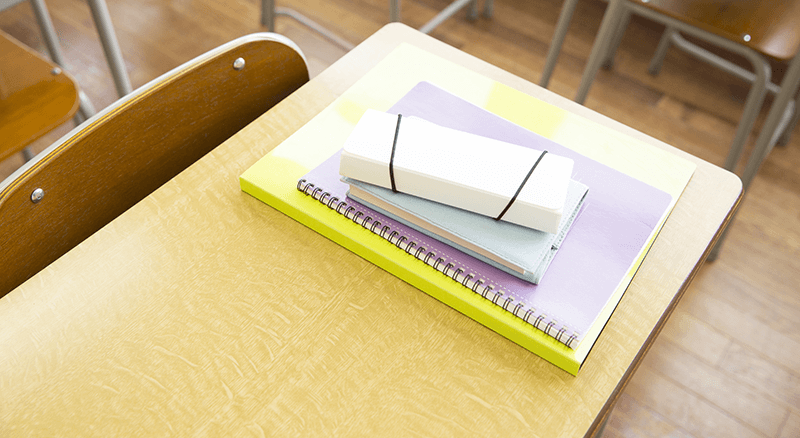
ここからは医学部再受験と難易度について、その実態をより深く見ていきましょう。
国公立と私立の違い
医学部再受験と一概に言っても、国公立大学と私立大学では事情が異なります。
国公立大学の場合、共通テスト(旧センター試験)での高得点が必要で「85%以上はほぼ必須」とまで言われる難易度の高さ。しかも共通テストでは理系科目のみならず国語や社会といった文系科目も課されるため、難易度の高い二次試験の勉強のみならず幅広い分野を学ぶ必要があります。面接は全大学で必須、小論文もほとんどの大学で課せられます。
一方の私立大学の場合、ほとんどの大学が英語・数学・理科2科目に加えて面接・小論文で合格判定をします。確かに試験科目数は少ないため難易度は比較的下がる大学が多いものの、出願時点から受験料が国公立大学の2倍(国公立大学3万円、私立大学平均6万円)であり、周知の通り6年間総額の学費も国公立大学の数倍〜10倍以上と、その学費がネックとなるものです。
また、医学部再受験の年齢に寛容な大学の数についても、国公立大学の方が多く、私立大学の場合は全体の大学数に対しては寛容とされる大学が少ないのが事実。
医学部再受験生と一言に言っても、年齢や性別、学力など個人個人で背景が違うためその合格難易度は一概に言えないのが事実ですが、国公立大学は経済的な理由で、私立大学は学力的な理由で選択する人が多い印象にあります。
実際に何人が合格しているのか
実は、各大学の毎年の入学者データから、実際に医学部再受験生がどれぐらい 合格しているのか、ある程度読み解くことができます。
医学部再受験の多くは22歳以上、 もしくは25歳以上という枠になります。
ここ数年のデータを国公立大学・私立大学と合わせて見てみると、22歳以上の入学者数は多い大学で20数人、少ない大学で2-3人。25歳以上になると多くても15-20人、少なければ0人の大学も実は少なくありません。
全体の人数としては、25歳以上で見ると毎年数百人前後が医学部再受験に合格・入学していることがわかります。
この数字を多いと捉えるか少ないと捉えるか。
医学部再受験に限らず、医学部全体としては一般試験前期日程で毎年約4.1倍の倍率であるため、仮にこれが医学部再受験でも同様と考えると、毎年1000〜2000人ほどの医学部再受験生が挑戦していると考えることができます。
ただし、医学部再受験は難易度が高く、実際にはもっと多くの人が挑んでは挫折しているような、そんな印象を受けます。
なぜ編入試験を選択する人が少ない?
医学部再受験生の中には他大学を卒業し学士を修得している人も多く、その場合は医学部に編入試験で入学するという選択肢もあります。
編入試験は試験科目に生命科学など大学レベルの知識が問われるほか、面接が20-30分と比重が重く、年齢はほとんど気にされず、学力と面接でのアピール力で勝負をすることができるのが特徴。途中学年からの編入のため、大学生活にかかる費用を減らすメリットもあります。
しかし、編入試験は定員も少なく、問われる知識量が高い、さらには流通している情報量が少なすぎるなどの理由で、あまり選択されることがありません。難易度もそれだけ医学部再受験以上に難しいものです。現に、ときに倍率が50倍なんてことも。
実際のところ、編入試験をおすすめできる医学部再受験生は特定の人のみなので、医学部再受験生の中で編入試験を選択する人が少ないのも納得のいく事実なのです。
医学部再受験は勇気ある決断

本気で医者を目指す医学生の割合
突然ですが、現役医学部生の中で本気で医師になりたくて医学部に来た人はどれぐらいいると思いますか。
あるアンケートでは、「医者になることを以前から考えていた」と答えた人は全体の38%で、「学力が届いたから医学部に入った」という人が24%という結果に。
そのほか、「なんとなく」や「親・先生・友人に勧められたから」といった回答が設けられていました。
医学部再受験生は、その多くが医師になることに強い意志を持っているもの。
このアンケートのような現状の中、医学部再受験を決意するというのは大いに尊敬に値する行為とも言えるのです。
難易度は想像以上と思った方がいい
しかしながら、毎年一定数の医学部再受験生が挫折・失敗し医学部再受験そのものを諦めてしまいます。
これには様々な原因がありますが、大きなものとして「難易度」の認識のずれがあります。
医学部受験そのものがかなりの高難易度。
その上、自身の大学受験からかなりのブランクを経て挑む訳ですから、受験勉強に苦難が生じるのは当然とも言えます。
自信が想像している以上に、医学部再受験は難易度が高いと思うべきかもしれません。
結果次第でライフプランに影響が出ることも
そんな医学部再受験ですが、見事合格し成功した場合には人生が大きく変わることは間違いありません。
それだけの難易度の試験をクリアしたのであれば、大学入学後の医学部の勉強漬けの日々も決して苦ではなく、国家試験もさほど苦労しないはずです。
現に、医学部再受験生は留年率も低く、国家試験の合格率も高い傾向にあります。
医師になれば今より年収が大きく変わり、社会的地位や信頼も獲得できます。
医学部再受験を制することができれば、自身のライフプランは大きく変わるでしょう。
医学部再受験を成功させる方法

最後に、難易度の高い医学部再受験を成功、それも最短で合格に導くために重要となるポイントについて、簡単にご紹介します。
受験は情報戦
医学部再受験に関わらず、医学部受験ないし大学受験全体に言えるのがこの格言。
特に医学部再受験の場合は、
- 年齢に寛容な大学はどこか
- 自身の特性と相性の良い大学はどこか
- 面接ではどんなことが聞かれるか
このような情報が受験校選び、志望校対策に必要不可欠です。
もちろん自分自身でネットや書籍を駆使して調べることも可能ですが、勉強しながら満足のいく情報収集は難しいもの。
そこで筆者がおすすめするのが医学部予備校などの利用です。もちろん河合塾などの大手予備校もOK。
ぜひプロの力に頼って、効率よく難易度の高いこの医学部再受験を攻略していきましょう。
勉強よりも問題にあるものとは
医学部再受験は難易度が高いことは再三お伝えしてきましたが、それは何も「勉強」だけを指している訳ではありません。
再受験の場合、多くの人が仕事や家庭にある程度の犠牲を払いながら受験勉強をするもの。しかし、思い立ってから1年目で合格する人はかなりのレアケース。2年、長い人では4年以上かけて成功を掴む人もいます。
そんな中、最大のライバルは自分自身。
犠牲にしているものへの責任感や周囲からのプレッシャー、慣れない受験勉強の日々に、精神的に挫折する人は決して珍しくありません。
そう、勉強の難易度よりもモチベーションの維持の方が課題と言えるのです。
目標を明確に
医学部再受験に限らず、難易度の高い医学部受験全般に共通して言えることですが、モチベーションの維持方法は人それぞれ。
しかし往々にして適応するアドバイスは「目標設定」と「適切な評価」です。
月単位の大目標、週単位の中目標、日単位の小目標を設定し、毎度「適切な」評価を行うことがおすすめです。
目標は達成できる難易度にとどめ、評価で常に満足感を得るのも悪くありません。
また、評価には適宜、模試や予備校のチューターなどプロによるものも挟むことでより正確に自己分析ができるようになります。
ただがむしゃらに突き進むのではなく、道をしっかり確認しながら、着実に一歩一歩進めていく、それがモチベーションの維持に最も重要です。
なお、難易度の高い医学部再受験においては「諦める基準」の設定も重要です。
何年やってダメなら諦める、共通テストで何点なら諦める、など設定内容は個人それぞれですが、強い意志でこれを決定しておくべき。
こうすることで背水の陣を感じて熱が入るものですし、決めておかないといつまでも中途半端にズルズルと続けてしまう危険があります。
常に成功のその先を描く
前述したように、これだけ難易度の高い医学部再受験を決意したということは相当の尊敬に値するもの。その熱い意志は成功に繋がるべきです。
難易度の高い医学部再受験のモチベーション維持には、その熱い思いを何度も想起することも欠かせません。
医学部に入学したら学べること、卒業して医師となってからやれること、それを想起し自身の思いを重ね、ぜひ1日1日の勉強に精を出してください。
まとめ〜大変だが価値ある挑戦〜
ここまで、医学部再受験の難易度について、その実態に触れながら解説してきました。
確かに高難易度の医学部再受験ですが、決して無謀な挑戦ではありません。
年齢に寛容な大学を選ぶ、そのために情報収集を欠かさない、面接対策を徹底するなど、ポイントを押さえれば合格可能性は決してゼロではありません。
しかし一方で、失敗する人も少なくないのが事実。ただしそれは、単純にい難易度が高いからではなく、難易度以外の理由があるものです。
医学部再受験という難易度の高い決断はなかなかできないものだけに、その決断に敬意とエールを捧げます。
ぜひ、最後まで諦めずに合格を勝ち取ってください。