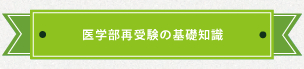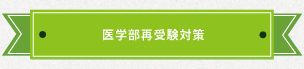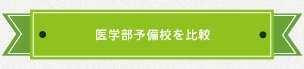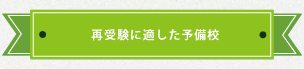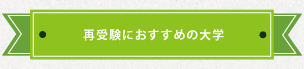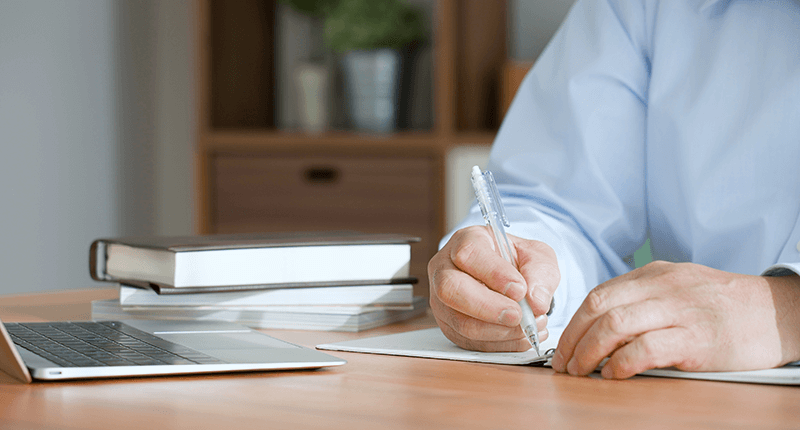
医学部受験ブームがますます熱気を増してきていますが、それは現役生や浪人生だけでなく、社会人経験を経て医学部再受験合格を狙う医学部再受験生にも当てはまります。
最近であれば40代から医学部再受験をはじめ、45歳で大阪医科薬科大学に無事に合格した、元予備校講師かつYoutuberである「ビリおじ」が有名ですね。
このように医学部再受験界隈の中には30代以上の医学部再受験生もいますが、こういった学生は医学部再受験だけでなく医学部に合格してから自分が馴染めるかどうかで悩むことも多いです。
30代以上といえばそろそろ「おじさん」「おばさん」とコメントされる頃ですが、実際のところ彼らの末路はどうなのでしょうか?
そもそも30代以上の医学部再受験はいばらの道

医者は高度な内容の医学を頭に入れ、患者さんごとにあった治療を迅速に決める必要があります。
そのため医学部では記憶力・理解力・判断力の高い学生を求めており、合格するには全科目で偏差値60を超えていく必要があります。
また、医学部は定員が100名程度と狭き門であり、そもそもの合格難易度が極めて高い部類に入ります。
そんな中、30代以上の医学部再受験生は年齢的に記憶力や理解力・判断力は低下しており、また問題を解くスピードも遅くなっています。
こうした年齢的なディスアドバンテージが医学部再受験生にはあるため、はっきりいって30代以上での医学部再受験はいばらの道です。
また、2018年に東京医科大学を皮切りに発覚した医学部不正入試事件の記事の記憶は新しいと思いますが、この事件後の調査の結果、複数の大学で高齢の医学部再受験生に対して減点や不当な措置をとっていたことが判明しました。
すなわち、医学部再受験生にとっては単なる学力だけの壁ではなく、こうした医学部再受験生に対する不寛容も乗り越える必要があるためより厳しいのです。
2022年現在は文部科学省が目を光らせているため医学部再受験生に対する不正は行われないとみて大丈夫ですが、いつから再び不正を行うかはわからないので注意が必要です。
医学部再受験生は医学部予備校に頼るべき!

これは年代に関係なく医学部再受験生に言えることなのですが、医学部再受験生が医学部に合格するための最短ルートとしてよく挙げられるのが医学部予備校です。
医学部予備校は大手予備校と異なり、医学部受験のみを扱う予備校のことです。
講師はみな医学部受験を専門にしており、近年の医学部受験の動向から踏まえた指導を行い、さらには自分との相性などから受験校の選定や編入試験の対策なども手伝ってくれます。
基本的に医学部予備校は一対一の個別指導もしくは少人数制なので、生徒と講師の距離が近く、講師は生徒の弱点をすぐに見つけ、弱点克服のための指導をしてくれます。
医学部再受験生の場合、いかに効率よく勉強するかが重要なので、このように弱点に特化した対策をとってくれることが医学部予備校をオススメする理由です。
実際医学部再受験生のうち、無事合格を収めた人の多くは医学部予備校に通っていたので、早々に頼るべきでしょう。
30代の医学部再受験生の医学部合格後の末路

30代以上で医学部再受験を無事突破したのはいいものの、実際に現役生や若い浪人生と混じって医学部内にいるのは想像できますか?
おそらく多くの方は、「自分はもしかしたら医学部内で浮いてしまうかも」「おじさんだし友達になってもらえないかも」なんて思う方もきっと多いはずです。
しかし安心してほしいのですが、実際の医学部内では特に30代以上だからといって馴染めないなんてことは決してありません。
まず大前提として、医学部は現役合格よりも、浪人生の割合の方が多いです。
したがって、もともと年齢のずれ・歪みはあるため、そもそも医学部生の多くは年齢差があることに対して特に気にしていません。
もちろん入学して最初の頃は、自己紹介などして30代以上!?となる反応が多いかもしれませんが、それも数か月もしたら誰も気にせず「同期」として扱うことが普通です。
なので現在医学部合格後の末路に悩んでいる30代以上の医学部再受験生は安心してください。
医学部での生活はどんな感じかを解説

そもそも医学部ではどのような生活を送るのでしょうか?
1年生
1年生の頃はまだ大学になれておらず、忙しい毎日です。
入学してすぐはお互いのことを知らず、医学部再受験生とか関係なくまだみんな打ち解けていないころです。
そのため大学側でオリエンテーションとして自己紹介や懇親会を行うこともあります。
新歓を経て部活に入るとおのずと同じ部活の中まで行動することが増えていく印象です。
勉強の方も経済学や線形代数学などの一般教養などがあったりして、一般的な大学生の雰囲気が味わえます。
大学によっては早い段階から解剖学や生理学などの医学系科目が始まります。
2年生
大学生活にも慣れてきて、多くの大学で解剖学や生理学を学習し始めるころです。
特に解剖学は最も医学部に入った実感が湧くと思いますし、これを通じて自分が医者になるんだという再確認ができます。
しかしながらこうした基礎医学の科目は、試験が難しいことが多く大学にもよりますがこの2年生で留年することが多いので要注意です。
下宿生であればようやく一人暮らしにも慣れてきて、忙しいながらも楽しい生活が送れるでしょう。
3年生
内科学や整形外科学、産婦人科学、小児科学といったいわゆる臨床医学がスタートする頃です。
病院をイメージしてもらえればいいのですが、とにかくたくさんの科があり、当然テストもたくさんあります。
しかし臨床医学はやっていて楽しいものが多いので、意外と留年するほどの厳しい代ではない印象です。
部活にもよりますが3年生くらいから幹部代と呼ばれ、ある程度部活を仕切る学年になるため、部活の忙しさもなかなかハードになっていきます。
4年生
4年生なるとCBTとOSCEと呼ばれる、医学部生活の中でも重要な2つのテストが待ち構えています。
CBTとはこれまで学習した基礎医学、臨床医学に加えて公衆衛生などの社会医学といった全範囲から網羅的に出題されるテストです。
これに合格しないとポリクリと呼ばれる病院実習に参加することができず留年となってしまいます。
またOSCEとは実際に模擬診察のようなことをして、採血の方法や縫合など実技的な側面でちゃんと自分で技術を磨いているかのテストです。
正直OSCEはあくまで模擬なので、そこまで厳しくはありませんがこれも落としたら留年となってしまいます。
4年生は多くの大学で部活の幹部を担当している代なので、勉強も部活も忙しくなかなかしんどい学年です。
5年生
5年生はもうポリクリがはじまっていて、いわゆるstudent doctorとして病棟内での実習で拘束時間が長いです。
座学ではなくなりますが、実習前に予習が必要だったり、自分が見た症例をパワーポイントでまとめて毎週報告したりと、思ったよりも忙しいです。
ポリクリはだいたい班行動なので、同じ班になった学生とは仲良くなりやすいです。
ポリクリの後に飲みに行ったりも多く、一般的な会社員のような生活に近いかもしれません。
6年生
6年生は当然ながら医師国家試験が控えており、4年生ぶりに猛勉強する必要があります。
しかしポリクリはだいたい夏くらいまで継続してあり、意外と勉強時間はとれないですし、また学生最後の夏ということで遊びに行ってしまいがちです。
さらに6年生の場合卒業後の研修先を決めるために、病院見学を適宜行くことになり、かなり忙しいといえます。
いくら医師国家試験が合格率90%といっても、万が一不合格になったらと考えてしまうので、プレッシャーも感じやすくさながら医学部受験のような緊張度が高まります。
30代以上で入学してもちゃんと医者をやれるか?

30代以上の医学部再受験生が医学部に入学した場合、どんなに早くてもその医学部再受験生が医者になるのは36歳からとなります。
現役で入学してきた学生は24歳から医者になれるわけですが、その体力のある現役生たちですら研修期間中の過酷な労働につらいとコメントしています。
30代以上で入学した医学部再受験生は無事に医者として勤められるのでしょうか?
実際、外科や産婦人科などは体力勝負
外科というとオペ室でメスを握り、腹腔内の臓器や脳に対して手術をすることで治療する科となるわけですが、実際のところ体力勝負となります。
ずっと立ちっぱなしで手術をし、かつ長時間に及ぶ手術も多いので、現役生でも体力がないものは諦めるといった現状もあるので、確かに医学部再受験生にはしんどいかもしれません。
その他にも産婦人科や麻酔科は夜中に緊急で呼び出されることも多く、やはり体力がないと医学部再受験生には厳しそうです。
しかし、逆に言えば内科系や人気マイナー科と呼ばれる眼科・耳鼻科・放射線科などは比較的緊急を要する手術が少ないことから、医学部再受験生にはおすすめの科といえます。
研究の道もある
医学部再受験生の中には、直接臨床の現場で患者を助けるのではなく、研究の道に進む人も多い印象があります。
医学部再受験生の多くはビジネス・社会人経験もありデスクワークになれていて、また医学部再受験で培った忍耐力から、研究者に向いている人が多く、中には在学中に論文の著者になる人もいます。
研究医の場合、当然臨床のような激務ではないため体力的にも戦えるフィールドであるので、おすすめできます。
30歳以上のおじさんが馴染むおすすめの方法

ここでは30代以上の医学部再受験生が気になる、医学部内で馴染む方法について書いていこうと思います。
しかし、大前提としてあまり気にしなくても気づいたら馴染めている、というん尾は念頭においてください。
友達をどう作るか
先に述べた通り、1年生の頃はみんなお互いを知らないので、ここがチャンスです。
おそらくオリエンテーションがあり、自己紹介をすることになりますがそこで医学部再受験というとみんなびっくりしたコメントをすると思います。
それはある意味チャンスであり、ほかの人よりもインパクトが強いので話しかけてもらいやすいことになりますがここで注意なのが「絶対に悪目立ちしないこと」です。
変に奇をてらったことをしたり、軽いノリをみせるのは失敗であり、柔和な雰囲気を保つと仲良くなりやすいでしょう。
自分のことをあまり医学部再受験生だ、とかおじさんだからなどと卑下するのも、相手からしたら反応に困ってしまうのでやめておいた方が無難です。
また、友達作りで大事なのが部活です。
医学部内での行動は部活が同じもの同士で動きがちなので、絶対に何かしら部活は入っておくべきです。
部活に入ることで先輩からも認知してもらい、交流も増えますし、試験の過去問や勉強方法のコツ、実習の情報なども教えてもらえるので一石二鳥です。
勉強は大丈夫?
医学部再受験を無事成功させてからも、今度は医学部での膨大な勉強が待っています。
医学部での勉強は、数学や物理といった計算ではなく、単純にどれだけ暗記できるかの戦いなので、早くからの試験勉強が医学部再受験生には必要です。
また、医学部での勉強はよく「情報戦」と呼ばれていますが、それは単に教科書で勉強するよりも、いかに過去問を集めて傾向を読み、また授業中に教授が強調していたことを聞き留めていたかが大事なのです。
そのためやはり友達が多いとそれだけ情報量も増えるので、試験勉強がしやすくなります。
まずは自分の医学部再受験を成功させることに集中
このように医学部に入学してからは、よほど奇をてらったことさえしなければだいたいは馴染めるものです。
医学部での生活は、受験のような個人戦とは異なり全員で試験に受かろうというムードもあるため、よほどのことがない限りは過去問や解説ももらえるでしょうし、医学部再受験生だからと変な扱いをされることもないでしょう。
となると医学部再受験生にとって一番の課題は、やはり医学部再受験をどうクリアしていくかとなります。
医学部再受験では年齢的な衰えによるしんどさだけでなく、面接での医学部再受験生に対する圧迫的な質問や、医療に対する姿勢の懐疑的な確認にも対応する必要があります。
こうした試験の対策は独学の勉強でやっていてはらちがあきません。
医学部再受験をもくろむ学生は、できるだけ早い段階から医学部予備校を活用して勉強するとよいでしょう。
そして医学部合格後の末路に悩むのではなく、少しでも医学部再受験の成功率をを上げることに尽力しましょう。