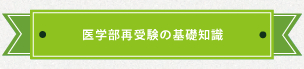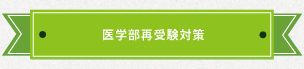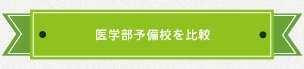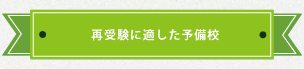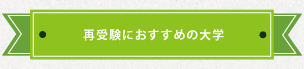医学部再受験生は時間もお金もない人が多いことから、参考書を買って手軽に勉強が始められる独学を選びがち。
しかし、参考書は正しい使い方があり、誤った勉強法では医学部再受験を成功させることはできません。
今回はお進めの参考書を科目別に紹介しながら、正しい使い方を紹介していきます。
学力に見合った参考書選びが重要
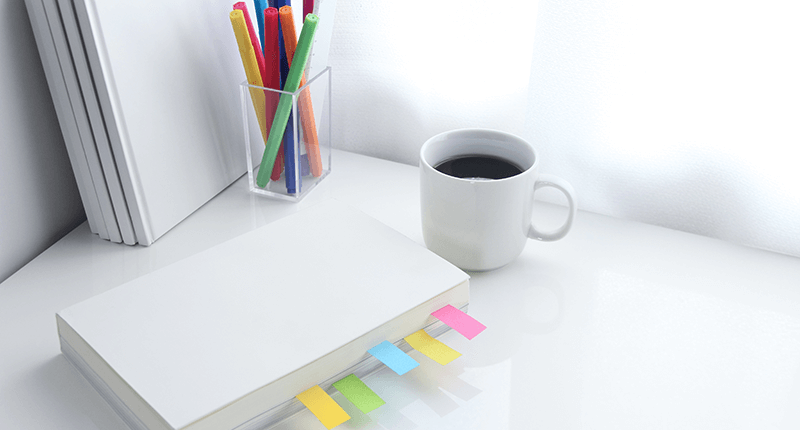
医学部再受験生の中には独学を選ぶ人もいますが、難関医学部入試をできるだけ早く突破したいのであれば医学部予備校に通うことをおすすめします。
それでも経済的な理由で独学を選択せざるを得ない医学部再受験生もいると思いますが、その場合は参考書選びが重要になってきます。
医学部再受験生の学力が様々で、知識ゼロからの人もあれば科目によってはある程度の学力を有している人もいます。
医学部を目指すのだからと背伸びをして難しい参考書に手を付けると効率性が悪くなると同時に、なかなか進まずモチベーション的にも苦しい思いをしてしまいます。
まず医学部再受験生は、自分の学力に合った参考書を選び、徐々にステップアップしていくと良いでしょう。
参考書は多くの出版社から販売されていますが、数学および理科については河合出版の参考書が医学部再受験生からの評判が良いです。
医学部再受験生におすすめの参考書まとめ
ここでは医学部再受験生におすすめの参考書をご紹介しています。
医学部再受験生の最大の特徴は、「ブランク」です。
すでに一度は高校で学習した内容とはいえ、他大学の卒業や企業就職など、社会経験を積んできた医学部再受験生にとって、医学部再受験は「再勉強」の過程とも言えます。
受験勉強において最も大切なことは『効率』です。
それは医学部再受験にとっても同じ。
既習範囲とはいえ、忘れている知識は意外にも多いのです。
さらに、近年は学習指導要項の変更もあり、「習っていた分野が、実はもう出題されない」「習っていない分野が出題範囲に含まれている」ということは珍しくありません。
これは特に数学などの理系科目に多いため、医学部再受験では必ず確認が必要です。
ここでは、
序盤:基本的な知識の確認(インプット)
中盤:中〜やや難の問題演習(アウトプット)
終盤:医学部再受験に向けて応用力を養う(過去問演習と併用)
の3つのフェーズに分けて、おすすめの参考書をご紹介します。
英語
英語の学習は以下の3つで構成されます。
- 単語(+熟語)
- 文法
- 長文
ここでは、各分野の学習でおすすめの参考書をご紹介します。
まずは英単語。最も重要なのは、「確実に覚える」ことです。
序盤〜中盤では『DUO 3.0』を完璧にしましょう。
最も生の英語に近い単語帳として、各種英語資格試験の対策として評判の高い参考書です。
熟語も学習することができ、類義語の使い分けや使用シーンの解説など、非常に優れた参考書です。
この単語帳のみをマスターすれば、医学部再受験の英単語は怖いもの知らずです。
終盤では、専門的な単語の補充を行いましょう。
模試など問題演習の過程で覚えていく方法で構いませんが、余裕のある人は『話題別英単語リンガメタリカ 改訂版』を。
医療系を含め様々な分野について語彙が掲載されているので、この参考書をマスターすれば、どんな分野の長文問題でもかなりスラスラ読めるようになります。
 |
|
新品価格 |
続いては文法の参考書。
序盤は、『総合英語Evergreen』でセンター基礎から発展まで十分に文法を勉強しましょう。
この参考書は専用アプリもあり、解説動画もついているため、特に医学部再受験生に最適です。
中盤では、『Next Stage』で問題演習量を稼ぎましょう。
かなり問題数が多い参考書ですが、英語を改めて勉強する医学部再受験生には必要十分量です。反復演習ができれば、なお良しですね。
終盤は長文読解に集中したいため、わざわざ高難易度の文法問題を求めて参考書を買う必要はありませんが、余裕のある医学部再受験生は『基礎英文問題精構』を活用してください。
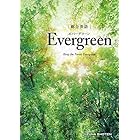 |
|
新品価格 |
最後に長文読解の参考書。
序盤は単語や文法の勉強に専念し、中盤〜終盤は、『やっておきたい英語長文シリーズ』を利用しましょう。
この参考書は300(非常に易)→500→700まで勉強すれば合格には十分です。
過去問演習の方が大事ですから、非常に難な1200は、余裕がある医学部再受験生のみ挑戦しましょう。
また、このシリーズは近年改訂がされていないので、中古購入をお勧めします。
英語については、すでに得意としている医学部再受験生も多いはず。
得意な方は、ぜひ他の教科に力を入れてください。
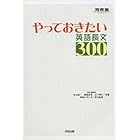 |
|
新品価格 |
数学
数学は、特にここ数年で大きく内容が変更されています。
医学部再受験生は、出題範囲を把握するためにも、必ず基礎から勉強し直す必要があります。
序盤は、『理解しやすい数学』もしくは『青チャート』で網羅的に勉強しましょう。
どちらの参考書も医学部再受験に必要な基礎力を得るのに十分な内容と問題量ですので、デザインなど自身の好みで選んでください。
ちなみに、数研出版の青チャートと黄チャートでよく悩まれますが、終盤まで活用できるのは青、黄は秋には手放すべき存在、という違いがあります。
 |
|
新品価格 |
 |
|
新品価格 |
中盤は、『合格る計算』シリーズで合格に必須な「計算力」を。
しばらく数学の計算から遠ざかっていた医学部再受験生は、この参考書で素早い計算力を身につけてください。
 |
|
新品価格 |
終盤は、『理系数学の良問プラチカ』で高難易度の試験問題にも対応できるようにしましょう。
この参考書では問題一つ一つの「理解」に努めると、医学部再受験の合格につながる究極の数学力を養うことができます。
 |
|
理系数学の良問プラチカ 数学1・A・2・B (河合塾シリーズ 入試精選問題集 5) 新品価格 |
数学を専門的に扱っていた医学部再受験生はあまり困りませんが、改めて高校数学を勉強する医学部再受験生にとっては出題範囲が広範で、かつ問題演習量が鍵を握る理系科目については、「効率よく網羅的に」学習することが合格のカギになります。
医学部再受験生はぜひ、数学の参考書選び・問題演習でもこのポイントを意識してください。
化学
化学は、ほとんど全ての医学部再受験生が選択する理科の科目です。
化学は理論・無機・有機とに分かれていますが、特に理論化学の理解を重要視してください。
応用問題や高難易度の問題に対する理解力の差は、理論化学の理解度が大きく左右するからです。
高校化学は高校物理よりも数学色が強くなく、その代わり、理論など暗記の方に重点が置かれています。
だからと言って、初めから闇雲に覚えようとするのはダメ。
最も定着力のいい暗記は、「理解すること」なのです。
医学部再受験生は、ぜひ、理解に重きをおいた参考書選び・問題演習を心がけてください。
序盤〜中盤では、『鎌田の理論化学』『福間の無機化学』『鎌田の有機化学』の3つの参考書で基礎から勉強してください。
これらの参考書は独学でも深い理解が得られるとしてレビューの高いものです。医学部再受験で合格するために必須である、応用力の基礎をここで養ってください。
もしも化学に苦手意識があったり、途中で挫折しそうなときは、『宇宙一わかりやすい高校化学』をおすすめします。
終盤では、『化学 重要問題集』で問題演習を行ってください。
内容はセンター基礎から医学部合格レベルまで十分な問題量となっています。
医学部再受験生はぜひ、2,3周することを目標にしましょう。
ちなみに、化学はここ数年での変化は大きくないので、中古参考書でも問題はありません。
 |
|
新品価格 |
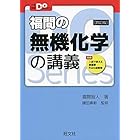 |
|
新品価格 |
 |
|
新品価格 |
物理
理科2科目の選択で多くの医学部再受験生が選択するのが物理。
物理の参考書には有名な著者が数名いるのですが、それぞれで解法のアプローチが異なるのが特徴です。
個々の医学部再受験生にとって、理解しやすいアプローチがあるものですが、ここでは分かりやすいという声が最も多い、有名予備校、河合塾講師の浜島清利流の解法パターンを身につける参考書セットをご紹介します。
序盤では、『浜島清利物理講義の実況中継』と『物理のエッセンス』でセンター基礎から医学部合格レベルまで、網羅的に学習しましょう。
前者の参考書は講義形式ですので、改めて物理を学習しようとする医学部再受験生におすすめです。
逆に、ある程度高校物理の記憶が残っている医学部再受験生は、後者の参考書からの学習で十分でしょう。
もしも化学に苦手意識があったり、途中で挫折しそうなときは、『宇宙一わかりやすい高校物理』をおすすめします。
中盤では、『良問の風』で問題演習を積み、理解の定着を図りましょう。
物理を解く上で重要な「本質を捉える」力を養うのに最適な参考書なので、医学部再受験生にもおすすめです。
 |
|
新品価格 |
終盤は、『名門の森物理』で医学部レベルの応用力を養いましょう。
「受験物理の最後の参考書」とまで称される最良の問題集・参考書です。
この参考書をマスターすれば、ほとんどの入試問題は解けなければならない問題になるとまで言われるほどです。
医学部再受験生はぜひ1冊、しっかり最後までやり抜いてください。
ちなみに、物理の参考書はいずれも中古でも問題ありません。
 |
|
新品価格 |
生物
理科2科目として物理と対をなす存在となっている生物。
生物を選択した医学部再受験生は、特に「出題内容」「用語」に注意して学習を進めてください。
他の理系科目と同様、生物もここ数年で内容が大きく変更されていますが、「好気呼吸」→「呼吸」といった細かい用語の変化も起きています。
既習している医学部再受験生も、必ず一度は全範囲の基礎を網羅しましょう。
序盤は、『大森徹の最強講義117講』で全範囲を学習してください。
この参考書は講義形式で問題自体はほとんどありませんが、センター基礎から医学部合格まで十分な内容です。
医学部再受験生にとって、生物学習の導入として非常に評判の高い参考書です。
 |
|
新品価格 |
中盤では、『生物 基礎問題精講』で問題演習を行い、正答率の向上を目指しましょう。
生物の学習において最も重要とされるのが、この「アウトプット」問題演習です。
覚えた・理解したつもりの内容も、アウトプットできなければ試験には役立ちません。
医学部再受験生は、この参考書を何周もして、ぜひ理解・記憶を定着させてください。
 |
|
新品価格 |
終盤では、『生物 標準問題精講』で医学部レベルまで持ち上げましょう。
この参考書は少し解説が簡素ですが、他のどの参考書よりも問題の網羅性が優れているため、一通りやることで受験生物の典型問題に目を通すことができます。
生物で学習した内容は、もちろん医学部進学後も活かされます。
特に、人体以外の植物や進化論についての知識は、医師としての教養にもなるため、ぜひ知的好奇心を振るって学習しましょう。
なお、生物の参考書選びでは、内容の改変が多いという特徴から、中古での購入はお勧めしません。
 |
|
新品価格 |
共通テスト(旧センター試験)
医学部再受験において、国公立大学医学部の合格を目指すのであれば、共通テスト対策が必須です。
しかし、共通テストは2021年度入試で初めて導入されたばかりで、センター試験対策の参考書の方が多いのが現状です。
共通テスト対策の参考書をやり切った医学部再受験生は、センター試験対策の中古本などで勉強してください。
ここでは、簡単に、医学部再受験生の共通テスト対策でおすすめの参考書をご紹介します。
英語、数学、理科2科目については、上で述べた参考書を活用して勉強してください。
その上で、共通テスト対策としては、Z会の『共通テスト 実践模試』で問題演習をしましょう。
なお、共通テスト対策の参考書は常に最新の情報を取り入れるために、中古での購入はお勧めしません。
 |
|
新品価格 |
国語・社会についても同様に、Z会の『共通テスト 実践模試』で勉強を進めることをお勧めします。
ここからは、国語・社会の各科について、簡単におすすめの参考書をご紹介します。
ちなみに、文系科目は改訂が少ないので中古参考書で問題ありません。
現代文は、『決める!センター現代文』で、共通テストにも引き継がれているセンター試験独特の「解き方」やパターンを勉強しましょう。
現代文の問題演習に不安がある医学部再受験生は、『出口の現代文レベル別問題集』も利用しましょう。
古文は、『富井の古典文法をはじめからていねいに』がおすすめです。文法をマスターしなければ合格点は勝ち取れません。
漢文では、『漢文早覚え速答法[共通テスト対応版]』がおすすめ。これだけで国公立2次レベルまで習得できるとまで言われる良書です。
地理は『村瀬のゼロからわかる地理B』、現代社会は『共通テスト現代社会集中講義』、倫理は『蔭山の共通テスト倫理』、政治経済は『蔭山の共通テスト政治経済』、日本史・世界史は『講義の実況中継』シリーズがおすすめ。
いずれも講義形式で、独学の医学部再受験生に評判の高い参考書のため、amazonでもランキング上位に位置しています。
問題集ではないため、問題演習はセンター試験対策の参考書などを活用してください。
 |
|
新品価格 |
参考書・テキストは手を広げ過ぎないのがポイント

参考書で勉強している人の多くが陥りやすい傾向として、教材の手を広げ過ぎて勉強が中途半端になってしまうことです。
医学部予備校生は、基本的に与えられた教材に特化して何度も繰り返し学習するため、理解をどんどん深めていくことができます。
しかし、独学で勉強していると今の学習範囲では足りていないか不安になり、ネットなどで推奨されている参考書を買い集め、結局はどれも最後までやれずに本試験を迎えてしまう人が多く見受けられます。
特に国立大学医学部は、私立大学と違いセンター試験があるため文系科目の対策も必要となり、その傾向が多いようです。
参考書を1周してもその内容を全て理解することは不可能なので、何度も繰り返して対策することが重要です。
そのほうが効率よく学力向上が実現するだけでなく、1冊終わらせたという達成感を味わうこともできるので次の勉強へのモチベーションも高くなります。
したがって、独学で勉強する際は、最低限の参考書に留めてボロボロになるまで勉強することを目標にしましょう。
それでも、時間を持て余すようであれば、追加でその都度教材を購入するほうが、効率的かつ経済的です。
問題集の解答を確認するだけでは不十分
よく、医学部再受験生で参考書を使って勉強する場合、間違った問題は解答を確認して次に進む人がいますが、これだと次に似たような問題を解く際に同じ間違いをするリスクが高いです。
ケアレスミスであれば、解答を確認して訂正するだけで問題ありません。
しかし、根本的な知識や解法を理解していない場合は、解答を確認するだけでは十分です。
なぜ間違えたのかを考え、知らなかった、あるいは理解していなかった論点はテキスト等に戻ってしっかりと復習を行いましょう。
同じ問題集を何度も繰り返いしていると、たまに解答を覚えてしまっていて作業的に解いてしまうことがあります。
この場合、本試験でちょっと視点を変えた出題がされた場合は対応できないでしょう。
本質的な理解があれば、応用や初見の問題でも対応できる学力が身に付きます。
したがって、参考書を使った日ごろの問題演習の時から、しっかりと解法や論点をちゃんと理解しているかを確認しながら丁寧に解いていくことが大切です。
医学部再受験生も適度に予備校を利用していく
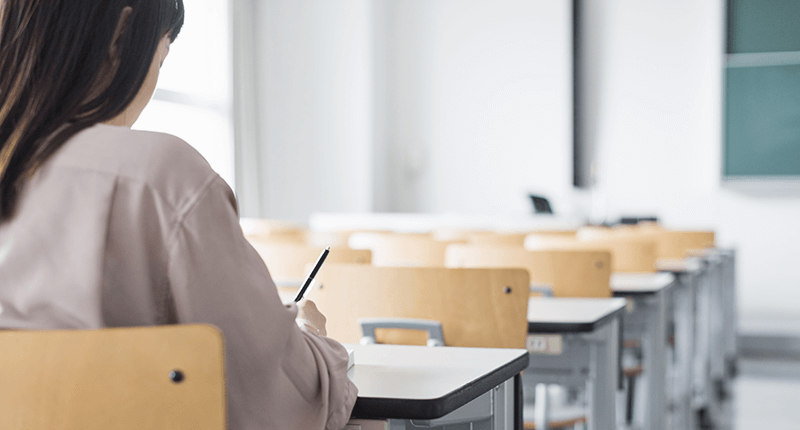
参考書だけ使って独学で医学部を目指すことは再受験生に関係なく難関医学部入試を合格するには非常に困難となります。
しかし、特に社会人の方は親から経済的に独立しているため、学費の高い医学部予備校に通えない人もいるかと思います。
この場合、短期講座や単科講座を活用して講師から指導してもらうことで、誤った理解の修正や苦手な論の克服へとつなげていきましょう。
また、期間限定あるいは科目を絞ることで学費の費用負担を大きく抑えることもできます。
特に独学の医学部再受験生は、勉強していて分からない論点があっても質問できる相手がいないので、苦手な分野を作りやすい傾向があります。
参考書を使って完全に独学するのではなく、上手く医学部予備校などを利用しながら勉強することが合格への最短ルートとなります。
河合塾と駿台の模試は受験必須
独学を選ぶ医学部再受験生の河合塾と駿台の模擬試験は必須です。
模擬試験は、本試験の予行練習になるのはもちろん、現役生や浪人生を含めて多くの医学部志望者が受験するため、現在の学力の立ち位置や知識のヌケ・モレを把握できるからです。
さらに、大手予備校や医学部予備校が実施する模擬試験からは、毎年多くの的中問題が出題されているので模試は受けていて損はありません。
模擬試験はそこまで受験料は高くならないので、大手予備校だけでも利用しておくことをおすすめします。
医学部再受験生が独学するメリット・デメリット
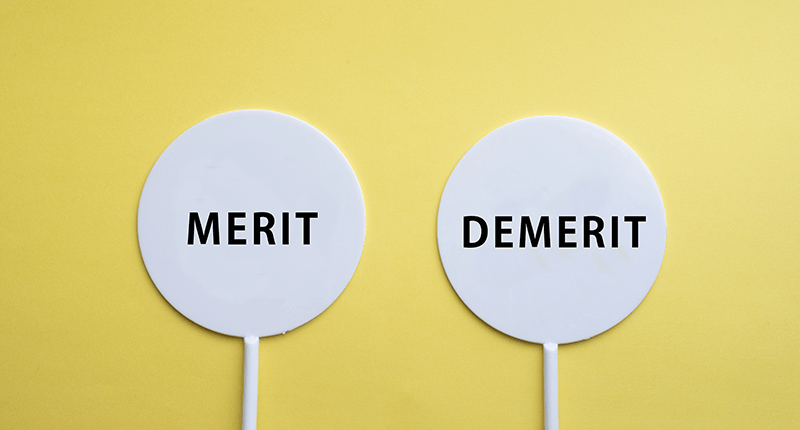
| メリット | デメリット |
|---|---|
| コストが安い | 質問や相談できる相手がいない |
| 勉強の時間や場所に拘束されない | モチベーションの維持が難しい |
| 辞めるのが簡単 | 継続して勉強するのが困難 |
| マイペースに学習可能 | ライバルとペースが遅れる |
独学最大のメリットは費用面
独学の最大のメリットは何と言っても勉強にかかる経済的負担を大きく抑えられることではないでしょうか。
医学部予備校の学費と言えば年間200万円以上も当たり前のなか、独学であれば参考書代と模試代くらいで済ませることが可能です。
と言うことは、かかった費用も少ないので途中で医学部再受験を止めようと思った時も経済的なダメージは少なく諦めた時の後悔も最小限で済みます。
また、自分が勉強したい時間に好きなだけ集中して行えるので、時間や場所に拘束されることなくマイペースに勉強できる点も魅力に感じる人は多いと思います。
講師などから勉強をやらされているという受け身の姿勢ではなく、自分から学ぼうとする意欲や姿勢は、勉強の質を高めてくれます。
モチベーションの維持や質問できないデメリットに注意
いっぽう、独学にはデメリットもあるので医学部再受験を始める際は慎重に検討するようにしましょう。
まず、独学は自分で参考書とにらめっこしながら勉強していくので、分からない場所があっても質問する相手がいません。
分からない箇所を放置しておくと、そこが苦手分野になりやすいので全ての科目で高いレベルが要求される医学部入試では致命的となってしまいます。
また、独学は孤独であるがゆえ、モチベーションの維持は困難であり、勉強が嫌になってそのままフェードアウトしていく人も少なくありません。
医学部予備校は授業で直接教えてもらえるだけでなく、質問や相談の対応もそうですが、同じ医師を志す仲間と切磋琢磨できる環境が大きな魅力であり勉強の原動力となります。
独学で勉強していると刺激を受けることも少なく、またマイペースに勉強できる分、ライバルなどの進捗に比べて遅れを取ってしまう危険性もあります。
学習計画の実行力があり、自己管理ができる人でない限りは独学で医学部再受験合格は難しいかもしれません。
まとめ
参考書を使った勉強で合格を実現することは不可能ではないですが、医学部再受験生ほど予備校などで対策したほうが合格できる可能性は高まります。
それだけ圧倒的な勉強量と手厚いサポートが必要だということです。
しかし、医学部再受験生は様々な事情があり、金銭的に予備校が利用できない人がいるのも事実。
この場合、模試や季節講座を受講しながら参考書で対策を行い、上手く予備校の情報やノウハウを利用していきましょう。
そして、自分の学力に合った参考書を適切に選び、1つ1つしっかりと理解しながら勉強を進めていくことが医学部再受験を成功させるために必要となります。