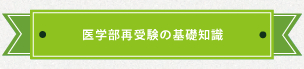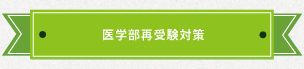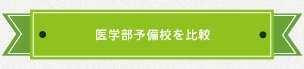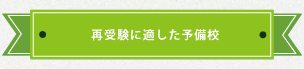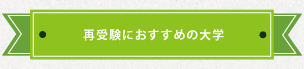医学部再受験生は年齢が通常の受験生よりも上がるため、医師になるときには何歳になっているのか。
ここでは、医師として活躍するまでには何年かかるかを、医学部医学科へ入学後から紹介していきたいと思います。
医学部医学科は何年制?

日本の医学部は6年制
大学の学士課程は4年間が一般的ですが、医学部医学科は6年で卒業です。
したがって、医学部卒業生は修士課程を修了したとみなされます。
6年制を採用しているのは医学部以外にも薬学部や歯学部など医療系の学部に多く、それだけ専門的な知識と豊富な実習が必要とされていることになります。
特に近年は医療技術の発展が著しく医療は高度化・複雑化しており、学士課程でも学ぶべきことが多く6年という長い時間をかけて学んでいくことになります。
したがって、医学部再受験生の場合は、卒業したら30代というケースは珍しいことではありません。
海外の医学部事情
海外の医学部は日本とは制度や仕組みが違うことが多いです。
イギリスは日本と同じように、高校卒業後に共通試験や国際バカロレアを受験して医学部に入学し、5年から6年かけて学びます。
また、留学先として人気の高いアメリカでは、高校卒業後に一般の大学で学士号を取得した後にメディカルスクールに通うという仕組みになっており、医学部は日本での大学院に相当しています。
同じく留学先として人気の高いオーストラリアも最近は学士号取得を条件にしている医学部が増加。
国によって医学部が何年制か、また、医師になるまでのプロセスも異なってきます。
外国の医学部で学ぶという選択肢

実はここ何年かで、医学部受験生の中で海外の大学医学部への受験を検討する人が増えてきています。
フランスやドイツ、カナダやアメリカなどその選択肢は広く、ここ10年で海外医学部への日本人合格者数は増え続けています。
特にハンガリーと中国は人数が多く、30人近くの日本人が同時期に合格した年もあります。
また、タイやフィリピンなどの東南アジアへの留学がここ何年間では人気が急上昇。韓国や台湾など、日本に近く言語も日本語に文法が似ていることから比較的学びやすい特徴があります。
外国の医学部は何年で医者になれる?
では、海外の医学部に行けば何年で医者になれるのでしょうか?
海外大学を受験するとなると、その国の言語(多くの場合英語)を習得する必要があります。これに何年もかかる人もいれば、なんなくクリアする人もいて様々です。
また、医学部自体には4年〜7年と国によって何年で卒業できるかはバラバラ。ただ、平均は日本と同じ6年間のよう。
さらには海外にも当然のように留年があり得るので何年で卒業できるは自分の頑張り次第とも言えます。
加えて、海外の医学部卒業後には現地での医師免許試験合格が必要です。
多くの国で受験前後に何年かの臨床研修経験(だいたい1-2年)を積むことが条件とされているため、現地で一人前の医者になるのにまず何年かかかってしまいます。
その後に日本の医師免許を取得できるかは国により制度が異なり、申請のみで日本の医師免許が発行される国もありますが、多くは新たに日本の医師国家試験を受験する必要があります。
そのため、海外医学部卒業後に日本の医師免許を取得するには、実際には日本の医学部を卒業するより何年ものギャップが生まれることに。
この何年かのギャップの存在から、医学部再受験生のほとんどは海外医学部を敬遠してしまいます。
しかし、海外医学部に通うことでメリットも多くあります。
それは、多国籍が集まる場で学ぶことで人間性を大いに磨くことができること、さらにはオックスフォード大学やハーバード大学など有名大学へのエントリーがしやすくなることです。
日本の大学を卒業するより何年も時間を要しますが、得られるものもそれだけにとても大きなもの。ぜひ、海外大学医学部という選択肢も検討してみましょう。
大学在学中…留年は決して珍しくない

日本の医学部は6年かかりますが、実際には6年で卒業できない人も決して少なくありません。
医学部では、その学習量のせいからか、昔から留年という事実が決して珍しくなく、何年か留年したという人もざらにいます。
しかし、何年も留年できるわけでもありません。原則として、一つの学年を留年できる回数は2回までと制限が。
それ以上の留年は、放校となります。
また、留年の危機に直面すると休学届を提出しその年を休学扱いにすることでこの足踏み制限を回避するという人もいるほど。
ちなみに、進級に際して毎年進級試験を課す大学もあれば、ほぼ全員がストレートで卒業できるような大学もあります。
文部科学省は毎年、その年の国家試験の受験者数や合格率などとともに、各大学のストレート合格率が算出できるようなデータを公表しています。
以下に、そのデータから算出した国公立大学医学部・私立大学医学部それぞれの、平成28年度入学者のストレート卒業率ランキングトップ10をお示しします。
東大や京大など名門校であればストレートに進学できるというわけでもないと言うことがお分かりいただけると思います。
国公立大学医学部
| 順位 | 大学名 | 平成26年度入学者 | 第114回国家試験(令和2年3月) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学者数(人) | 6年次ストレート進級率(%) | ストレート卒業率(%) | 合格率(%) | ||
| 1 | 大分 | 91 | 100.0 | 100.0 | 93.5 |
| 2 | 愛媛 | 105 | 100.0 | 99.0 | 94.0 |
| 3 | 和歌山県立医科 | 84 | 100.0 | 97.6 | 100.0 |
| 4 | 三重 | 125 | 96.8 | 96.0 | 95.3 |
| 5 | 名古屋 | 116 | 95.7 | 95.7 | 93.3 |
| 6 | 浜松医科 | 120 | 94.2 | 94.2 | 96.7 |
| 7 | 札幌医科 | 110 | 93.6 | 92.7 | 94.0 |
| 8 | 神戸 | 117 | 92.3 | 92.3 | 95.8 |
| 9 | 東京 | 100 | 94.0 | 92.0 | 96.0 |
| 10 | 鹿児島 | 117 | 94.9 | 91.5 | 99.1 |
私立大学医学部
| 順位 | 大学名 | 平成26年度入学者 | 第114回国家試験(令和2年3月) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学者数(人) | 6年次ストレート進級率(%) | ストレート卒業率(%) | 合格率(%) | ||
| 1 | 東邦 | 92 | 100.0 | 100.0 | 95.0 |
| 2 | 順天堂 | 127 | 96.9 | 96.1 | 99.2 |
| 3 | 自治医科 | 123 | 92.7 | 92.7 | 100.0 |
| 4 | 東京女子医科 | 112 | 92.0 | 92.0 | 92.5 |
| 5 | 獨協医科 | 121 | 91.7 | 91.7 | 89.1 |
| 6 | 久留米 | 115 | 91.3 | 90.4 | 87.8 |
| 7 | 慶應義塾 | 113 | 91.2 | 90.3 | 99.1 |
| 8 | 東京慈恵会医科 | 111 | 90.1 | 90.1 | 95.4 |
| 9 | 金沢医科 | 115 | 84.3 | 84.3 | 84.5 |
| 10 | 藤田医科 | 110 | 83.6 | 83.6 | 94.6 |
何年生で留年することが多いか
医学部では留年すること自体決して珍しくないことをお伝えしまたが、実は留年の可能性が高まる「関門」とされる学年は限定されています。
というのも、医学部で学ぶ内容は国家試験に向けたものとして文部科学省で決められており、大学によってカリキュラムが異なるものの、大きな枠組みは変わらないから。
簡単に医学部のカリキュラムを示すと、
- 1年生:教養科目
- 1年生〜2,3年生:基礎医学
- 2,3年生〜4年生:専門医学
- 4年生〜6年生:臨床実習
このようになります。
この4つに分かれたそれぞれのタームの中では、留年することはありません。
逆に、それぞれのタームの節目が、留年の危機になります。
特に注目すべきは、1年生の終わりに留年の危機があるということ。
医学部再受験に限らず、辛い受験勉強を乗り越えてきた医学部受験生の多くは、医学部入学ととともに肩の力が抜けてしまうもの。
その状態がしばらく続いてしまい、1年生を終えようとすると留年。
なんて流れはかなりあり得る話で、実際、多くの医学生はこの1年生から2年生の間で留年をしています。
ただでさえ6年制で医者になるにはかなりの年月を要するのに、学生生活で足踏みをしてしまうのは勿体無いもの。
実際のところ、医学部再受験生で留年する人というのは比較的少ない印象ではありますが、他人事と思わず、努力が実り医学部入学が叶ったとしても、6年間身を引き締めてストレート卒業してください。
卒業後は何年で医師になれる?

医師国家試験で医師免許取得
医学部を卒業したらまずはすぐに医師免許を取得する必要があるので国家試験を受験することになります。
実際は、国家試験は2月上旬の日程で実施されるため、卒業見込みの状態で受験することになりますが、各大学医学部での卒業試験に合格していないと受験できません。
また、医師国家試験の合格率は9割程度と高いですが、全員が合格しているわけではないので注意しましょう。
合格率が9割程度なのは現役生のみで、国試浪人をすると1年目で5割、2年目では3割を切るなど合格率は急激に下がります。
医学部を卒業できても何年も国試に合格できず、浪人生活を送っている人もいるのは事実です。
なお、医師国家試験合格率は簡単に調べることができ、これを元に受験大学を選択することも可能です。
しかしここでも注意が必要。
医師国家試験の合格率は各医学部の指標としても見られるため、大学としてもその数字は気になるところ。
中には、5-6年生の段階で医師国試合格に学力が及んでいないと判断した学生を留年させてそもそも医師酷使を受けさせまいとする大学もあるほど。
そのため、受験校選びの際には、医師国試合格率のみではなく、ストレート卒業率なども比較して検討しましょう。
医師国家試験に合格すると免許を取得し医籍登録ができるので、その後は病院で初期臨床研修に参加して研修医として経験を積むことになります。
卒後は初期臨床研修2年が必須
医者になるためには、医師免許取得後に初期臨床研修へ参加することが義務付けられています。
なお、初期臨床研修を修了しない限り、保険診療を提供できないので、実際に医師として活動することができません。
2020年度から必須科目が大幅に増加して3科目から7科目へ変更となり、外科、小児科、産婦人科、精神科、内科、救急科、地域医療の科目を経験することが求められています。
初期臨床研修を修了すれば2回目の医籍登録が完了し、いよいよ医師として活動していくことになります。
つまり、医学部を最短で卒業し医師国試に合格しても2年の初期研修期間を終えない限りは、法律上も一人前の「医師」にはなれないのです。
やはり時間がかかるので、今後のキャリア形成を見据えて医学部再受験生は1年でも大学に合格することが重要です。
博士課程へ進学や専門医の取得も多い
初期臨床研修を修了すれば医師として活動することが可能ですが、多くの人は大学院の博士課程へ進んだり、専攻医研修プログラムに応募して専門医研修に進んだりしています。
博士課程へ進んで博士号取得や研究医を目指す人もいれば、専門医を取得して高度な医療を提供を目指す医師を目指す人もいるなど、様々な道へ進んでいきます。
医療の高度化・複雑化に伴い、医師としての経験も必要ですが、知識や技術を取得するために継続して何年間も勉強することが医者という仕事には求められているのです。
ただし、それぞれが目指す医師になるまでには何年もかかるもの。
例えば初期研修2年を終えた多くの医師が進む「専門医研修プログラム」も3-4年の研修後の専門医試験に合格して初めて『専門医』に。
その後は『認定医』『指導医』などさらにプログラムが用意されており、途中で『産業医』など他の医師資格を持とうとすると何年もかかるのが伝わることと思います。
医者は一生勉強。まさにそれ実感するキャリア形成です。
学士編入なら医学部生活を短縮できる
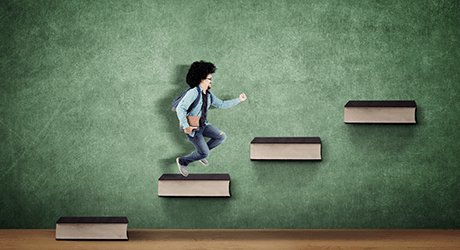
社会人など他大学を卒業して学士号を取得している医学部再受験生の場合、学士編入試験を利用すれば、医者になるまでの期間を何年か短縮可能です。
国公立大学医学部を中心に学士編入制を実施しており、何年生から編入になるかは大学次第。1年次後半や2年次編入が主流ですが、なかには3年次に編入できる大学も。
社会人の場合は年齢が30代という人も珍しくなく、医者になるまでに何年もかかっていては、キャリア形成も遅れてしまいます。
学士編入で効率よく医学部医学科を卒業できれば、その分早く医師として経験を積むことが可能です。
学士編入は途中入学だから同級生と差が出る?
学士編入を敬遠する人の中には、このような感情を抱く人がいるようです。
ただ、答えは明確に『NO』。
医学部の多くはカリキュラムの中に一般教養を含めています。
つまり、6年間のうちのはじめ何年かは一般教養を学ぶ時期で、多くの大学はこれを1年間としています。
したがって編入で何年生から入学しても、「医学を学び始めるタイミング」自体は同じなので心配はいりません。
編入学年が何年生かは大学により異なりますが、これは大学それぞれでカリキュラムが違うからです。
多くの大学で、カリキュラムの最初に人体解剖が行われますが、当然編入生も、これに参加するところからになります。
まとめ
医学部再受験を始めて医学科に合格できた場合、学士課程に6年、初期臨床研修に2年と医師になるまでには最低8年を要することになります。
ただし、医学部は留年する学生も少なくないので、卒業までに何年かを要することも珍しくありません。
また、医師国家試験も合格できずに何年も浪人している人だっています。
初期臨床研修が終えても、専門医の取得を目指す医師がほとんどであるため、医師になるまでには何年もの時間が必要となることに。
したがって、医学部再受験生ほど合格の時期が遅れれば、それだけキャリアへの影響も出てくるので、1年でも早く合格することが重要です。